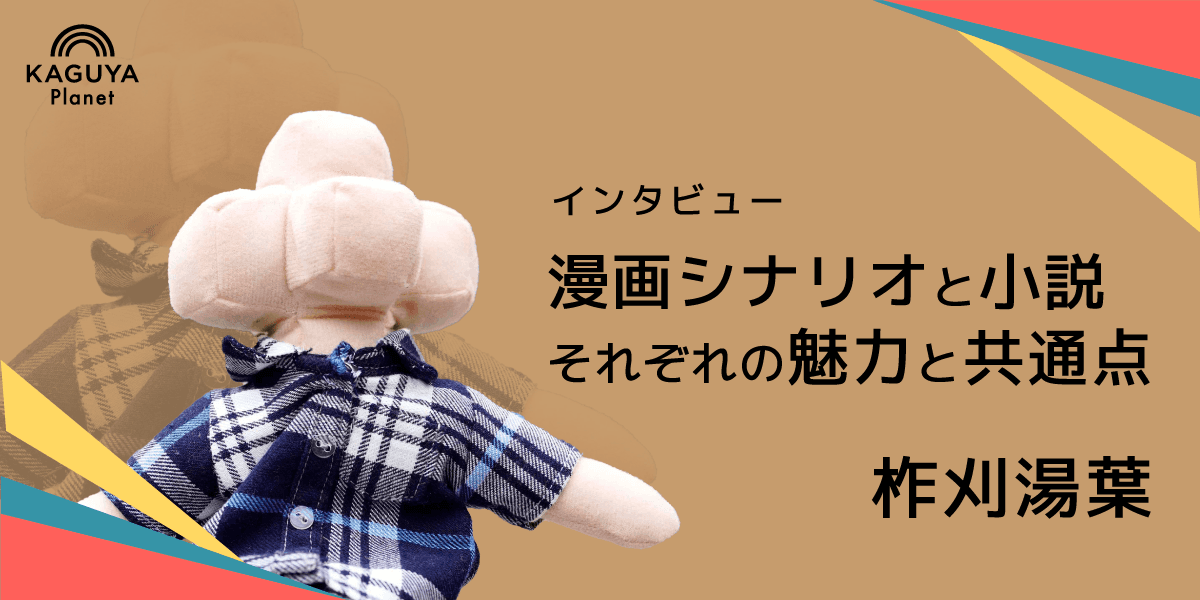
柞刈湯葉インタビュー:漫画シナリオと小説、それぞれの魅力と共通点
2016年に『横浜駅SF』でカクヨムWeb小説コンテストSF部門大賞を受賞しデビューして以来、『重力アルケミック』(星海社FICTIONS)や『まず牛を球とします。』(河出書房新社)などのSF小説、漫画『オートマン』(講談社)の原作、旅行エッセイ集『SF作家の地球旅行記』(産業編集センター)、SFプロトタイピングなど、様々なジャンルの仕事を手がけてきた柞刈湯葉さん。現在は、ジャンプTOONで毎週火曜日に更新中の『ぬのさんぽ』のシナリオを手がけています。『ぬのさんぽ』→【公式サイト】
そんな柞刈さんに、小説と漫画の表現の違いや通底する「ユーモア」の作り方、SFプロトタイピングから見えてきたSF作家の役割などについてお聞きしました。
◇◇◇
覆面作家として活動していく際のお役立ち情報などもお聞きした、柞刈湯葉さんのインタビューのフルバージョンは『Kaguya Planet No.4 プラネタリウム』に掲載しています。詳細は【こちら】
◇◇◇
漫画のシナリオってなにをしているの?
──今ジャンプTOONで連載されている『ぬのさんぽ』という漫画のシナリオを担当されていますよね。シナリオの執筆についてお話を聞かせてください。漫画のシナリオと作画は、どんな役割分担で、どうやって作業を進めているのですか。
まず僕が文章でシナリオを書きまして、それを編集さんを経由して作画の小津さんに送ります。それから数日すると、小津さんが「ネーム」という、コマ割りとセリフだけ書いたデータを送ってくれます。それで、僕と編集さんと小津さんとでそのネームを見ながらビデオ会議をして、このコマはこうした方がいいですねとか、このセリフこれに変えましょうみたいなことを色々話し合って、それが終わったら作画に入っていただきます。
作画も分業されていて、小津さんに描いていただいた線画に、色をつけて背景を描く夏本さんという方がいます。なので、このネームチェック会議が終わったら小津さんがその線画を完成させて、夏本さんに送って、色とか背景をつけてもらって、 文字を入れてもらって完成という感じです。
──『ぬのさんぽ』の企画や内容はどのように決まっていったのですか。
順番でいうと、作画を小津さんが担当してくださると決まったのが一番最初。漫画の原作は、企画内容を決めてから作画の人を選ぶこともあるんですけど、『ぬのさんぽ』は、作画が小津さんと決まってから内容を作りました。
当初の予定では、もっとおどろおどろしいハードめのSFをやろうと思っていて、その話を編集さんと一緒に練っていたんです。でも作画が小津さんに決まったので、じゃあもっと可愛い話にしようということになって『ぬのさんぽ』を作ったわけです。
連載を始める前に決めていたことは、主人公のサンポと相方のヌノだけ。最初はとりあえず、そこだけを決めていました。
──シナリオを書くのと小説の執筆では、頭の使い方は全然違いますか。
昔、講談社で『オートマン』という普通のヨコ漫画のシナリオをやったんですけど、その時は「小説とはけっこう違うな」と思いました。というのは、ヨコ漫画はページをどう区切るかが読むときの印象に大きく関わってくるんですよね。めくりというんですけど。僕はそこが不慣れなせいで、それがうまくできなかったなという印象がありました。
それに比べると『ぬのさんぽ』はタテ漫画なので「かなり小説と近いな」と思っています。画面をスクロールするだけで、ページめくりがないので。ですので、地の文のない小説みたいなシナリオを書いています。一コマ分ごとに区切りながら、セリフとその人物の動作だけを箇条書きで書いていくという方法です。
──では細かいポーズなどは作画の小津さんが決めているのですか。
そうですね。基本的にはそちらにお任せしています。
漫画と小説、表現の違いと魅力
──漫画には、小説にはできない表現とか、 小説とは違う魅力はありますか。
漫画にできることは漫画家さんの個性で決まると思います。小津さんは絵が大変可愛いので、この可愛さをどう見せるかという方向で考えていますね。
──柞刈さんの小説が大学生や大人が主人公なことが多い中で、『ぬのさんぽ』は中学一年生が主人公なのはそういう理由なんですか。
そうですね。小津さんは、とあるボカロ曲のミュージックビデオで大変有名になった方なのですが、そのキャラクターは小学生でした。なので、小学生のイメージの方が伝わりやすいとは思ったんですけれど、小学生だとやっていいことの範囲が狭すぎるかな、と思ったので中学生にしました。
あと、中学生にすると制服があるので、キャラクターデザインのコストが少なくてすむのですよね。作画の負担になるような設定はなるべく避けたいなという配慮で。
──確かに漫画だと、制服と私服では描くコストが違いますね。でも逆に、そこで個性を表現することができるという見方もありますよね。
服のデザインに関しては小津さんと色を塗っている夏本さんにお任せしているんですけど、例えばサンポの幼馴染みのランちゃんという子はイメージカラーがオレンジだそうで、私服を着る回も大体オレンジを着ています。その服のデザインがちょっとずつ違っていて、キャラクターの軸を持たせつつ、いろんな表現をしてくれていて、すごいなと思っています。
──できあがったイラストを見るのが楽しみですね。
はい、楽しいです。とてもかわいい絵なんで。
──柞刈さんの小説は、展開や設定の印象が強いです。その傾向に比べて、『ぬのさんぽ』はサンポが中学生であることも相まって、キャラクターが立っていますよね。
漫画はやっぱりキャラクターを立たせたいと思っています。あと今回は複数人で制作をしているということと、メディアミックスとかを目指したいという事情もあります。『ぬのさんぽ』は TOHO animation STUDIO が制作しているのですが、そもそもなんで東宝がウェブトゥーンを作るのかというと、アニメの原作が欲しいからなんでしょうね。そうなるとやっぱりキャラクターを面白くしないと。
──漫画と小説だと、ユーモアとか笑いの作り方に違いはありますか?
なんか違うなと思ってはいるんですけど……。表情を使った笑わせ方はどうしても漫画じゃないとできないとか、そういうのはあるんですけれども……。
漫画と小説の違いというよりは、一人で書くか分業で書くかの違いがあります。「笑い」ってかなりタイミングに敏感なので、分業にすると、細かい調整があまりうまくいかなくなるのですよね。そうすると、あんまりタイミングを活かした笑い方みたいなのではなくて、どう笑わせるかということになると……。僕もあんまり漫画でどう笑わせているのか自分の中でイメージできてはいないんですね。『ぬのさんぽ』だと、どんなところで笑いましたか?
──目覚まし時計のくだりとか……あとはサンポと同級生とのやり取りも笑いました。
確かに会話の見せ方は漫画の方がやりやすいです。漫画は小説と違って、三人以上で喋っても分かりやすいんですよ。『ぬのさんぽ』でいうと友達同士の三人組のやり取りがあるんですけど、これができるのは漫画の特権かなと思っています。
小説で三人が喋ると、どれが誰のセリフなのかわかりづらくなるので、すごい特徴的な語尾にするとか、ちょっと変な手段を使う必要があります。
──逆に共通点かなと思うのですが、『横浜駅SF』と『ぬのさんぽ』には両方、日常的なものや身の回りのものが違う文脈に置かれることで生まれるユーモアがありますよね。『横浜駅SF』では駅の構内のルールが未来の世界で変な形で残っていたり、『ぬのさんぽ』だと逃げる目覚まし時計の話が後半に予想外の展開を迎えたり……。そういうネタはどんなふうに探しているのですか。
どんなふうに探しているんだろう……。編集さんとごちゃごちゃ色々話し合った末に出てきているので、どう探しているかと聞かれると、自分でもピンと来てはいないんですけど……。SFはどうしても身近じゃない話になってしまうので、何かしら身近なものを取っかかりとして作ろうということは意識していますね。
──たしかに、『ぬのさんぽ』に出てくる〈宇宙遺物〉のありそうでなさそうなリアリティラインは、身近なものが取っかかりになっていますね。宇宙遺物たちのアイデアはどこから湧いてくるのですか。
どこから来てるのだろう……。『ぬのさんぽ』に出している〈因果を先取りする炊飯器〉の話でいうと、炊飯器はずいぶん色々なものが作れるんだなという印象があって、それをきっかけに本当に何でもできる炊飯器っていうのを思いついて、そこから話を膨らませたような感じですね。要は、身近にあるものに対する印象をちょっと誇張表現していくというものが多いですね。
SFプロトタイピングから見る、SF作家の役割
──『WIRED』に寄稿したり、SFプロトタイピングの仕事もされていますよね。どういう経緯でSFプロトタイピングの仕事をするようになったのですか。
一番最初は『WIRED』からウェルビーイングについての小説を書いてくださいという依頼が来て書いたんですけど、それが好評だったのかな。WIREDを介していろいろな企業とのSFプロトタイピングを依頼されるようになりました。
──SFタイピングではどんなことをされるんですか。
内容や時間に合わせて何種類かあるんですが、一番ちゃんとやる時は、僕と何人かの作家とWIREDの編集者で先方のオフィスに赴いて、社員の皆さんとワークショップをやります。
机に大きい模造紙を置いて、主人公のペルソナとか、登場人物のキャラクターとか、舞台設定とか、〇〇がない世界を考えようみたいなテーマなどを色々与えられて、そのお題に対する自分なりのイメージを、僕や社員の方が書いていき、それをまとめて、最終的に一本の小説に仕上げるということをやりました。
──社員の人たちはどんなことをするんですか。
基本やることは僕と同じですね。一緒にやりましょうって感じで。小説を仕上げることよりも、プロセスをみんなで体験していただくってところに意味があるみたいです。
あとは「SFプロトタイピングの体験をしてみよう」というイベントに呼んでいただいたこともあります。会場にいろいろな企業の人が何十人も集まって、「未来の食べ物を考えよう」をテーマに、ありそうな道具とか、そういう世界に生きていそうな人とかのアイデアをポンポン考えて、それに対して僕が、これはこうですね、これはこうですねと、ちょっと偉そうに(笑)コメントするということをやって。SFを作る過程を考えるというところに意味があるみたいですね。
──考える思考やプロセスに寄り添ったり、アイデアを出したりする存在として、作家がいる。
そうですね。想像力に定評のある職業みたいな感じ。つまり、企業の人が企業の中だけで考えていると、今あるものをどう変化させるかということばかりになってしまうので、もっと飛躍が必要で、そこで飛躍といえばSF作家だろうということで呼ばれているっぽいです。
──『WIRED』に寄稿されている小説は、特集のテーマをもとに、どうやってお話を組み立てていますか。
たとえば『WIRED Vol.40 特集:地球のためのガストロノミー』では、「食」がメインテーマで、そこに再生可能性や持続可能性なども織り込もうとすると、地球全体で考えると規模が大きすぎて分かりにくいなと思って、あえて舞台を月面基地にしたんですよ。別に宇宙にする指定でもないのに。
月面基地を舞台にすると、物質的なサイクルがすごく小さくなるんです。食べたものをCO2にして吐き出して、それが基地の中にある畑とかで光合成で固定されて、それをまた食べて……。テーマに沿いつつSF的な面白みも作れるようにしていこうと考えた結果、ああなったという感じです。
──どう表現したらテーマがわかりやすくなったり、掘り下げられるかということを考えているのですね。その辺の舞台設定を自由にできるのはSFならではですね。
こういう舞台でこういう話を書いてとか、細かい指定をされないのはありがたいですね。例えば「この道具を使ってSFを書いてください」という依頼はあるのですが、それが結局良いものなのか悪いものなのかみたいなことは特に指定されない、PRではないので。
SFプロトタイピングのようなものを企業がSF作家に頼んでくるということは、社会的なSFの役割というのは「問いを立てること」なんだろうなと思っています。この事業をやったらうまくいくのかどうかということを調べるのは、専門家の人たちがちゃんとエビデンスを集めてくるでしょうから、SF作家はそこじゃないところをやるんだろうなと。
──未来予測はSF作家の仕事ではないですもんね。
そうですね。予測が仕事だと思ってる人はけっこう多いんですけど、それは違うだろうと僕は普段から思ってるんですよね。SF小説に書いてあった未来が現実になった、すごいということは言われはするんですけど、意外と、昔からあったものをただ書いただけ、予言じゃなくて実況だったってことが多いですから。
──続いて、顔を出さずに活動をしていく作家の方々向けに、柞刈さんの経験を教えてほしいです……
▷▷▷覆面作家として活動していく際のお役立ち情報などもお聞きした、柞刈湯葉さんのインタビューのフルバージョンは『Kaguya Planet No.4 プラネタリウム』に掲載しています。詳細はこちら。
◇
このインタビューは2024年10月25日に行ったものです。(聞き手・構成 井上彼方)
柞刈湯葉(いすかり・ゆば)
小説家・漫画原作者。大学の研究職(生物学系)を経て、2016年に『横浜駅SF』でカクヨムWeb小説コンテストSF部門大賞を受賞しデビュー。『重力アルケミック』(星海社FICTIONS)、『まず牛を球とします。』(河出書房新社)などを刊行。現在はジャンプTOONで連載されている「ぬのさんぽ」のシナリオを手がけている。
