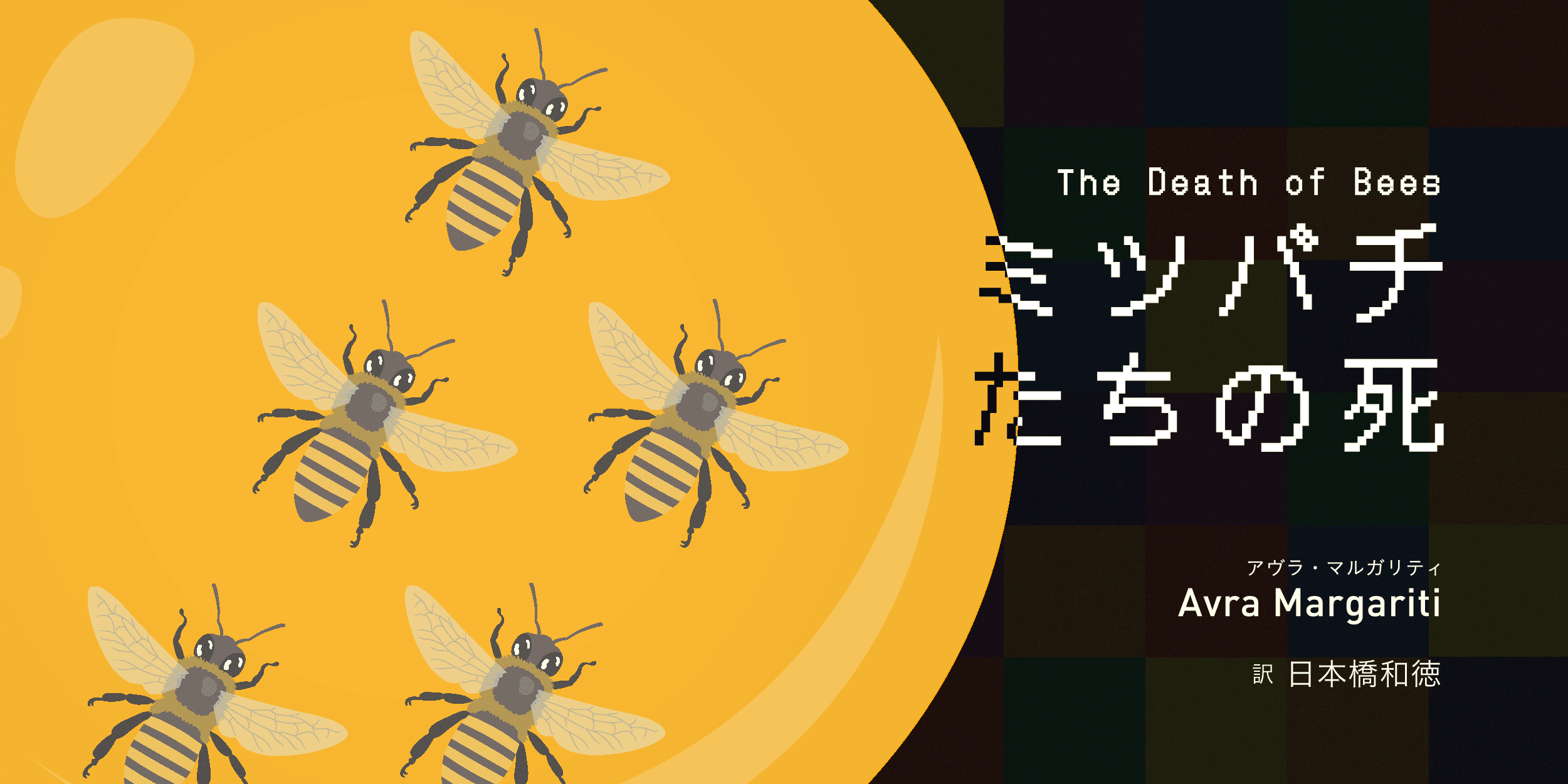
ミツバチたちの死
原題:The Death of Bees
1,646字
ボクのオンライン友だちは、ミツバチの個体数激減について論文を書いている。ボクは自分の寝室の窓から、ラベンダーの茂みを見た。毛に覆われた虫たちが、かわいい紫色の花にとまっている。
「どうしてうちのミツバチは、みんな元気であんなにたくさんいるのかな?」ホーム・スクーリングの最中に、ボクは父さんと母さんにたずねた。
台所のテーブルの向こう側で、二人は顔を見合わせる。「ミツバチに近寄っちゃいけないよ」両手をもみながら父さんは言った。
「ハチはみんな、怖い針を持っているじゃないの」母さんはやきもきしている。「ああ、そうよ、サラ。あなた、アレルギーでも持っていたらどうするの?」
ボクは目を白黒させて、数学練習シートの余白の落書きを再開する。
昼食の後、歴史の授業まで、父さんと母さんは二階で昼寝。その隙に、ボクはこっそり裏庭に出た。もしも父さんと母さんが、過保護で考えすぎのままなら、ボクがこの家を出ることはきっとないだろう。こんな奥地だから、家の外ですることもない。いちばん近所のお隣さんでも、何マイルも先に住んでいる。まあ、二人がそう言っているだけかもしれないけど。
刈り込まれた芝生とにぎやかな花壇が、裏庭のほとんどを飾っている。そこにジャングルがある。敷地の奥にある木製フェンスの近くにまで伸びきっていて、低木とごわごわした蔦の、ちょっとした雑木林になっている。ボクはジャングルのほうは無視して、ラベンダーの茂みをじっと見た。おばあさんのおしろいみたいな香りが、ボクの鼻の穴をくすぐる。太ったマルハナバチが、トゲの間を飛んだり、花房の上で休憩している。
ボクは自分の携帯を取り出して、アナスタシアにメッセージを送った。『そこにあるものが現実だって、どうしてキミにわかるの?』
アナスタシアは、オンライン友だちであると同時に、ボクのガール・フレンドでもある。ウチの両親は、彼女のことを知らない。どうせ二人は、こう言うはずだ。彼女とボクはお互いに触れ合えないし、現実世界の同じ空間にいることはできない。そんなのは、愛情じゃないって。
彼女の返事はすぐにやって来た。『自分で調べなよ、おバカさん』震えるハートでいっぱいの、絵文字のおまけ付きだ。
アナスタシアは新進気鋭の環境科学者で、こういうことに通じている。ボクは、ラベンダーの茂みの近くで腹ばいになって、情報を集めた。数えきれない数のハチが飛んでいる。どれもこれも、同じ渦巻き模様を描きながら花から花へと移動していて、少しも茂みから離れることはない。そのまま、何も変化がない。ここはやっぱり、実行あるのみだよね。ボクは指先を伸ばして、刺される心の準備をする。ところが、丸っこい虫たちはフラフラとのろい動きでボクに当たってくるだけで、すぐに元来たルートをたどって、やけにシンメトリックなダンスを再開した。
ミツバチたちの動きは、アナスタシアの論文内容と全然違っている。
ボクは裏庭を見渡した。どこも完璧で、どこもシンメトリックだ。ボクは家の窓を見上げた。カーテンは引かれたまま。口うるさいコンピューター・プログラマーの両親は、まだ昼寝の最中だ。そこでボクはたった一つの不協和音である、ジャングルへと踏み出した。春の空気が波立ち、トゲだらけの枝がボクの腕や足を引っかく。ボクは、ギリギリいっぱいまで手を伸ばした。その時、世界が色彩にあふれた。それからボクは、後ろに投げ出された。でもその直前に、虹色のベールの向こう側が覗き見えていた。
残像が、まぶたの裏で燃えている。それは、ボクが取り込まれているこの仮想バブルの外側にある、現実の世界だった。
ボクの傍の、芝生の上に落ちた携帯から、ピー、と音がする。文字を表示しているひび割れたスクリーンの上で、アナスタシアがいたずらっぽくニタニタ笑っている。『ところで、お宅のハチたち、どうしてる?』
指先が痒い。肌も心臓も脳みそも、同じようになんだかムズ痒くて、ボクは文字を入力していた。『キミが現実だって、どうしてボクにわかるの?』
告知
先行公開日:2021年7月22日 一般公開日:2021年8月28日
カバーデザイン:浅野春美
"The Death of Bees" by Avra Margariti
Daily Science Fiction, 2020 ©Avra Margariti
Translated with the permission of the author.
