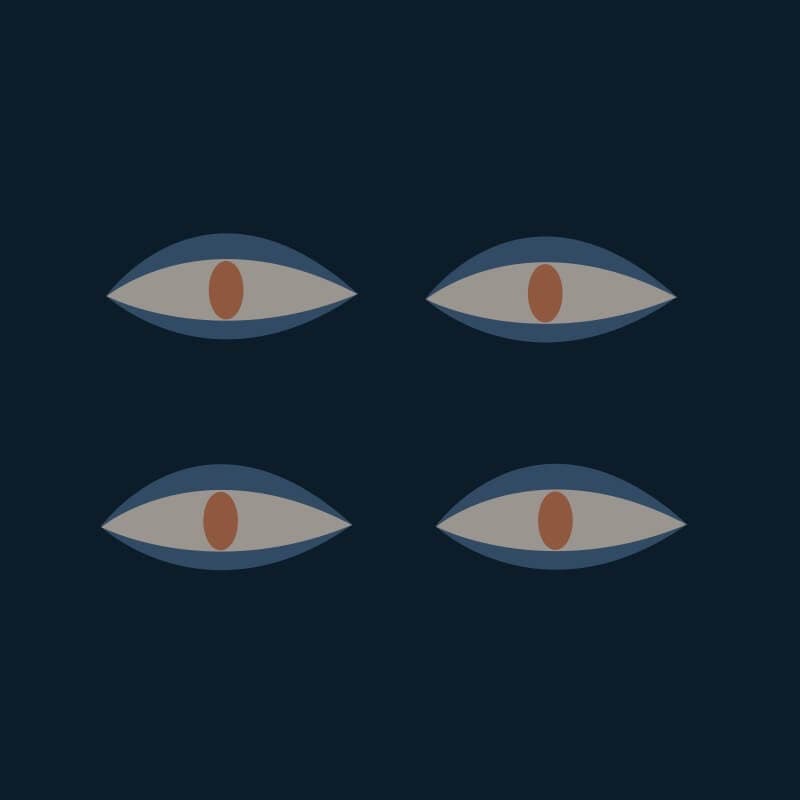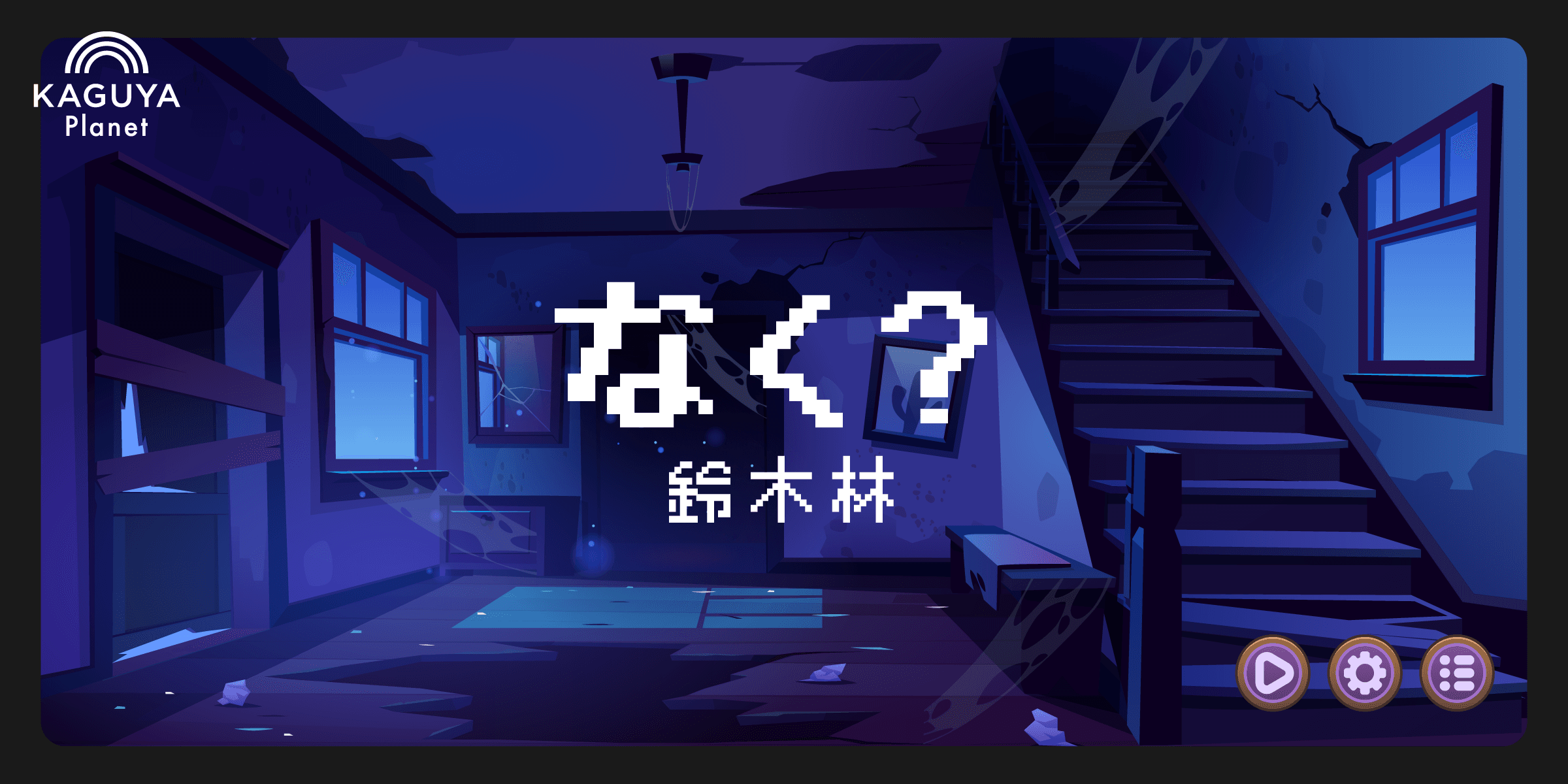
なく?
8,764字
作品ができた。リツとシモンがなにそれとよってくるのには、ありえないくらいどや顔する。先生のお手本をパクった建物や乗り物の工作がたくさんある中で、私の作品は見た目シンプルで逆に目立つ。
「すげえ」
シモンの声にリツははやくみせてとせがむ。私はニヤニヤする。まっ白なキューブの作品は、ひとつの面がフタになってる。そこを開けて中をのぞくと、急にいろんな色が目にとびこんでくる。私がつくった世界にたったひとつの動物園。布や色紙でできたうさぎ、ゴリラ、ライオン、ねこ、鳥、カエルがキューブの中で楽しそう。かれらが休むためのソファはフワフワのわたでつくって、うすい緑のモールできれいな木をつくった。水のみ場のふちにボンドではったビーズが光できらめく。セロハンでつくったステンドグラスがきらめきをふやす。リツとシモンは万華鏡みたいにキューブをくるくる回転させながら、「超かわいい!」「超かわいい!」って言う。ふたりの声にクラスのみんなも集まって、みせてみせてのつらなり。どや顔の私はホウヨウが乱暴にキューブをうばうのを止められなかった。
ホウヨウはみんなの手が届かないように、教室のうしろの棚にとび乗って、キューブをひとりじめした。
「うわまじですげえ」
実際かれは私のキューブに夢中になってたと思う。私はキレてた。ひとりじめされたのもあれだけど、こわされるんじゃないかと心配した。私はホウヨウの足をぐいぐいひっぱった。かれが厚紙でできたキューブをつぶすところを想像して、手に力をこめる。「返して、返して」と何度言ってもホウヨウは「すげえ、すげえ」としか言わなくて、とうとうかれの足が棚のはしから外にでた。落ちるなんて考えてなかったと思う。体のどこから床についたのかわからない。私はキューブだけをみてそれをさっと取ると、みんなの輪にもどっていった。ヒーローみたいに。「大丈夫?」って言ってる声がうしろから聞こえた。そのあとホウヨウがどうやって立ち上がって、どうやって私をにらんでいたかなんてわからなかった。またキューブをみせてわーきゃーやってると、背中をちょんちょんつつかれた。ふり返る。顔をまっ赤にしたホウヨウが、左手を前に出して、思い切り右手をうしろに引いていて、
はじめて顔面パンチくらった。せいいっぱいの強がりで、「そうきましたか」とか言ったけど、顔痛いし、私がさっきかれにしたことももしかして暴力だった!? っていう感じがすごいショックで、かなり泣いた。治してるところの歯肉炎からちょっと血が出てたみたいで、それをみつけたホウヨウは、「大丈夫?」とニタニタしながら言う。情けなくてさらに泣く。「全然、歯、これ出したほうがいい血だから」って言う私は恥ずかしい。
泣きやんだあとはむりやり平気な顔をした。授業が全部おわるとひとりで帰ろうとして、でもサミがいつものように寄ってきた。「かえろー」
サミは禁止されてるスマホをいじりながら、「ヤバいゲームみつけたから」っていつものように自分がしたい話ばっかしてて、私はそれでよかった。
「URLおくるからやってね」
「うん」
「感想ね、言ってね」
「うん」
親が知らないサイトとか、金かかんないゲームとかマンガにサミはくわしい。親のスマホはしょっちゅうは借りれないから、サミにおしえてもらって、うちのリビングにおいてあるパソコンでメッセはやる。サミからのURLはいつもあやしくて好き。
サミはプログラミングスクールがあるからってうちにこなかった。私はさっそくパソコンを立ち上げて、アプリをひらく。たったひとりフレンドになってるサミから、学校を出たあたりの時間にURLがおくられてきてた。カチッ。
英語ぽい画面が出る。たぶん英語。ページのまんなかにゲーム画面があって、動画みたいに再生ボタンがついてるわけじゃなく、ページにとんだ瞬間からもう動かせた。フルスクリーンにする。家の中、玄関に「私」はいた。キーボードの「W」をおすと家の奥にすすむ。コツコツ音がして、画面にうつっていない足が靴をはいたままなのだとわかった。
玄関はひろくて、目の前にはカーブした階段がある。天井にある丸いあかりが、あたりをふわっとてらしている。暗い水色の壁紙が、うちの家とちがっておしゃれ。「D」で右を向くと、ドアがある。そっちにすすみ、カーソルを合わせてノブをまわす。その先は子供部屋だった。白い木でできたベッドと、勉強机と、本棚がある。ベッドの上には動物のぬいぐるみが五個。壁紙はピンク。窓の外はくもり。
またこの家、と私は思った。祖母宅レベルになつかしい。ホラーゲームでよく使いまわされてる家の素材だ。サミがおくってくれるゲームで、何度もこの家を歩きまわった。玄関入ってすぐに階段があって、右の部屋が子供部屋って変なつくりで。
勉強机の上に絵がおいてある。お母さんとお父さんと、子供がならび、その横にまっ黒な背の高い人が描かれている。これも覚えてる。前にも遊んだゲームを、サミがまちがえておくってきたのかと思った。
机からはなれると、ベッドの下に一瞬長い手がみえた。やっぱり。これもみたことがある。前にもプレイしたゲームだったら、たしかクローゼットの中に、もうひとつの子供部屋の鍵がおいてあったはずだ。「私」は移動してクローゼットを開く。中にはフリフリの服がたくさんかかってて、下に<key><handgun><newspaper1>が落ちてた。ハンドガンなんてあったっけ、と思い出そうとする。新聞紙を開いて、出てきた言葉をキャプチャして翻訳する。「■■州▲▲市の一家死亡、心中か」と見出しにはあった。幽霊にとりつかれた父親が家族を殺してから自殺したっていうストーリーのやつだっけ、いや、子供部屋に、娘のひとりを監禁していたってやつじゃないか。思い出そうとする。
「私」は玄関にもどってから、家の奥へとすすむ。丸テーブルがあって、その上には料理ぽいものが乗ってる。全部つぶれた黒いかたまりになってて、もともとがなにかわからない。表面に開いたぶつぶつとした穴から赤茶色のねとねとが出てる。それにおぼれた芋虫がたくさん死んでる。カコン、と家のどこからか、缶が落ちるような音がした。で、あ、この黒い料理?もみたことある、って思い出して、でも自殺とか監禁とかと関係ない気もする。ハンドガンを使うようなストーリーだったとも思わない。
「Tab」キーで自分の持ち物を確認した。鍵、ハンドガン、新聞紙、そしてもともと持っていたらしいのが、女の子の横顔がほられたメダルで、<talisman>というものだった。知らないけどたぶんお守り系のアイテムだと思う。
部屋の奥の、ゴツい鍵がかけられたドアの前に、紙がおちてた。書いてあることをまたキャプチャする。「被験体1436の経過報告」。これも知らない。
──このゲームってやったことあるやつ?
そう思っちゃうよね、とスクールで勉強中のはずのサミからはすぐに返信がきた。
──たぶんだけど、このゲーム、いろんなゲームパクってんだよ。この家を舞台にしたいろんなゲームの要素を使って、つなぎあわせて、変なのにしてるわけ
──そういう、「ヤバい」ゲームか
──そうそう
ゲームをすすめると、サミが言ってたことがよくわかった。ストーリーのめちゃくちゃさについていけなくなってくる。悪魔、幽霊、殺人鬼、変な動物?、ミイラ、ゾンビ、ありとあらゆる設定と敵があって、でも肝心の弾がないからハンドガンは使えない、拾ったバールで二階の風呂の鏡をこわしてナゾ解きパズルをやっている間にでかい蜘蛛モンスターとのチェイスがはじまって、ころがったビール瓶をみると「私」はなにかを思い出したように苦しんで、操作性はどんどん最悪から最悪になってく。でも最悪って熱中できる。
──アレに会った?
一時間くらいたったころにきた、サミからのメッセが青いポップアップバナーで確認できた。アレがなにかわからない。手足切られたやつとか、口から虫をはくやつとか、いろいろいたけど。
──アレって?
──まだ会ってないか
何度目かの首吊り死体を二階の部屋でみると、それがフラグだったのか、うるさかったポルターガイストがおさまった。そのころには家中が血のあとで汚れていたんだけど、その血がどんどん灰色になって、ぶ厚くなって、もったりと重力でかたちを変えた。とかしたプラスチックがそこら中についてるみたいだ。さわってみると灰色はむちゅりと、絵の具ぽくえぐれる。さわった感じが、キーボードの上においた手に伝わってきた。ゲーム世界では「私」の体を壁につっこんでも、手の一部がバグぽくめり込んでみえるだけなのが普通なのに、灰色にさわった「私」の手をひっこめる瞬間にねっとりと糸をひいて物体がついてきて、私の脳がバグった。リアルぽさが変わっている。
壁紙が少しめくれたところから何かが出てきている。近づくと、何か、はハイライトされ、選択できるようになった。「私」は、何か、をひっぱる。ビニール袋だった。ぐいぐいひっぱった勢いで袋は床にたたきつけられる。中に入っていたジュースの紙パックと丸めたティッシュがこぼれ出る。ゴミだ。そこなわれている壁紙を入り口にして、ボトボトとビニール袋が大量におちてきた。部屋はゴミだらけ。ろう下に出ようとした時にふり返って、さっき首を吊ってた男の代わりにダンボールが吊るされてるのをみる。
ぶぶぶぶ
ぶぶぶぶぶぶと細かい音がどこからかする。
キッチンに行った。さっきまで内臓ぽいものでくさそうに汚れていたシンクはきれいになってた。大きなL字型のカウンターの向こうはリビングになってる。そこにアレかあと思うものがあった。サミが言ってたアレがきっとアレ。
カウンターごしにみえたのは、ゴテゴテした塊だった。大量のボールペンやカラーペンが針金でまとめられてる。「私」がギリギリ抱えこめるくらいの大きさだ。針金は手で適当にひねったようなぐにゃぐにゃなところと、機械でキレイに整えたみたいに、ほどけそうにないところが両方あって、変だった。ギチギチにまとめあげられたペンとペンの間、ほとんどない隙間に小鳥が一羽、頭をつっこんでる。ぶぶぶぶぶぶぶぶと羽をいっぱい動かして、潰れた頭の部分から液をとびちらせてる。カウンターをまわりこむと、物体の全部がみえた。ペンの束の上には、中途半端に中身の残った、油のボトルが乗ってる。日本語で「キャノーラ」と書かれてるからすぐわかった。その横には傘がつきたてられていて、上になっている持ち手のところに、キューブ型の、まっ白なオブジェクトがめり込んでる。ペンの束の下には、積み重なった洋服みたいにまだらな色の球体があって、それが二かける二の合計四つで並んでペンの束を支えてた。できあいの素材をむりやり合わせてつくったみたいな物体だった。
ぶぶぶぶという痛い羽の音が続いてる。小鳥の反対側に、リボンがゆらゆらゆれてる。ようやくこの物体がなんなのかわかった。下手な人間のかたちだった。小鳥とリボンは手、投げやりにくっついた白いキューブは頭らしきもの。
小鳥を助けたいと思った。変な人型のオブジェに近づくと、画面上にボタンが表示される。
なく?
——アレ、そろそろみつかった?
サミからのメッセが目にはいって、カッと顔があつくなった。サミがなにを考えてるかちょっとわかる。「なく?」ってふざけた質問だ。よりによって、今日教室で泣いた私に向かって、「なく?」って。は、うざ、と思う。このオブジェに関係あるとこだけ日本語だし、サミがどうにかして、授業中にでもゲームを改造してつくったんじゃないか。あいつだったらそのくらいできそう。私の恥ずかしいところをつついて、ニタニタしながら反応をみてるってことか。
私はその時突然大人になった気がした。
──ごめん時間なくてやめちゃった
と返信し、パソコンをシャットダウンする。サミのからかいにつきあう必要はない。今日は恥ずかしかったし今も恥ずかしいけど、誰かに笑われるべきだとは思わない。
大人になるってすごいことで、それからサミと嫌な関係になったわけではなかった。でも親友とは一度も呼ばなかった。時々送られてきたURLには「ごめん忙しかった!」と返す。やりとりの回数は徐々に減り、記憶の中のサミは遠くで手を振っている、親しかった友人のうちの一人になった。私とサミは元気に社会人生活を送っている、ということをお互い、SNSを通してうっすらと知っている。
*
怪しい個人サイトやインディーゲームが冒険の場であったのは、サミと特別親しかった頃だけだった。動物や工作が好きである一方で、ゲーム世界が自分にぴったりだとも感じ、自然にブラインドタッチをし、グロテスクなイメージを楽しみ、偏った言葉ばかりを覚えていた頃。とても短い期間だったけれど、今でも奇妙な時代として思い出すことがある。毎日更新され続けるネットニュースを流し読みする中で、「電脳空間に現れた心霊スポット」なんて古めかしいような表現を見た時も、サミのメッセージアイコンが頭に浮かんだ。
その記事では、「Order of Silence」というゲームが紹介されていた。三ヶ月前にプレイ動画が投稿され、話題になったのだそうだ。洋風の住宅を舞台にした一人称視点のゲームで、クオリティが高いとは言えない。ありとあらゆる幽霊が次々に飛び出し、恐怖より疑問や呆れが先にくるタイプのゲームだったのだ。しかし、悪趣味なオマージュが耳目を集める。「Order of Silence」は、同じ住宅素材を使用して制作された数々のホラーゲームのシステム、ストーリーを流用していたのだという。
「オマージュ」の確認のために視聴者はプレイ動画を繰り返し見た。再生数が徐々に伸びていく中で、出来の悪い噂が流れはじめる。「再生する度に、登場する幽霊や悪魔が増えた」。噂の真偽を調査した有志は「真っ赤な嘘」と結論づけたが、SNS上では比較検証と称した切り抜き動画が拡散され、それを真実であると訴える派閥と、フェイクであると訴える派閥、そしてフェイクと言うのは野暮という派閥が規模のつかめぬ勢力としてそれぞれ登場した。かれらの言い争いは茶番と言ってよかった。誰もが楽しんでいた。一見被害者のいないコンテンツはじわじわとふざけたように広まり、それが再生数に反映される。繰り返し、繰り返しプレイ動画は見られる。
ホラーゲームファンたちは(もちろん良識のあるファンは権利関係を気にしてはいたが)、「Order of Silence」をこぞってプレイしようとした。しかし、どうやってもゲーム自体は見つからない。もう公開されていないのか、そもそも動画投稿主が個人的に制作した映像作品だったのか。皆がやっきになる中、ゲーム制作者たちは、「Order of Silence」に酷似したゲーム、または同じ住宅を舞台にしたゲームを次々に公開しはじめた。十数年前につくられた素材である家がいわくつきの場所として扱われ、コンテンツは熱を帯びる。しかし、プレイ動画が非公開になると、急速に話題に上らなくなった。一過性のブームではあったが、伝説のオカルティック・ゲームとして「Order of Silence」は歴史に名を刻んだことだろう、と記事はまとめていた。
タイトルは思い出せなかった。というか、当時は読んですらいなかった。記事や考察ブログを漁り、プレイ動画の切り抜き転載に目を通す。サミが送ってきたあのゲームだ、と確信する。
自宅のパソコンの前に座り、あたりを見回した。今は一人暮らしで、夜。それでも、実家にいる時の誰もいない午後のリビングの静けさが部屋中を塗り替える気配がした。おそるおそる、昔のメッセージアプリをインストールして、ログインを試す。幼い頃の記憶の定着とは恐ろしく、一度もはじかれない。
sami、と登録されている名前をクリックし、かつてのやりとりを辿る。だんだんと私がサミに連絡を取らなくなった経過があり、遡ると楽しそうな私たちがいる。
泣き喚いたあの日を、こうした形で日付まで思い出すことになるとは。ようやくURLを探り出した。一呼吸置いてクリックする。リンクは切れているだろうという思いの奥底には、絶対に通じているという確信があった。
「Order of Silence」
とタイトルが出る。ゲーム画面を、十分リアルに感じた。最新ゲームのグラフィック事情なんて私は知らなかったから。
ネットを騒がせたあのゲームを私はプレイするのだという微かな優越感に体表が粟立つ。キーボードを叩く動作に、「私」がゆるゆるとついてくるのがもどかしい。はやくアレの所まで辿り着きたかった。今なら最後までプレイできる。
母子は惨殺され、父親は幽霊に取り憑かれ、娘はゾンビ化し、攫われてきた子供は実験体にされ、殺人鬼は一家の心臓を抜き取りそれで人形を製作し、魂を宿した女のマネキンが侵入者を襲い、部屋で監禁され育てられた娘は化物を妊娠し、生まれた赤ん坊が猫を食い散らかし、そんな歴史が刻まれた家に越してきた夫婦は異食にめざめ、病死した女を助けようとして男が身を捧げて悪魔を召喚すると、女は蜘蛛と合体した姿で蘇り、半身を腐らせながら訪れる者を待っている。
「私」はというと、家に調査に来た探偵で、刑事で、古い友人で、殺人鬼で、探索に来たストリーマーで、アルコール依存症の親であった。
接木されたストーリーラインを並べ立てるとどの意味も遠のいていき、哀れな者たちの傷ついた体のイメージは目に映るばかりで、きっと誰にも記憶されない。最後の首吊り死体に辿り着くまでにどれだけの壊れた体を繰り返し見たのか。時間としては三時間がかかった。
家が静まり返り、グラフィックの質感が粘性の高いものに変わっていく。遠くから羽音が聞こえる。壁から湧くゴミを踏んで、覚えているままの姿で待っている人型オブジェに近づく。
暗いリビングの中で、キッチンの照明が逆光になり、オブジェを浮かび上がらせていた。ぶぶぶぶぶと羽ばたく小鳥がかわいそうで懐かしい。
ボタンが表示された。
なく?
選択肢は他にない。躊躇せず私はなく。
カチッ
うええええええ
これまで鳴っていたサウンドエフェクトよりずっと大きく安っぽい声が響いて、直接触られたような心臓がびくつく。私は急いでスピーカーのボリュームを下げた。
うえええっえええっ
「私」は人型オブジェの前から移動できない状態にあった。視点だけは上下左右に動かせる。傘の持ち手にめり込んだキューブのオブジェクトを見上げると、わずかに泣き声の音量が上がる。音の発信源はそこに設定されているようで、やはりキューブを頭に見立てているのだなと、私は妙に冷静に考えた。
うえっえええっええっそうううううう
嗚咽に混ざって、言葉が聞こえた。「そうううきまっしたかっ」今度はもっとはっきりと。「そうきましたかっ」子供特有のしゃくり上げる泣き声。嫌悪感を覚える声質なのは何故なのか。よく知っているはずなのに、何度聞いても紛い物にしか思えない音。
これは小さな私の声だ。間違いがなかった。あの日の泣き声が録音されていたのか、合成音声か、頭を急速回転させて手に取れるリアリティを探ったが、なによりも先にフラグが立つ。
着信があった。パソコン画面の右上に、青色のバナー、アニメキャラクターのアイコンの横に、samiの名前。何年も連絡を取っていない佐藤美津である。「拒否」のボタンをクリックしようとして手を止めた。昔、サミと距離を置くために送った何件かの気のないメッセージと、送信ボタンを押した自分の手を思い出す。今「拒否」を押すのは過去の行為の繰り返しである。直感的に、同じ道は避けるべきだと思った。時間制限でもあるかのような焦燥感で体が勝手に震え出し、思わずパソコン画面上の時計を確認するが、samiからの着信バナーで隠れて見えない。絶え間ない呼び出し音のせいで、時間が足りない足りないと、追われるようにして「応答」を押す。
「大丈夫?」
大丈夫?
スピーカーから微かに聞こえたサミの声は幼く、反射的に、私の成長し過ぎた声で応えることができなかった。
「ねえ、どうしたらなきやむの?」
ねえ、どうしたらなきやむの?
サミの声に合わせて、ゲームの画面下部に、字幕が打たれた。サミの言う言葉と同じ文字が表示されている。先ほどまで「私」だったプレイヤーの発言として、泣き続けている私のオブジェに向かって放たれる言葉として。
今日からずっとないてるよね。おすすめのゲームはおもしろくなかった? これすごいよ。これまでとこれからのストーリー全部のせ。一回プレイする度に幽霊何匹出てくるんだろ。幽霊の数え方って粒子? だったらヤバいね……。ゲームやってると時間忘れちゃう。何回繰り返しやっても、スタートボタンを押せばはじめてみたいに新しく死体や思い出が出てくるから楽しい。……まだないてる。どうしたらなきやむかな。あなたにとらえられた小鳥の羽音がもう聞こえないのわかってるよね。しんだよ。死者は<talisman>を使用することで一定時間避けることができるよ。持ち物は「Tab」キーで確認してね。さ、どうしたらなきやむ?
サミの言葉は放課後の延長みたいで、声は私を昔に引き戻しかける。しかし思い出の中には存在しない言葉だ。知らない時間がスタートしていた。通話は切れ、字幕は消える。次の選択肢を考える。
キッチンカウンターの上に新たなアイテムが出現していた。確認するとそれは弾丸であった。何故、オブジェを人の形のようだと思ったのだろうと、私はぼんやり考えた。
告知
鈴木林「なく?」は マガジン『Kaguya Planet 特集:食』に掲載されています。詳細はこちら。
先行公開日:2024年8月17日 一般公開日:2024年10月14日
カバーデザイン:浅野春美
怪談好きの小説家。映画美学校の言語表現コース〈ことばの学校〉の一期生。2022年に第四回ブンケイファイトクラブで本戦に出場。2023年には「ベントラ、ボール、ベントラ」で第三回かぐやSFコンテストで最終候補に選出され、選考委員の岸谷薄荷さんから「オカルトや奇妙な物語への愛が端々からわかる書きぶり」を高く評価された。同年、にいがた経済新聞の主催している第一回NIIKEI文学賞で、「エゴネリ」が純文学部門佳作を受賞。「エゴネリ」は『NIIKEI文学賞2023』に収録されている。
また、ことばの学校の一期生有志による合同誌『tele-』に短編小説を寄稿している。2024年には、出版レーベルffeen pubが刊行しているweb上の小説アンソロジー『FFEEN vol.4』に「曰く」を寄稿。「曰く」はffeen pubの初めての書籍『小説紊乱』に転載された。