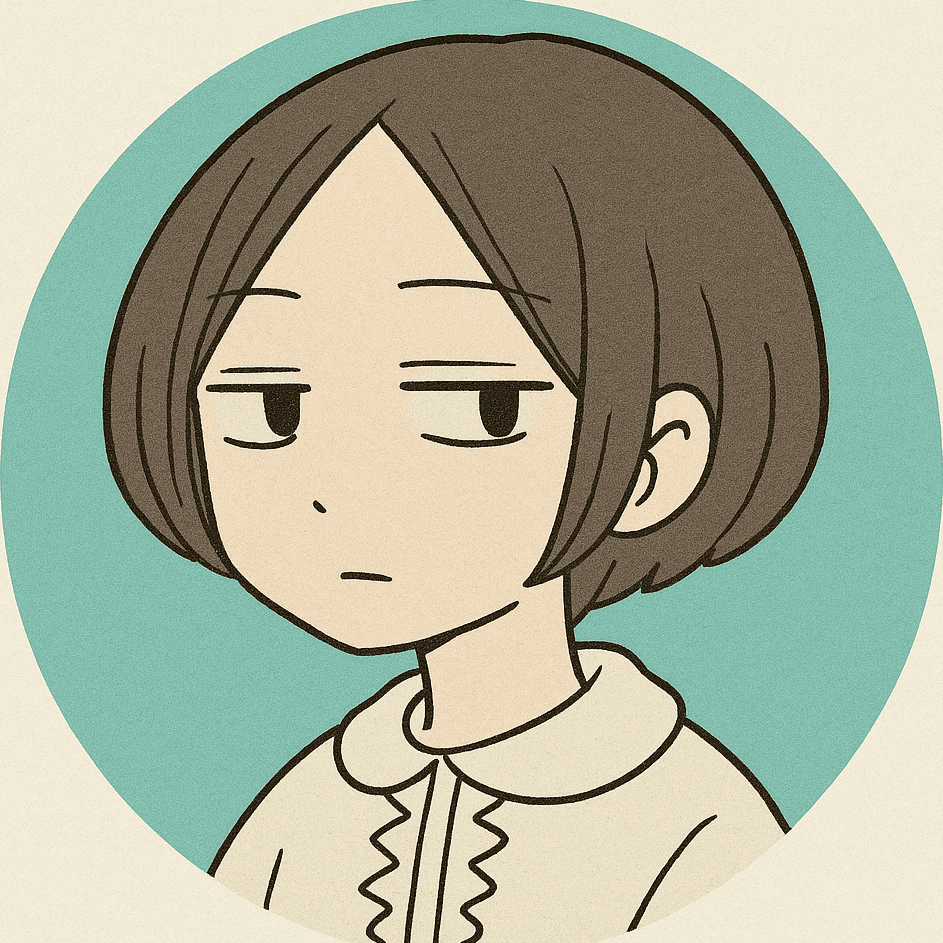ウサギ列車
7,481字
一.乗車
兎にも角にも僕は要領が悪いらしい。同僚たちが次々と仕事をこなしていくのに、いつだって一人取り残されてしまう。会社の机の上には書類が山積みになり、来る日も来る日も残業ばかり。今日だって気がつけば終電目前の時間だった。夕食と言えばコンビニのおにぎりを一つ口に放り込んだだけ。ペコペコの腹を抱えながら、僕は地下鉄の駅へ急いだ。
発車時刻一分前に改札を抜け、ホームに駆け降りた。ああ、間に合ったと一息ついて周囲を見ると、僕以外に列車を待つ客はいない。それどころか駅員の姿もない。何だか変だとも思ったが、そんなことはどうでもよかった。クタクタだった僕は、早く乗車してシートに座り込みたかった。
やがてファーンという警笛とともに、いつもの地下鉄車両がホームに入ってきた。運転手の姿が一瞬僕の目に入る。……あれ? なんかおかしくなかったか? 制服は着ていたけど、顔がやたらと白くて、帽子の上にも白いものが二つ、にょっと突き出ていたように見えたんだが……。まもなく車両が停止し、目の前で三両目のドアが開いた。僕は乗り込んだ途端に言葉を失ってしまった。何だこれは。一体どうなってるんだ!
いつもの地下鉄なら横長のロングシートのはず。でもこの車内には背もたれの硬いボックスシートが並んでいた。天井では扇風機が回っている。何だかローカル線の古い客車みたいだ。茫然とする僕の後ろでドアは閉まり、列車は静かに動き出した。地下を走っているはずなのに、窓の外にはなぜか街の夜景が広がっている。
仕事のし過ぎで疲れてるんだ。きっと夢でも見てるんだ。とにかく休もう。そう思って僕は近くの席に身を投げ出すようにして座り、目を閉じた。そこへ、誰かが声をかけてきたのだった。
「お隣、よろしいですかあ?」
その相手を見て、僕はもう卒倒しそうになった。全身真白、長い耳に赤い目。鼻をピクピク動かすそれは、誰が見たってウサギだった。おまけに大きい。人間の子供と同じぐらいだろうか。しかも二本足で立っているし、言葉だって喋った。ひょっとして、さっき一瞬見えた運転手も……? 僕は思わず立ち上がって車内を見回した。たくさんの乗客がいる。白い身体、長い耳……なんてことだ。僕以外はみんなウサギじゃないか!
なかなか返事をしない僕に業を煮やしたか、声をかけてきたウサギはピョコッと会釈して隣の席に座った。僕はへなへなと座り込み、ウサギは持っていた新聞を広げて読み始める。
「あの…」
ちょっと興味が湧いてきて、僕は恐る恐る聞いてみた。
「何が書いてあるか、わかるのかい?」
ウサギはチラッと横目で僕を見て、ふふっと笑った。
「わかりますよお。私は世の中のこと何でも知ってますからね。どこかの大臣のとんでもない発言だって、チキュウオンダンカとかいう困った現象のことだって」
「はあ……」
「しかし人間さんも大変ですね。賢くなりすぎて、自分で自分を縛りあげてる感じだね。おっとこれは言い過ぎだ、失礼」
急に車体がガタガタ揺れて、身体がグッと座席に押し付けられた。驚いて窓の外に目を向けると、街の明かりがどんどん眼下に小さくなっていく。ウサギが新聞を畳みながら言った。
「お、飛行が始まりましたね」
「ひ……飛行?!」
地下鉄が空を飛ぶなんて、一体何が起こっているんだ。僕は慌ててウサギに聞いた。
「この列車、どこへ行くんだ?!」
「おや。そんなのあなたの気持ち次第に決まってるじゃないですか」
「僕の気持ち?」
列車は夜空を走り続ける。やがて暗かったはずの窓の外が、パアッと明るくなってきた。ウサギが眩しそうに赤い目を細めた。
「いやあ、夏が来ましたね」
二.夏
気がつけば、列車は青い海が広がる海岸線をガタゴトと走っていた。窓を開けると、潮の香りが車内にさあっと広がっていった。少し前の座席にいた子ウサギが歓声をあげ、母ウサギを呼んでいる。
「お母さん、お母さん。海だよ!」
「まあ、大きいねえ、きれいな青だねえ」
まるで人間の親子みたいな会話だ。潮風に吹かれながら、なぜか僕は幼い頃を思い出していた。都会育ちの僕が海を見るのは、夏休みに祖父母の家に遊びに行く時ぐらいだったろうか。少なくともあの子ウサギのように歓声を上げることはなかった。泳ぐことは大の苦手だったから、海を見て心が躍るなんてことがなかったのかもしれない。学校の水泳授業ではいつも先生の手を煩わせる落第生だったし、そのことで同級生からよく馬鹿にされた。自分は何をやっても駄目なんだ……そう思い込み、何事にもすっかり臆病になったのは、あの頃からだったように思う。
僕の表情が翳ったのに気づいたのだろう。隣のウサギが少し声を落して聞いてきた。
「夏はお嫌いでしたか?」
「いや、あまりいい思い出がないもんで……」
天井の扇風機がブンブン全力で回っている。それでも車内の気温はどんどん上がり、僕は上着を脱いで網棚に乗せた。ウサギも暑そうだ。
「私も夏は苦手ですねえ。なんせホラ、この毛皮ですから」
すべてがキラキラと輝いているような季節。そんな夏という時期を心底楽しんだ記憶がないなんて、本当につまらないと思う。せめて心に残る思い出の一つや二つ、なかったか。そう思い目を閉じてみると、心にある光景が蘇ってくる。遊びに夢中になって、すっかり帰りが遅くなってしまった夕方。気の長い夏の太陽がようやく沈み始め、夕闇に追いかけられるように僕は家路を急いだ。我が家の玄関ドアを開けたとたん、鼻をくすぐるおいしそうな匂い。もっと早く帰りなさいという母の小言を聞き流して、汗をかきながら食べたカレー。ゴロゴロと大きく切られたジャガイモの食感を思い出す。
突然、僕の腹がグウッと鳴った。そうだ、腹ペコだったのだ。見透かされたように、隣からほんのり温かい包みが差し出された。
「ウサギが作ったおにぎりなんて、お口に合いませんかねえ?」
開けたとたん、ふわりと海苔の香りが広がった。ウサギにお礼を言うと、僕はそのおにぎりにかぶりついた。心に沁みるようなおいしさだった。人間がウサギにごちそうしてもらうなんて、きっと前代未聞だろうな。
列車はいつの間にか海岸線を離れ、海はもうずっと彼方で輝きを見せているだけだった。
三.秋
車内に流れ込んでくる風が何だか涼しくなってきたから、あわてて窓を閉めた。列車は急勾配の坂を上っていく。
隣のウサギにもらったおにぎり二つを平らげて、すっかり落ち着いたせいだろうか。僕は改めて今置かれている状況を考えてみた。終電の地下鉄がなぜか古い客車に姿を変え、夜空を飛び、海辺を走り、今度はどうやら山へと向かっているらしい。運転手をはじめ、僕以外の乗客はみな白いウサギ。しかも人間の言葉を喋る。どう考えたって現実とは思えない。けれどもさっきの潮風の香りやおにぎりの温もり、そして途切れることのないリズミカルな列車の揺れは何ともリアルで、夢だとも思えないのだ。どちらにしても、今はこうしてこの妙な空間に身を置いているしかないのかもしれない。
僕はふと隣のウサギに聞いてみた
「君は何でこの列車に乗ってるの?」
「何でって、そりゃあなたを見届けるためですよ」
「見届けるって……僕が一体何をするっていうんだ?」
「それは私にもわかりませんねえ。それより、ほら。もうすっかり秋ですよ」
列車は山間を走っている。ウサギの言ったとおり、車窓に流れる山の木々は見事に紅葉していた。
「紅葉のしくみって、ご存知ですか?」
ウサギが僕の顔を覗き込んでくる。
「いや、知らないなあ……」
「秋になると葉の付け根に仕切りができて、枝との間での水や養分の流れが妨げられる。その結果、葉を緑に見せてた葉緑素がだんだん弱ったり分解されたりして、赤や黄の色素が生まれたり目立ったりしてくるんですよ。まあ、散り際の晴れ舞台ってところですかね」
ウサギは得意そうに鼻をピクピクさせる。僕は再び車窓に広がる秋の景色を眺めた。残された力を振り絞って色づいていく木の葉たち。燃え上がるように紅葉し、やがて静かに散っていくのだ。なんて潔い最期なんだろう。
「僕にはできないな」
「は? 何がですか?」
「あの葉っぱたちみたいな生き方さ」
ウサギが耳をピンと立てて、不思議そうに僕の呟きを聞いている。
「潔い、なんて僕には縁遠い言葉だ。いつでもあと一歩が踏み出せないでいる。肝心なところで勇気が出なくて、つまんない道ばかり選んでる気がするな」
「人間として立派に生きてらっしゃるのに、つまらないんですか?」
「立派だなんて……僕なんて大したことないのさ。昔から何をやっても不器用で要領が悪くてね。臆病者だし、自分に自信が持てないし。時々考えるよ、自分の存在価値ってものを」
「ソンザイカチ……ですか?」
物知りウサギもさすがにそれは知らなかったらしい。
「自分が何のためにこの世に生まれて、何のために生きているのかってことだよ」
「はあ……人間さんはやっぱり賢くなりすぎたんですねえ。そんなことを考えながら生きなきゃならんなんてねえ」
列車は相変わらず色づく山間をガタゴトと走っている。鉄橋に差し掛かった。眼下を流れる川面に、秋の高い空が映っている。ぼうっと見惚れていたら、突然ピーッと汽笛がなって景色が寸断された。トンネルに入ったのだ。窓ガラスに僕の顔が映し出される。随分疲れた顔をしていた。
四.冬
思いのほか長いトンネルだった。ふと窓ガラスに触れると、随分と冷え切っていた。
「何だか寒いな」
「ええ、もう冬ですからねえ」
ウサギが答えると同時に、列車はトンネルを抜けた。途端に外は一面の銀世界だ。この世界はどうしてこうも季節がクルクル変わるのだろう。暖房が入ったらしく、足下がポカポカと暖まってきた。
「そう言えば、君たちは冬眠するんじゃなかったっけ?」
「私は飼いウサギですからしませんよ。野生の仲間たちは今頃ぐっすりでしょうけどねえ」
「君は誰かに飼われてるの?」
「誰かにって……もう忘れちゃったんですか?」
ウサギが顔を覗き込んできた。僕は何が何だかわからない。忘れるって、何を? すぐに答えられない僕が不満だったのか、ウサギはブツブツ言いながら再び新聞を広げて読み始めた。僕は気まずくなって、とりあえず窓の外に目を向けた。
雪が降り続いている。突然前方のドアが開いて、制服制帽姿の車掌ウサギが一礼して車内に入ってきた。僕と目が合うと、帽子を取って深々と一礼した。思わず僕も頭を下げる。隣のウサギがふふっと笑った。
「私だけじゃない。彼も覚えてるんですよ。この列車に乗っている者は全てあなたを知ってます」
「どういうこと?」
ウサギは新聞を膝の上で折り畳んだ。
「あなたは私たちを救ってくれたんですよ。今から十五年も前の冬の日に、あの場所で」
ウサギに促されるようにして、僕は窓の外を見た。ちらちら舞う雪の向こう、左前方から何か大きな建物がゆっくりと近づいてくるのが見えた。どこかで見た覚えがある。やがて列車は大きな門柱の間を抜け、建物の敷地内に入っていった。
「ここは……僕の行ってた小学校じゃないのか?」
広いグラウンドを突っ切った列車は校舎をぐるっと回りこんで、裏手にある小さな小屋の前で静かに停車した。車内のウサギたちが一斉に窓辺に集まり、無言のまま外を見つめている。
小屋の前に一人の男の子がうずくまっているのが見えた。ちょっと細身でメガネをかけている。スポーツブランドのロゴが入った青いジャンパーに見覚えがあった。ああ……あれは僕。小学三年生の僕だ。忘れていた記憶が一気に蘇ってきた。
この小学校の飼育小屋では、二十羽ほどのウサギが飼われていた。僕はそのウサギたちを眺めるのが好きで、ちょくちょく小屋に通っていた。世話をするのは高学年の子供達で、当番制で餌やりや掃除をしていたように思う。しかしどうも真面目にやらないらしく、いつも汚れがち。狭い小屋の中で、たくさんのウサギたちも何だか住みにくそうにしていた。
寒さが厳しくなり、小雪もちらついたその日。隙間だらけの小屋で身を寄せ合って震えていたウサギたちを見つめながら、僕は決意した。こんなところにいちゃだめだ。ここから逃げるんだ。そうしてどこか暖かい場所で、安心して暮らせばいい。僕は思い切って小屋の扉を大きく開いた。ウサギたちは戸惑ったような様子を見せながらも次々と小屋の外に飛び出し、そこらじゅうをピョンピョンと跳ねまわる。それを見ていた誰かが職員室に駆け込み、数人の先生が慌てて飼育小屋までやってきた。僕はこっぴどく怒られ、小屋に戻されたウサギたちの目の前で扉はガチャンと閉ざされた。
「結局僕は君たちの仲間を助けてあげることができなかったんだ」
「そんなことはないですよ。あの後どうなったか、覚えていませんか?」
ウサギ脱走事件の翌日、僕は担任の先生に呼び出された。なぜあんなことをしたのか、という質問に僕は答えた。
「ウサギたちがかわいそうだったんです。あんな窮屈で、寒い小屋だし。掃除だってちゃんとできてないと思う。もっと暖かい場所に逃げれば、幸せになると思ったから」
先生がウンウンと頷きながら聞いてくれたことを覚えている。それから何日かして飼育小屋の壁が補修され、半数のウサギがどこかに貰われていった。
「あれでだいぶ寒さもましになったんですよ。小屋の中も清潔になって、ゆったり健康に暮らせるようになった。いやあ、ありがたかったです」
隣のウサギがさも体験したかのように言う。
「あなたの行動は確かに突飛だったけれど、そのおかげで教師たちが重い腰をあげたんですよ」
「君は……あの時のウサギなのかい?」
ガタンッ。突然列車が動き出し、僕たちの会話が中断された。どんどんスピードが上がっていく。雪が激しく降り始め、やがて猛吹雪になった。叩きつける雪で窓の外は何も見えない。列車はガタガタと車体を震わせながら走り続けている。隣のウサギが声をかけてきた。
「そろそろですよ」
「え?」
「まもなく到着です。準備をしましょう」
唐突に車内が薄いピンクに染まった気がした。窓の外はいまだに吹雪……いや、違う。雪ではない。桜だ。無数の桜の花びらが、吹雪となって列車を包み込んでいた。
五.春
列車が静かに停車した。
「行きましょう」
ウサギに急かされて僕は席を立った。出口へと進む僕たちの後ろに、他の乗客ウサギたちがぞろぞろと続く。車外に出たとたん、僕は軽いめまいを覚えた。
桜が舞っている。ぶわあっ……と視界を遮るほどの桜吹雪だ。辺りが薄いピンクに染まっていく。
「さあ、どうぞ。ここからはあなたが先頭です」
新聞を小脇に抱えてウサギが言った。僕は言われるままに歩き始めた。不思議と不安はない。この先にきっと何かがある。僕にとって大切な何かが待っている気がしたからだ。
向こうに人影が見える。ゆっくり近づいていくと、それは小さな赤ん坊を連れた若い夫婦だった。どこかで見た気がする。古いアルバムに収められた写真に、その人たちが写っていたはずだ。
「……父さん、母さん」
そう、確かに若かりし頃の僕の両親だ。胸に抱いた赤ん坊がぐずり出し、母が優しくあやしている。あれは僕なのか。
「泣かなくていいのよ。怖いことなんて何もないの。何があっても大丈夫。だってこんなきれいな季節に生まれてきたんだもの。桜の咲く春に私たちのところにやってきた、あなたは大切な命なんだもの」
立ち止まってその親子を見つめながら、僕は思い出していた。母がいつか話してくれたことを。
「難産だったから、それこそ命がけで産んだんだよ。病院のそばにきれいな桜並木があってね、退院の日にあなたを抱っこして父さんとゆっくりと歩いたの。桜に祝福されているようで、本当に幸せだった。私、生きていてよかった。産まれてきてくれてありがとう。心からそう思ったんだよ」
その時は照れくさくて聞き流していたけれど、今になるとその言葉をささやかな感動と共に思い出す。僕は祝福されて生まれたのだと。
ウサギたちが立ち止まる僕の傍に集まってきた。
「さっきの質問にお答えしていませんでしたね」
僕の隣に座っていたウサギが言う。
「おっしゃる通り、私はあの学校の飼育小屋にいたウサギです。実際にあの頃小屋の環境はかなり悪くて、体調を崩す仲間もたくさんいました。私もそうだったんです」
親子連れがゆっくりと桜並木の向こうへと消えていった。そっと見送りながら、僕はウサギの話に耳を傾ける。
「私たちが脱走した事件をきっかけに、教師たちが小屋の修理をしましたよね? 飼い方も見直されました。おかげで住みやすくなり、元気を取り戻したんです。その後何年かで私はこの世に別れを告げ、その命は子供達に受け継がれました。その子供達の命が尽きたら、今度は次の世代にバトンタッチしていった。そうやってずっと命のリレーが続いているのです。ここにいるウサギは皆、あの時生き延びた私や仲間の子孫たちです」
海を眺めて喜んでいた親子ウサギ。制服姿の運転士ウサギ、車掌ウサギ。たくさんのウサギたちが僕をじっと見つめている。
「あの時あなたが小屋の扉を開けてくれなかったら、私たちは皆この世に存在しなかったかもしれない。あなたの小さな勇気が、私たちに命をくれたんですよ。わかりますか?」
ウサギは静かに、確かめるように言った。
「これが、あなたの、ソンザイカチです」
存在価値。僕がこの世に生まれ、生きていく理由。僕の命を心から大切に思ってくれる人たちがいる。僕が救った小さな命が、今も生き続けている。何かが心からぐっと湧き上がり、僕の目から涙が溢れ出た。
隣のウサギが静かに言った。
「あなたを見届けることができたようですね」
風が吹いて、桜吹雪が激しくなる。辺りに発車のベルが鳴り響き、車掌ウサギがよく通る声で言った。
「列車はまもなく発車いたします。この先の旅のご無事をお祈り申し上げます」
六.出発
気がつけば、僕は自宅の最寄り駅のホームでベンチに座っていた。見慣れたいつもの駅だった。
僕をここまで運んだのは本当にあのウサギ列車だったのか。既に車両は視野から遠く走り去り、それを確かめる術もない。
「行くか」
僕は立ち上がった。時は流れている。だから僕も進んでいかなければならない。要領が悪いから失敗ばかりだ。思い切ったこともできない。それでも、僕は僕なのだ。自分の日々を生きる中で、きっとこんな僕にもできることがある。赤ん坊だった僕が、小学生だった僕が、誰かを幸せにし、誰かを救ったように。
僕は歩き出す。遥か彼方から、列車の汽笛が聞こえたような気がした。
吉野雪音「ウサギ列車」解説|秋永真琴
吉野雪音「ウサギ列車」は、会社の仕事に追われて身も心も疲れている青年が、地下鉄の駅に急ぐ場面から始まる。その日の最終電車はなんと、運転手も乗客も二本足で立つ人間大のウサギたち。マジカルな現象はこれだけで終わらない。戸惑う青年を運んで、列車は夜空へ飛び出し、やがて四季の風景の中を駆けていく。それは青年が、自分の人生のさまざまな季節を振り返る旅でもあって……。
この短篇の舞台は特定されていないが、道北の文芸サークルの会誌で発表された作品と聞いて、やはり私は北海道を連想した。道内で地下鉄が走っている街は札幌のみ。主人公は地方から進学、あるいは就職のタイミングで引っ越してきたのか。冬の場面には小雪がちらついている。ロマンティックなできごとではなく、厳しい寒さに身を縮める日々のいち風景としてさらりと書かれているのがいい。
もちろん、他の街を舞台として読んでもかまわないだろう。おそらく作者は、誰が読んでも「自分の物語」として感情移入しやすいように、主人公の青年にも名前をつけていない。
青年が自嘲してウサギの乗客に語る「僕なんて大したことないのさ。昔から何をやっても不器用で要領が悪くてね。臆病者だし、自分に自信が持てないし。時々考えるよ、自分の存在価値ってものを」という気持ちは、多かれ少なかれ、皆さんも味わった覚えがあるんじゃないだろうか。ないですか。それならよかった。私はあります。「そこまで悪いことばかりじゃなかったけど、これから大していいことがあるとも思えず、仮に人生の価値を数値化するならよくてプラマイゼロか、最終的にはマイナスなんじゃないか」みたいな、ゆるやかな虚無感。
この小説は、そんな虚無にそっと異を唱える。
自分の過去の行いが誰かを救っていたこと。自分がこの世界にいることを誰かが喜んでくれたこと。それらを思い出すことで、青年は、これからの自分にもきっと存在価値はあると信じられるだけの力を取り戻す。
「ウサギ列車」は前述の通り、作者が道北にお住まいのときに書かれた作品である。ご縁があってこの作品に巡り合ったKaguya編集部が吉野さんにお願いし、Kaguya Planetへの掲載を快諾いただいたと聞いている。
地方の文芸同人誌は、現在も全国の各地に存在している。地元の取り扱い書店や図書館に行けば、その県や市の名前を冠した雑誌がいくつも置かれているだろう。プロ作家を志望する向きからは「『中央』でのデビューにはつながらない」と軽んずられることがあるのは否めなかった。しかし現在、そのような見方はいよいよ改められてよいのではないか。
だって、小説投稿サイトや文学フリマなど、個人発表の場がこんなに盛んな時代がおとずれたのだから。それは商業出版の斜陽と背中合わせであって手放しでは喜べないが、必ずしもプロを目指さない純粋な趣味や自己表現としての活動がしやすい(同時に、プロへの門戸が多様化している)のは、風通しがいい状況だと思う。
そして、ウェブ小説や文フリもまったく新しいムーブメントではなく、地方の文芸誌が原点のひとつであると言える。
文学は、東京や大手出版社だけで生まれるものではない。どの土地にも、そこにしかない風景や言葉があり、それを書こうとする人がいる。この温かなファンタジーが地方の同人誌から生まれ、読む人の心を打ち、いま、皆さまの手元のスマホやタブレットに届いていることが、私は嬉しい。
告知
「ウサギ列車」は『北海道SFアンソロジー:無数の足跡を追いかけて』(Kaguya Books)との連動企画として掲載しています。『北海道SFアンソロジー:無数の足跡を追いかけて』は、「ウサギ列車」の解説を書いている秋永真琴さんと堀川夢さんが編者を手がけ、「広い北海道の土地を、物語と一緒にたどりたい」をコンセプトに、10組の作家が共演する珠玉のアンソロジー。こちらもでぜひチェックしてみてください。
先行公開日:2025年10月31日 一般公開日:2026年1月17日
カバーデザイン:VGプラスデザイン部