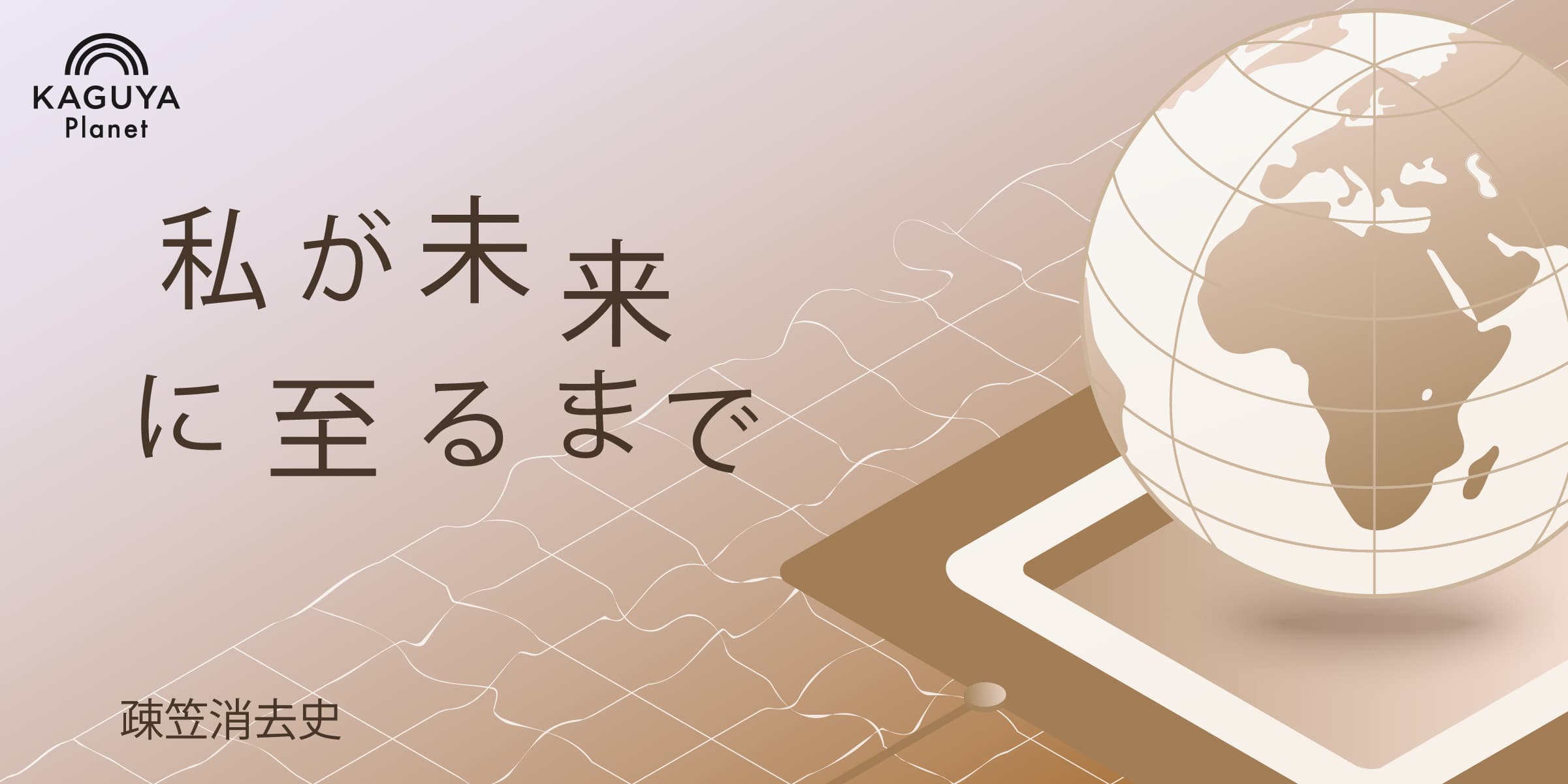
私が未来に至るまで
8,958字
百年たったら、科学は進んで、きっとこうなるぞ。科学小説をお書きになる先生は、こんなすばらしい東京のすがたを考えました。(『たのしい四年生』昭和36年1月号)
*
作業所の和室の戸を開けたら、巨大なエリンギが茶をすすっていた。ぱっと見で身長は170センチほど。黄色いドッジボールをはめこんだような瞳も、排水溝カバーのような口も、低予算の自主制作映画みたいににチープだった。エリンギはパンタロンの裾みたいな末広がりの手を上げて、
「よう」と気さくに声をかけてくる。
驚こうか、と思ったが、差し向かいに入本さんが座っているからには、きっと何か訳があった。物事に動じなくなっているのは年の功なのか、感受性が鈍麻しているのか、自分でも判断がつかない。私はタンスに手をかけて、卓袱台の輪から少し離れた特等席に座った。膝に負担をかけないように、ゆっくり、ゆっくり。身体と感受性が衰えても、痛覚だけは鋭い。
「弘美さん、驚かないんですねえ。これシイさんですよ。シイさん、実は宇宙人だったんですって。華族の血筋とか熊に育てられたとか、ハクビシンと暮らしたことがあるとか、ぜんぶ嘘」
入本さんが饅頭を食べながら、目を細めてエリンギ人間を指さした。
「あなたも驚いてないじゃない」
「三十分前に目ん玉ひんむきましたよ。やんごとない血筋ってのは信じてたのにな」
かはは、と鷹揚に笑う入本さんは、この「江東区シルバー人材センター北砂作業所」の管理員だ。山のような巨体に太鼓腹、恵比寿さんそっくりの外見をしている。
「ハクビシンと暮らしたのは本当だぜ。地球に来て最初は動物に化けてたんだ。イルカから蝶々、つぎにハクビシン。気の良い奴らだったよ。それで最後に人間さ」
「ふうん」と私。
「……なんで驚かねえんだよ。見た目の問題か。しょうがねえだろう、こういう宇宙人なんだから」
見た目どうこうというより、話す感じが、シイさんだからだ。長谷川椎三、98歳。作業所の登録者では一番の古株、高齢化社会を象徴する働く老人にして、下町を象徴する天然記念物級のせっかち爺さん。気が短すぎて、せっかくの一大告白にタメもフリもない。
「シイさんはシイさんだもの。本当に宇宙人なのかは気になるけれど、宇宙人であっても驚かない。もう20年近い付き合いなのに、なんで今さら正体を現したのかは知りたいけれどね。……もうすぐ死ぬから?」
「……あんたにゃ勝てねえな。まったく口が悪い」
ぽりぽりと頭の後ろを掻くシイさんに、不思議と人間のときの表情を見る。決まりの悪さを人のせいにしつつ、少年のように笑うから憎めない。
シイさんは万歳の姿勢を取る。ラッパのような両手の表面に、幾筋も電光が走った。
「……確かに、老い先が短えからだよ。いっちょ俺の真の力を使って、世話になった皆に、一旗上げてもらいてえんだ。なにせシルバー人材センターの補助金が減るからな」
宇宙人らしさが全然ない発言に、私はようやく軽く笑った。
2040年現在、高齢者の労働人口は本当に多い。なるべく長く働かないと生きられない。だから一般企業のパート雇用に高齢者が流れ、スポットワークが基本のシルバー人材センターでは登録者が落ち込んだ。雇用の年限を外れた80代以上が登録者の大半だから、市場からも利用を尻込みされる。そのため、補助金の削減や、作業所の統廃合による広域化が進んでいる。
私は87歳で、足が悪い。でも、何歳でも、どんな状態でも、生きるためにはお金がかかる。作業所が遠くなれば通い辛くなる。月に2、3万であっても、国民年金以外の大切な収入が減るのは、死活問題だった。
つまり、お金がない。宇宙人のシイさんすらも、お金がない。
「どうやって儲けるの? サーカスにでも入る?」
「あのなあ、今日日サーカスはねえよ。アトムじゃねんだから」
「ある意味でアトムじゃないですか。シイさんの腹の中のもの、使うんですから」
アトム。その名前を聞いて痛む胸が、自分にあることに、少し驚く。原子力エンジンで動く科学の子。かつて未来の象徴だったあの技術。私たち夫婦から故郷を奪ったあの技術。
シイさんは居住まいを正して「そうだな」と呟いてから、私に言った。
「俺達で原発をやる」
*
ジャック星人は、肉体のなかにある、核融合炉に酷似した器官を原動力に、稼働している。それゆえに星は繁栄した。無尽蔵のエネルギーを身体から取り出せるのだ。多くの労働を代替するロボット、星全体をめぐる音速の弾丸列車、気候操作システム、増えた人口を納める無数の海底都市、そして他惑星への侵攻兵器。栄華を極め尽くしたジャック星では、いつしか主幹事業が侵略戦争に成り果てた。シイさん──ジャック星人のシイさんは、それを嫌って亡命した。銀河系の辺境である、この地球へ。
皮肉にも、その来し方は、わたしと一緒だった。
つまりは、エネルギーと技術に翻弄されて、故郷を捨てたということ。
あの震災と原発事故。発災から暫くは、しがみついた。けれど──根強い風評被害と、海水温上昇のせいで減る一方の漁獲量、船の購入もかなわないまま、高騰してゆく資材費──負けを認めたのが2013年のこと。漁師だった夫が廃業を決めると、東京都の江東区に移住した。区内の東雲住宅に夫の親類が身を寄せており、少しでも近くに住もうと思った。けれど東雲から交通の便が悪い北砂に居を構えたのは相場より安い物件を見つけたからで、思えばずっとお金に汲々としている。
でも、シイさんも私たちも、下町だったから良かったんだと思う。専業主婦だった私は数十年ぶりにパートに出て、砂町銀座の惣菜屋に勤めた。シイさんは最初は大田区の工場長屋に勤めて(C3棟に住み込んだためシイゾウを名乗ったのだそうだ)、それから近隣を転々としながら、やがて北砂で修理工として一本立ちした。地方から腕一つ身一つで上ってきた人々でごった煮の街。あるいは、見知らぬ人とでも気安く会話を交わせるような、商売という窓口。代々の居住者にはしがらみもあるのだろうけど、漂流者だった私やシイさんにとっては軽やかな街だった。理想的な部分を、私達は味わったんだと思う。
だから愛着と、郷愁がある。
どうしても頭を整理したくて外に出たけれど、ねっとりと重い梅雨の空気より、空調の送風のほうが快適に思える。世の中は、春という季節から縁遠くなった。寒い冬から一足飛びに、蒸し暑い初夏が始まる。生態系が変わっていくというのに、植物だけはふしぎと、不安定な気温の間隙を縫って、古今変わらない花実をつける。
作業所の軒先には鉢植えが並んでいて、いま飛び切りに目立っているのは獅子咲きの変化朝顔。とても長い名前があったが忘れてしまった。薄水色の花弁が水飛沫のようで、蒸し暑い気候のただなかでも心持ちを冷涼にしてくれる。ラキブルさんという利用者が園芸好きで、時期が来ると下谷の朝顔市で鉢植えを買ってきた。彼が亡くなってからは、偲ぶ気持ちを胸に、入本さんが朝顔を買ってくる。
ラキブルさんはいい人だった。私をシルバー人材センターに誘ってくれたのも彼だ。
私は、2025年に夫を亡くした。彼なりに街に根付いていたけれど、それでもストレスが死因だったと私は思っている。ずっと故郷に帰りたがっていた彼は、原発の再稼働が次々に決まって、核融合炉の実用化が急がれる報道を耳にするたび、怒りを露わにした。海水温が上がって魚が獲れない。地球温暖化を止めるためには、クリーンなエネルギーが必要になる。風力や太陽光での発電には、コストがかかりすぎる。これからのAI社会を支える、巨大な電力を生み出すクリーンエネルギーとは、何か。こうして、原発が再稼働する。ソナーを買い替えられずに涙を飲んだ私たちが、何を支えるって?
私は、考えるのを止めてしまった。よく分からなくなっていた。夫は私との温度差を感じたまま亡くなっただろうと思っている。だというのに、夫が亡くなってからは尚の事、私は目先の生活のことしか考えられなくなった。
独りでの暮らしのためにパートを増やした。早朝のビル清掃の仕事だった。
生涯現役の社会なんて言うけれど、年金を貰うような年齢で遮二無二働くのは間違っていると、私は今でも思っている。疲労で朦朧としていた私は、大型掃除機のケーブルに、蹴躓いた。
尾骶骨の骨折──後遺症が重く、今でも神経痛がひどい。労災は降りたけれど、2ヶ月の安静期間を過ぎても痛みは引かず、清掃会社は雇止めになった。惣菜屋にも立てなくなって、気が塞いで引き籠もった。
どうしてこんな目に、私が遭うのだろうか。
子どものないなりに、あの街で夫婦二人つましく暮らしながら人生を終える。そんな未来が、あるはずではなかったのか。
「困ったときは助け合うのが江戸っ子でしょう!」
惣菜屋の常連だったシイさんとラキブルさんが、シルバー人材センターの案内を持ってこなかったら、私はどうなっていただろうか。今思えばおかしい。私に江戸っ子を語った二人は、外国と宇宙にルーツを持つのだから。むかし、「江戸っ子ブロックチェーン」という、先祖三代の居住状況から「江戸っ子」かどうかを判定するサイトがあった。「三代続けば江戸っ子」という概念で遊ぶ、ユニークな試みだ。シイさんは審査に弾かれて「そりゃそうだが、なんとかならねえかな」とパソコンに話しかけていた。彼はあのとき、母星の名前でも入力していたのか。
そんなシイさんにどやされ、入本さんに心配されながら包丁を研ぎ、縫い物をする。作業所の休憩所は、昔に戻ったみたいな畳敷きで、利用者たちと卓袱台を囲む。花柄の魔法瓶から江戸切子のグラスに麦茶を注いで飲む。
この空間も、なくなる。
お金がないから、なくなる。
私は目を上げた。北砂作業所は、砂銀から北に一本離れた、稲荷通りという場所に位置している。この通りにも商店が並んでいるけれど、昭和レトロを意識しながら新しい店舗も取り込んで、作り込まれたかたちに変化している砂銀と違って、稲荷通りには気負いがない。家と店が寄り集まって自然にできたような、生活の匂いがする。街灯や軒先テントが張り出して、家並みが詰め込まれ、狭い空に電線が張り渡された眺め。よろよろと進む自転車、汗ばんだワイシャツの背中が風で膨れている。街がある。人がいる。
今度こそ、ここにいたい。
「どんな手を使ってでも」
思わず声に出したとき、シイさんがそっと作業所の戸を開けた。暗がりのなかで、黄色い瞳が光っている。暑さを心配して、ずっと見守っていたのだろう。丈の余った袖みたいな手をびろんと出してきて、その手にはボトルの水が握られている。シイさんが言った。
「こんな手だが」
私は小さく笑った。
「お金、ないもんね」
*
「営業なんて、いつぶりだろう。作業所の空間づくりのためってことで、型落ちのトリニトロンテレビをなんとか備品にしようと掛け合ったことがありましたね。平成レトロもいいもんだってことで、区内の文教施設と連携してる小学校の」
「黙って運転しろ!」
シイさんが一喝すると、入本さんが「ずび」と鼻を啜った。
「緊張すると鼻水が出るんですよ」
「らしくやってくれよ。おめえが社長なんだから」
「社長かあ。でへへ。なったことない」
「だろうな。よくわかるよ」
発電事業への参入には、後ろ盾が必要だった。たとえシイさんが独力で発電をしたとしても、自家消費ではなく売電事業にするためには、様々な手続きをクリアしたうえで、設備を整えるための初期投資も必要となる。スポンサーづくりのために、私たちはオクノキ・プラント・タウンへと向かっていた。
江東区新砂に構築されたスマートシティで、延べ面積は200ヘクタール。AIの統合制御による脱炭素を実現しており、敷地内にある複合オフィスビルなどの消費電力を再生エネルギーが賄っている。区域内には水素ステーションと水素バスの発着場を備え、さらには隣接するデータセンターの排熱の再利用、下水処理場の汚泥から作るバイオマス燃料の活用も実現。ようは、大規模な再エネ設備によって自立発電する、未来都市。肉体発電という究極の自立発電を売り込むには、ぴったりの場所だと、シイさんはうそぶく。私は鼻で笑った。
「いつまで保つか、わからないんじゃない? 今は鳴り物入りでも、設備が古くなれば更新費用で首が締まるでしょ。顔が真っ赤になっても走っていられる根性があるかどうか」
「厳しいじゃねえか。ヒロちゃんには願ったり叶ったりの施設だろうに」
「信じてないのよ。未だにガソリン車が走ってる世の中でしょ。安上がりだから」
かくいうシルバー人材センターの社用車も、おんぼろのガソリン車だ。稲荷通りに借りている駐車場を出ると、大きく丸八通り方面へ迂回する。フロントガラスで、ピンク色のイルカのマスコットが揺れた。自動運転の都バスの後ろについて、法定速度で街を進む。通りに面した木造住宅にも、昭和の人口増を支えた東砂団地にさえも、今や太陽光パネルが湿布のように貼り付いている。現代にしがみつこうとするけれど、壁面は排ガスで煤けて、炭素の時代の名残をとどめている。スマートシティとの落差には目眩がしそうだ。この街が生き残っているのか、取り残されて生き永らえているだけなのか、私には分からなかった。
*
伝手はあった。
OPT内のオフィスビルに入居する電力販売会社に、ラキブルさんのお孫さんが勤めている。3階の共用スペースに現れたカマールさんは、精悍な顔つきの青年だった。私の中では、たまに作業所を覗きに来るあどけない少年のままで、イメージが止まっていた。
「覚えてますか、入本です、作業所の。今は社長なんです。夢の技術です。世界を変える入本です」
入本さんは鼻水を啜りながら、一生懸命に喋った。全く無害なクリーンエネルギーを開発しており、その発電効率の試験のために大型蓄電池を一台借り受けたいこと。成功した暁には優先的に御社に卸します、御社の母体が管理している太陽光発電システムや、浮体式洋上風力発電よりも維持費用がかかりません。もちろん、一夜漬けの丸覚えだった。
ひとしきり売り込みを聞いた後で、カマールさんは、あくまでも紳士的な微笑みを浮かべた。
「お二人が折角、尋ねてくださったのに、申し訳ありませんが……」
ここまでは織り込み済みだ。詳細も得体も知れない発電装置だなんて、まともな会社が乗っかるわけがない。そもそも社内に通されなかった時点で、話は見えている。重要なことは、私たちがこの会社を訪れる、理屈の通る理由があること。そのために私と入本さんに託された任務は、少しでも話を繋いでくれ、ということ。
「お忙しいところ、お時間をお取りしました」
「いいえ。久々にお会いできて嬉しかったです。お元気そうで良かった」
「はい。あの、ええと、いいお天気ですね」
入本さんが機能していない。どうしようかと思ってエントランスを見回した。そこで私は、受付カウンターのサイネージの隣に、手乗りサイズの鉢植えが置かれていることに気がついた。落下する稲妻のような、見慣れない花をつけていたが、佇まいは間違いなく朝顔だ。
「あら、あれって……」私は客商売で培った、人好きのする微笑みを意識的に浮かべる。
「ああ……」カマールさんは照れくさそうに片頬を上げた。
「この時期になると祖父を思い出しましてね。管理会社に頼んで、置かせてもらってるんです」
「実は、私たちも……つい買ってきてしまうの。作業所が鉢植えだらけで……」今度は自然と、顔が綻ぶ。でもすぐに将来への──この歳でなお存在する不安が首をもたげる。
「……来年は買えないかもしれないけれど。シルバー人材センターには予算がないし、私たちもお金がありませんから」自分でも、いやらしい言い方だ。私たちの懐事情と、カマールさんには何の関係もない。けれど、ちくちくと針を差してしまう。
「お金は、大切です」カマールさんは、出し抜けに言った。
「けれど、信頼も大切です。信頼は利益です。コストカットに走りすぎれば信頼を失います。今、私たちの事業はようやく信頼を積み重ねたところです。収益性には乏しいですが、十数年前の再エネ勃興期よりはマシです。新型の太陽光電池はシリコン製で薄型軽量、耐荷重を気にしません。景観保護の観点から、電池のカラーバリエーションも増やせるようになってきました。ようやく、古くからの街並みと、新しい技術が手を取り合えそうなんです。そうすれば発電力が拡大しますから、小さな電気を掻き集めて、利益を上げていく見通しが立つ。ひょっとしたら各戸の副収入に出来るかも知れない。薄利多売ですよ、下町らしいでしょう?」
金銭への目配せを仄めかしたのだと思った。少しずつ商売を軌道に乗せているのだと。そのとき商売ではなく、再生エネルギー自体が軌道に乗っていく。
わたしは、不信を胸に、ただ漠然と街を眺めてきた。だから、当たり前のようにあった太陽光パネルが少しずつ進歩していたことにも、気がつきもしなかった。軽く薄くなったから、どこにでも貼れる。だから増えている。ようやく、昔の建物と今の技術とが、当たり前に並ぶ。
「確かに、本当に夢のエネルギーが発見されたら、魅力的です。でも、積み重ねてきた営為と、せっかくなら共存したい。歴史の積み重ねが、街には溢れています……僕も、祖父や父からの、いろいろな人々からの、積み重ねの賜物です。なぜ、僕がこの仕事をしているのか、わかりますか?」
わたしが黙り込んでいると、カマールさんは言った。
「祖父が言っていたんです。エネルギーで不幸になる人を作ったらいけない、って」
ずきんと胸が傷んだ。それはラキブルさんではなく、私が言うべき言葉かもしれなかった。夫に寄り添うように言ってあげるべき言葉かもしれなかった。
「あの──」
私が口を開きかけたその時、カマールさんの眼鏡のツルが光った。骨伝導式の通信端末のようで、カマールさんはしばし耳を傾け、それから矢を射るように呟いた。
「停電?」
*
このとき、OPTのあちこちで、正体不明の野生動物が目撃されていた。シイさんが化けたものだ。
停電の原因のひとつに、野生動物が電線に衝突しての断線がある。そして、東京都では野生動物の流入が問題化している。シイさんはそれを利用した。あるオフィスビルに的を絞って、受電設備のあちこちをシイさんがダウンさせる。他の施設からの電力融通すら出来ないよう、徹底的に孤立させる。それを野生動物の仕業にかこつけるため、意識的にあちこちで姿を見せる。問題になっている一方で、昨今では動物の権利保護についての議論が活発化していて、こうした先進的な場所では、そうそう手を出されることもない。
かくして停電したビルに、私たちが売り込みをかける。よければいかがですか。高出力のエネルギーを、お得にご利用いただけますよ。
私は立ち上がろうとした。急いだつもりだけれど、身体は緩慢にしか動かない。ソファの上で身をよじり、背の部分を借りてどうにか立つ。擦るようにしか足を運べない。エレベーターまでが遠い。入本さんが、その巨体で重力を吸収しようとでもするみたいに、そっと寄り添う。
「僕だけ先に行くからさ、弘美さんはロビーにでも座って待ってて」
「だめ。私が行かなくちゃ。私には責任がある。私が決めたんだもの」
ようやくタッチパネル式のボタンにまで辿りついて、人差し指を曲げて突く。表面を撫でただけで階数表示が点灯して、少し驚く。力を入れる必要がない。何年も前からこうだったはずで、今までだってタッチパネルは使っていたはずなのに、今さらに凄みを感じてしまう。
振り払わなくては。どんな手を使っても稼ぐと決めた。今さら、過去の優しさや悲しさが覆いかぶさってきたから、なんだ。そんなもので財布は膨らまない。私に必要なものは夢の超エネルギー。その手で掴んだ自分の居場所だ。
エントランスホールの人波は、入館したときよりも増えていた。誰もが差し迫った様子で、通話しながら行き交う。作業着の男女が数人、地下へつながる階段から上ってきて、自動ドアの向こうへと足早に行き過ぎる。周囲からの断片的な会話が耳に飛び込んでくる。
医療モールとデータセンターの冷房だけは死守しろ、東北電力管内のメガソーラーが融通できる、パワコンの手動復帰マニュアル確認して、空調自動制御優先で共用部のIoT機器は一旦切って────。
頭のなかで音の洪水が巻き起こる。ひとつの光景が、フラッシュバックする。あのとき不慮の事態に対処していた人々。
事故を起こしてしまった!
身が竦んだ。はっきりと、自分が間違えたかも知れないという感覚を覚えた。それでも始めてしまったことだ。シイさんもまた、自分の仕事をしているはずだ。
なかば入本さんに抱えられるようにして、中央広場まで出てきた。四方の建造物が一望できて、綿密な都市計画が伺える。けれども──いくら見渡しても、シイさんが停電させたはずのオフィスビルが見当たらない。ふっつりとサイネージが消えた建物が、壁面投影の広告が消えた建物が、見当たらない。
区画をいくつも折れるうちに、「想定より早く復旧した」という雑談が聞こえてきた。やがて私たちが見つけたのは、据付のベンチでうなだれている、エリンギのマスコットキャラクターだった。
「シイさん」
私が近寄ると、シイさんはゆっくりと顔を上げた。
「………すまねえ、ヒロちゃん、入本。俺の力不足だ」
「ちょっと耳に入ってきたよ。ここの技術屋が頑張って復旧させて──」
入本さんが慰めようとするのを、シイさんは遮って、言った。
「ハクビシンがいたんだ」
「……えっ?」
「停電させ切れなかった。地下の電気機械室に、本当にハクビシンがいたんだ。ありゃ、住んでるよ。……騒ぎを大きくしすぎたら、いくらなんでも一帯の一斉駆除が進むかも知れねえ。迷惑は、かけられねえ。俺は……世話になったんだよ」
よかった、と思った。
シイさんは、シイさんだった。私をシルバー人材センターに受け入れてくれた、義理堅い下町の爺さんだった。例え宇宙人でも、下町の爺さんだった。だから、できなくてよかった。私を立ち止まらせてくれて、本当によかった。
「過去って面倒くさいね、シイさん。ずっと絡みついてくる」私は言った。
「全くだ。俺は、非情な侵略宇宙人にゃなれなかった」
「そして私は、やっぱり、原発が嫌い」
「……そうか」シイさんが力なく息を吐いて、また少しうなだれた。それから、ゆっくりと、前を向いた。
「これから、どうするよ」
私はちょっと考えてから、言った。
「地道に、働きましょうか」
*
そうして私達は地道に過ごした。
シルバー人材センターの補助金削減については、都に陳情書を送るところから始めた。活動に色よい反応をしてくれる都議がいて、こんど入本さんと一緒に面会する予定だ。もし作業所がなくなっても顔見知りとは集まれるように、近くの公民館の利用料が無料になるサークルを作った。公民館の和室には、古い花柄のポットが、まだ置かれていた。
未だに私もシイさんもお金がない。一番の問題は、すぐには変わらない。
でも。たった一つの不思議な力で、あっという間に全てを解決してしまう。単純な力で、単純にお金を儲ける。そんな浅はかな時代は、一度だってなかったし、これからもない。何度となく飛びついては痛みを背負った。また同じ轍を踏んではいけない。
だから私達は過去を積み重ねて、今を作らなくてはいけない。
身辺を見回せば、当然のように接している物事にも驚きが溢れている。その中には確かに、過去からの反省と、少しでも良くなろうと未来へ向かう力が、働いている。自分でも気付かないような営みとすれちがいながら、私たちはこの街で生きている。
先日、砂銀に実演販売の店ができた。どうしても私たち高齢者は対面販売に弱い。つい覗いてみると、むかし流行った円盤型の全自動掃除機がリニューアルして売られている。販売員が声を張り上げた。
「ソーラーエネルギーによる自動充電でコードいらずのこの製品、数々の高機能もついていますが、お年寄りの皆さんに一番オススメしたいメリットはね! コードないから、引っ掛けて、転ばない!」
どっ、起きた笑いの渦に、私も乗っかった。ジョークにくすぐられたのではない。
なあんだ、と思ったのだ。無線化なんて、ずっと前から行われてきたことだ。そのために、もう転ばなくて済む。今さら気付かされた。ずっと前から未来は来ていたのだ。
告知
本作は、『トウキョウ下町SFアンソロジー:この中に僕たちは生きている』の連動企画、もう一つの下町SF小説として執筆された作品です。
実は本作の中には、『トウキョウ下町SFアンソロジー』に収録された7編の短編小説に出てくる要素が散りばめられています。ぜひ、『トウキョウ下町SFアンソロジー』も合わせてお読みください。
先行公開日:2025年4月26日
カバーデザイン:VGプラスデザイン部
疎疎笠消去史著者
疎笠消去史著者
下町にゆかりのある覆面作家。