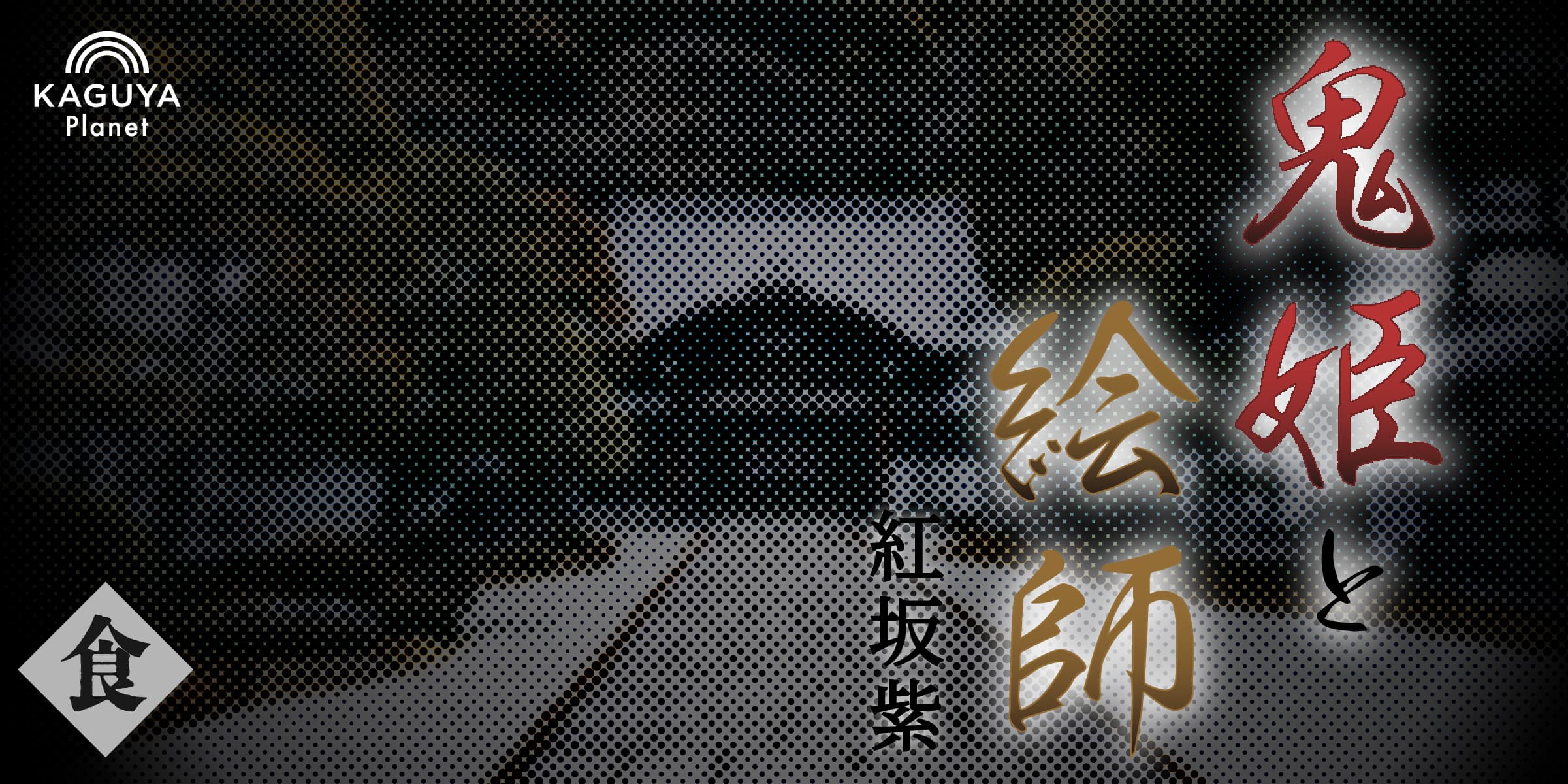
鬼姫と絵師
4,286字
女絵師は、人前でものを食べてはならない、と言われて育った。
なにも絵師だけの話ではなかった。絵師の棲まう村の女たちは、誰もが人前で食べることを禁じられてきた。口を開けてものを入れることは汚れたものを取り込むこと。生きるための欲望を見せることは獣のすると同じこと。子を産むものは殺生による穢れを引き受けるものではない。そのように教えられた女たちは各々部屋に籠り、口を薄く開けて日々の飯を食べた。幼いころは男たちに混ざって肉を食べた覚えもあるが、背が村の社のみかんの木を超えたころから、決して許されない行為になった。
絵師は、村の果てにある社の近くで暮らしていた。父母も、祖父母も絵師だった。父母もいなくなった今では、この女が村でたった一人の絵師だった。社や村での行事のために絵を描くのが絵師の主な仕事だったが、それだけでは生きてゆかれないから、隣村に出て仕事を貰ってくることも、絵師の村で描いた絵を売ることもあった。だから絵師は人前でものを食らう隣村のものを目にしていた。隣村のものたちは絵師の村の男たちのように豪勢な食事をすることもなければ、村の女たちのように隠れて薄く口を開けるようなこともしなかった。女が総出で社に集まり、男たちのためだけの食卓を整えるようなことも、隣村ではなかった。誰もが息をするように自分でものを買い、自分のために調理し、食べた。そこに特別な意味を見出すことはできなかった。だが隣村は隣村で、この村はこの村だ。この村の掟を不思議に思うこともなく、絵師は年を重ねた。この村は少なくとも祖母のころから変わっていない。祖母や母も、祖父や父と同じように絵師をしていたが、祖母や母の絵が祖父や父たちの絵のように売れることはなかった。祖父や父は好きなものを食べ、男たちとの酒席で仕事を取り、あるいは好きなときに好きな絵を描いたが、祖母や母にはそれができなかった。
絵師の絵は、その父の絵よりも淡白だと言われていた。情動が感じられないとも言われていた。絵師はそのことを気にするような絵師ではなかったし、売れ行きが父母のころよりも減ったかと言われればそんなことはなかった。絵師はただ目の前の描かなければならないものを描くにすぎなかった。それは、絵師が生まれたときから絵師として育てられてきたことにも関係があるのかもしれない。絵師は、絵師になりたくてなったわけでも、この村に生まれたくて生まれたわけでもなかった。絵師は毎日同じことの繰り返しを厭うわけでもなく仕事を続けた。
ある日、絵師が絵筆を社に落としてきたことに気がついたのは、夏の新月祭りの後だった。境内で祭りに飾る絵を描いていたところ、帰り道に失ってしまったらしい。きっと村の子どもたちに葉で面を切ってやったときだ、と絵師は考えた。鋏を出したときに絵筆がついてきてしまったに違いない。絵師は窓の外を見やる。社の明かりはとうに消えていて、虫の光も散らばっていない。祭りの後だ、月はない。星のか細い鳴き声だけが社の森をあたためていた。
夜の社には鬼が出る。新月祭りの後は贄が用意されているから、特に鬼が降りてきやすい夜だった。それが子ども騙しの物語でないことは、社の近くで生まれ育った絵師がいちばんよく知っていた。夜の社に肝試しに行って戻らない隣村の若者たちがいた。散らばった贄の残骸の片付けをしたこともある。だが、絵筆がなければ絵が描けない。絵が描けなければ金は手に入らない。明日には下描きを見せると約束した家がある。腕と信頼だけで金を得ている職だ。朝を待てない。そんな暇はない。鬼に出逢ってしまったときのやり過ごし方は、社の翁に教わっている。それが命を絶対に保証するわけではないことも知っている。それでも。絵師はもう一度窓を見る。蝙蝠の羽音が通り過ぎる。筆を、取りに行かなければ。
明かりを手に、履物を履いて家を出た。引き戸を閉める音が響き渡り、やがて社の森に吸い込まれて消えた。絵師は左右を見渡した。明かりの輪郭が輪になって広がるように周囲を照らしているが、五歩ほど進んだ先になにがあるのかは少しも見えなかった。それでも絵師はこの家から社までのことを誰よりも知っている。足を踏み出した。昼間と同じ草の音がしたが、それは昼間とは似ても似つかない響き方をした。息が珍しく上がっていた。己にも恐れというものがあったのだな、と絵師は思った。それは長きにわたり忘れていた感情だった。小さな獣が草間を駆けるたびに喉が鳴る。それでも筆のために、明かりを地面近くで持ちながら社までの道を進んだ。
じゅりゅ、という音が聞こえたのは社まで残り僅か十歩にもならないだろうという瞬間だった。絵師は社の近くにある小屋の影に身を隠した。幸いにも履物の音は鳴らなかった。明かりを頭上に掲げる。顔を上げる。社の奥宮の明かりに照らされて、鬼がいた。
人の女の似姿をしていて殊更に角などが生えているわけではなかったが、それが鬼だということは遠目にもすぐに分かった。港の遊び人を思わせる豪奢な着物を身に纏い、新月祭りの贄や供物を貪っていたからだ。社の翁に教わった通りだ。鬼はふつう人と見分けがつかない。多くは男の似姿をしているが、時折女の似姿をしている鬼姫もいる。鬼姫は特別な新月祭りの夜にのみ現れる。忘れていた。今日は夏至で、新月祭りで、日食いも起きていた。翁はそれが人の生きる間に見られるのは凡そ珍しいことだと語っていたのだ。鬼姫が現れるのも無理はない。特別な新月祭りの夜。絵筆のことばかりが頭を巡っていて、社の翁の話などすっかり抜け落ちてしまっていた。
鬼姫が目に入ってからものの数秒で絵師はそんなことを考えていた。鬼姫はこちらに気がついていない。絵師は我に返り、大事の時に使えと翁に貰った社の染物で口と鼻を覆う。これで人の息が鬼には届かなくなるとのことだった。呼吸を殺して染物を結びながらも耐え切れず、絵師は、もう一度顔を上げて鬼姫を目に焼き付けた。爪の先まで針のように銀と光る手で、贄の肉をもいでいた。滴る血を逆の手で受け止めながら、それを椀の形にして口許に運ぶ。ごくと喉を鳴らしてそれを吞み切る。奥宮の赤い火が鬼姫の汚れた頬を照らしている。供物の水を口の端から零しながら腹の中に運んでゆく。もう一度贄をもぐ。口に皮や繊維ごと運び、ぐちゃ、と表に見える歯で潰す。村から見える天の川のような手で、頬についた贄の体液を落とす。供物の菓子に手を伸ばす。砂糖を手のひらで払い落してから一口でそれを潰し、鬼姫は社で働く女たちが身につける爪紅も飲み干した。鮎の肝を嚙み潰したときの村の子どものような顔をして、それでも鬼姫はそれを一気に飲み干した。食べられないはずのものを口に含んで、鬼姫は笑った。笑ったのだ。
明かりを下げることも忘れて絵師は鬼姫に見入ってしまっていた。人前でものを食べる女を、隣村の女たちとも違って、恍惚の表情でものを食べる女を、絵師は初めて目にしたのだった。絵師は今この瞬間を早く絵に遺さなければと思った。そんなことを感じたのは絵師にとって初めてのことだった。人の前で口を開き、ものを入れ、咀嚼することがこのように汚らしくて、そしてこのように、生き延びる、ことそのものなのだと誰も教えてはくれなかった。食べることが社の奥宮の火のように美しく、絵師の目には映った。村の掟は、村の男たちが定めたものだ。男が絵師たち女に人前でものを食わせない理由が絵師にはやっと分かった。鬼姫のような力を得させないためだった。生きる力を与えないためだった。情動を得させないためだった。ただ細々と生きる以上の力を与えないためだった。鬼姫はこの村で生まれた普通の人間だったのだと絵師は、いまなら分かっている。鬼姫は人前でものを食べてしまったのだ。鬼は村で男に所有されていた身体を解き放ち、隣村へと生きることを探しに行ったのだ。
一つ短く小さな息を吐き、鬼姫は社の表のほうに目を向けた。慌てて絵師は明かりと頭を下げる。訝しげにこちらを見る様子が伺え、ふたたび絵師の胸は隣村まで駆け下りたときのように痛んだが、贄を食べて満足した鬼姫はそれ以上の詮索を止した。鬼姫はその着物の裾を指の狭間に持ち、天女のごとく社の果ての黒の山の上へと身を翻した。山の向こうには港がある。港は、隣村に似ていると聞いた。絵師は駆けて道に落ちていた絵筆を掴むともつれる脚をどうにか動かしながら、元来た道を帰った。それから家に着くなり、その洗面所の鏡に向かって笑った。歯を剝きだして、まるで鬼のように。
その年の夏至の新月祭りを境に、絵師の絵は変わったと言われるようになった。絵師の父の絵に似るようになったとも、それを超えて気味が悪くなったとも言われた。村の子どもたちは絵師に絵を強請ろうとするたび男たちに手を引かれて、やがてかれらも絵師に近づかなくなった。村の人間は絵師の絵を恐れたが、隣村の人間たちには新しい絵は広く好まれた。官能的だと言われるようになった。絵師はそんなこととはつゆ知らず、ただ一心にあの日の鬼姫の絵を描こうとした。鬼そのものを描くわけではない。鬼姫を見た日の胸の揺さぶりをずっと描こうとしていた。食べることを。絵師は今初めてこの村で、生きていた。よく笑うようになった。薄く口を開けるだけの女のようにではなく、業火のように燦燦と、歯を見せて笑った。やがて絵師は掟を破った。人前で飯を食べた。それはしかも、隣村で買った肉だった。歯で肉を骨から削ぎながら、それはそれは美味そうに食べた。社の翁は絵師が鬼姫憑きになったのだと叫んだ。男たちは絵師に松明の火の粉を浴びせたが、女たちは俯いて口を薄く開けるだけでなにも言わなかった。子どもたちは男の影に隠れてじっと絵師を見つめていた。絵師は、まだ幼く、男たちとともに食事をしていたころのことを思い出した。あの時、社の翁が同じように叫び、村から追い出した女がいた。女は歯を見せて笑ったし、幼い絵師を見て泣いた。女は村を出るとき、またね、と幼い絵師に言った。どうして今まで忘れていたのかは分からなかったが、その女がどこか鬼姫に似ていたことに気がついた。
絵師は村を追い出されることになった。一年後の夏至の夜だった。村には絵師がいなくなった。絵師は村の女には珍しく、家族というものを持たなかった。
絵師は、歯を見せて笑った。村のどの女たちよりも軽やかな足取りで、隣村へと降りた。
それから後、新月祭りのたびに、贄の残骸とともに絵筆が社に転がるようになったという。
告知
「食」特集 掲載作品
- 紅坂紫「鬼姫と絵師」
- 清水裕貴「美しい腸のための生活」
- エフゲニア・トリアンダフィリウ「ボーンスープ」(紅坂紫訳)
作品をより楽しみたい方は、マガジン『Kaguya Planet No.3 食』をお読みください。
先行公開日:2024年7月20日 一般公開日:2024年10月14日
カバーデザイン:VGプラスデザイン部
