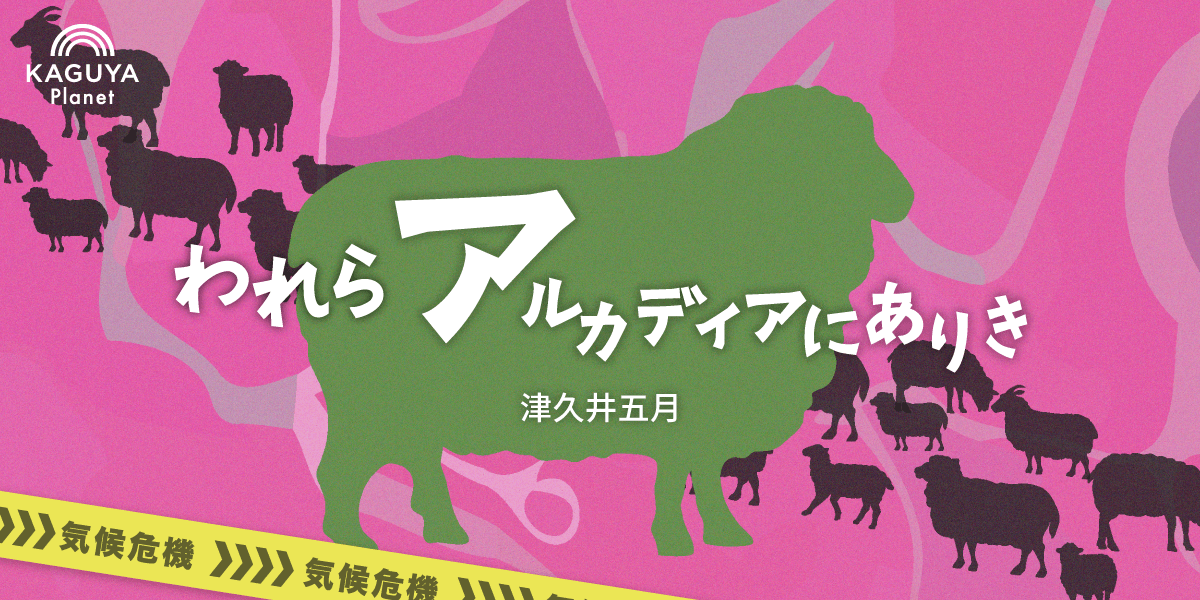9,587字
ケヴィンが料理をするのを見たのは、その日が初めてだった。
やつと俺は三十年の付き合いだが、それまで一度だってなかったことだ。やつは冷凍ピザをオーヴンに入れることすらしなかった。もう死んだ母親や、連れ合いのカレンに全部まかせっきりで、自分はソファに寝そべってFOXニュースを観ているような男だった。二〇〇〇エーカーの大豆畑をやっていた頃も、一帯の畑が全部ダメになって、俺たちみんなヒツジ飼いになってからも、変わらなかった。
それでも、良いやつだ。やつはカレンと一緒に俺たち夫婦を出迎えると、贅肉のついた丸っこい両腕で俺たちを抱きしめた。ほとんど涙声で、気を落とすなよ、と繰り返した。
「ケンもイヴリンも、気を落とすな。大丈夫だよ。ヒツジはまた増やせばいいんだから」
ああ、そうだな、と答えるのが精一杯だった。一週間で一三〇〇頭のヒツジをなくした俺とイヴリンの気持ちが、やつに分かるとは思えなかった。全財産の四分の三だ。穀倉地帯が壊滅したときだって、変化はそこまで急じゃなかった。
だが、やつがやつなりに精一杯、俺たちを励まそうとしているのは伝わってきた。やつは俺たちを解放すると、にやりと笑顔を作った。そのまま古びたキッチンに向かうのを見て、俺とイヴリンは驚いて顔を見合わせてしまった。
「忙しいのに、ごめんね。ケヴィンがどうしても、あなたたちにも食べてほしいって」
俺たちをテーブルに導くと、カレンが言った。困ったように眉尻を下げていたが、ケヴィンと同じく、どこか誇らしげな様子もあった。キッチンではケヴィンが、大ぶりのフライパンの上でスパイスの瓶を振っていた。香ばしい肉の匂いが漂ってきて、全部が冗談なんじゃないかと思えた。家畜小屋の扉を開け放って、苦しみもがくヒツジたちを見たときの衝撃が、おかげで少しだけ和らいだ気がした。
「いいえ、嬉しいわ。ちょっと──驚いたけどね」
イヴリンが応えて、テーブルの下で俺の右手を握った。冷たかった。ヒツジたちの伝染病が見つかってから、春だっていうのに、彼女の手はずっと冷えていた。
「おう、今からもっと驚くことになるぞ」
ケヴィンがそう言ってコンロの火を止めた。じゅうじゅうと鳴く肉をフライパンから皿に転がして、テーブルに運んでくる。それは三ポンドくらいの、分厚い肉の塊だった。表面は土壌崩壊前の畑の土みたいに黒々としていたが、やつがナイフで切り分けると薄いピンクの断面があらわれた。透明な肉汁が滴った。
「悪くないでしょう?」
俺たちが生唾を飲み込むのに気づいたのか、カレンが微笑んだ。
「彼もけっこう練習したの。肉の焼き方を覚えてからは、毎日こればっかりで──ああ、ケヴィン、グラスは新しいのを出してね」
分かってるよ、と言いながら、やつはワインのコルクを抜いた。それは俺たちが普段飲むような安酒じゃなかった。なみなみと満たされたグラスが四つ、テーブルに揃った。俺はさすがに戸惑っていた。元気づけようとしてくれるのはありがたいが、そこまでしてもらう理由はない。口を開きかけた俺を制するようにして、やつはグラスをチンと鳴らした。
「ケン、いいから食ってくれ。肉はたっぷりある。売るほどあるんだよ」
俺は諦めて、フォークを口に運んだ。柔らかい、だが弾力のある歯ごたえだった。スパイスやハーブの香りと一緒に、肉そのものの甘さが鼻に抜けた。
「あれ?」とイヴリンが首を傾げた。「これ──とっても美味しい」
疑ってたのかよ、とケヴィンが笑った。
「こんな上等な牛肉、どうしたんだよ」
コクの深いワインを一口飲んで、俺は訊いた。素直に褒めるのが照れくさくもあり、単に不思議でもあった。やつの笑顔は最高潮に達した。
「美味いよな。でも牛肉じゃない。味が違うだろ」
味音痴と言われたようで、俺は少しむきになった。
「じゃあ何の肉なんだよ」
「羊だ」
「ラム──いやマトンか?」
「そうじゃない。普通の羊じゃなくて、うちのヒツジの肉だよ」
俺は、うつむいてナイフで肉を切り、もう一口を頬張った。ゆっくり噛み締めて、やつの言葉と一緒にワインで腹に流し込んだ。隣では、イヴリンが呆気にとられていた。
家に帰り着いたのは午後五時ごろだった。俺もイヴリンも、本当は一度横になりたい気分だったが、仕事があった。青いシートで覆った家畜小屋の前で彼女を降ろすと、俺はおんぼろの四駆で放牧地を走った。
春でも夕方は寒くて、風が強かった。硬く鋭い牧草がガサガサと揺れていた。十年ちょっと前までは一面、小麦やトウモロコシや大豆の畑だった土地だ。三十代の頃は、俺もケヴィンもモンスター級のトラクターを乗り回して、いっぱしの農家になったつもりでいた。でも、DMTRが土を殺した。俺は、収穫高が倍になると言ってあのマイクロマシンを売りつけてきた連中を許さない。ピカピカの腕時計をつけて都会からやってきた男たちを信用した自分も、許せなかった。
放牧地を走りながらクラクションを鳴らすと、草を食んでいたヒツジたちが揃って頭をもたげた。それから、家畜小屋に向かっていそいそと動き出す。荒れ地と草地が斑になった大地の上を、ずんぐりとした真っ黒な獣が列になって駆けていく光景が、俺は好きだった。だが、その数が四分の一に減ったという事実は胸を締め付けた。
俺は車を降りて荒れ地を見た。干したプルーンの実みたいな、黒くて湿った塊が撒き散らされているのを見て、少し気が楽になった。生き残ったヒツジたちは健康で、快便らしい。イネ科の遺伝子組換え牧草を山ほど食って、DMTRがはびこる死んだ土に糞を落とす。腸内で増殖した善玉マイクロマシンがDMTRを殺して、土地は少しずつ生き返る。そこに牧草が生えてきて、ヒツジたちの餌になる。そういう循環と再生の仕組みを俺は美しいと思った。自分の食い扶持だから、なおさらだ。
群れの後を追って家畜小屋の前に戻ると、電力会社のトラックと入れ違いになった。そのコンテナの中に、伝染病で死んだ俺のヒツジたちがどんなふうに詰め込まれているのか、できるだけ考えないようにした。
いや、ヒツジたちは最初から最後まで、本当は俺のものじゃなかった。電力会社の許可なしにはヒツジはどこにも行けないし、俺が別の土地に連れて行くこともできない。ヒツジは連中の工場で生まれて、死ねばまた連中に回収されていく。俺たちに残るのは、電力会社からヒツジを借りるためにかき集めた金の返済残高だけだった。
「おかえり、ケン」
家畜小屋に入るとイヴリンがいて、俺に寂しげな笑顔を向けた。彼女はしゃがんで、生き残った年寄りのヒツジに毛刈り機を当てていた。刈り取られた真っ黒な毛がコンクリートの床に落ちる。俺は毛を掃き集めて圧縮機に運んだ。ヒツジたちの毛は一カ月で一インチは伸びるから、毛刈りが俺たちの主な労働だ。それが四分の一に減ったということは、収入も四分の一に減るということだった。
ヒツジの毛を圧縮して作る燃料棒は、真っ黒な金塊という感じの見た目だが、ずっと軽かった。金塊なんて持ったことはないが、炭素や水素の方が金より軽いことくらい俺でも知っている。毎週、回収車が一帯を回って、燃料棒を火力発電所に運んでいた。
ヒツジ──生態系およびエネルギー生産のための特殊化草食動物。
そんな正式名称を唱えると、いつもなら心が落ち着くはずだった。壊れた農地を再生しながらバイオマス燃料を作るために、国じゅうに広まった立派な仕組み。連邦政府も州政府も太鼓判の新しい職。だから俺たちの将来は明るい、大丈夫だ、と。
だが、その日は逆効果だった。どこのインテリが付けたのか、紛らわしくて呪文めいた名前が虚しく響いた。誰も助けちゃくれない。家畜伝染病に弱いヒツジを作ったのは電力会社なのに、連中は一パーセントだって責任を取ろうとしなかった。
日が沈みかけた放牧地の向こうに、ケヴィンとカレンの家が見えた。
肉を食った後、そこの地下室で見たものが、まだ信じきれていなかった。
皮を剥がれて、身体を縦に半分に割られて吊り下げられたヒツジたち。
冷凍されたモモ肉や肩肉。粉になるまで砕かれた骨。
そこは、ヒツジの解体室だった。
──食っちまったら、仕事はどうなるんだよ。
怒りが腹からせり上がってきた。ケヴィンが何をしてどうなろうとやつの勝手だが、連れ合いまで破滅に巻き込むようなことは許せないと思った。
心配するな、とやつは俺の肩を叩いた。落ち着いた、自信に満ちた笑みを浮かべていた。
──大丈夫だ。新しいヒツジをくれる人がいる。
「きっと、大丈夫だよね」
イヴリンがふいに作業の手を止めて、俺の背中に声をかけた。振り向くと、ランプの明かりの下に頬のこけた女がいた。俺の連れ合いはこんなに痩せていただろうかと思った。
大丈夫だ、と俺は言った。ケヴィンが出した名前が、まだ頭の中に響いていた。
──ウィリアムズさんが、ヒツジをくれるんだ。
朝、家畜小屋の扉を開け放つと、腹を空かせたヒツジたちが我先にと放牧地に駆け出していく。一〇〇ヤード先から観光客の声がかすかに聞こえた。クリーンエネルギーを生み出し続けるヒツジたちの楽園──そんなイメージに惹かれて、都会からはるばるやってくる物好きな連中だ。だが、ヒツジの数が期待より少なかったのか、歓声はすぐに止んだ。
ヒツジを放つと、俺はイヴリンを隣に乗せて、南に車を走らせた。普段は用事のない方角だった。DMTRに大農地を殺された前の地主は数年前に都会に去った。二束三文で土地を買ったウィリアムズ夫妻は、俺たちと同じくヒツジ飼いをやっているという話だった。
見たところ、土地の再生はかなり進んでいた。見渡す限りの牧草の海の中に、ヒツジの黒い影が点々としていた。なだらかな丘の向こうにその家はあった。派手ではないがどっしりとした印象の、平屋の屋敷だった。重そうなドアは叩く前に静かに開いて、奥の暗がりに大柄な男が立っていた。
「アレグザンダー・ウィリアムズだ。来てくれて嬉しいよ」
深い声だった。禿げ上がった強面だが、笑うと気安い雰囲気が滲み出た。ケヴィンから、話はすべて通っていたらしい。俺たちは名乗る間もなく奥へ導かれた。
廊下には絵が掛けられていた。どれも似たような感じの古臭い絵ばかりだった。ひょろひょろとした木が疎らに生い茂って、その下の地面は柔らかそうな草に覆われている。その草を羊たちが食んでいる。そばには布を身体に巻き付けた男や女がくつろいでいる。文字通り牧歌的な光景だった。
そんな類の絵を何枚も見ているうちに、俺はかすかに苛立った。ウィリアムズも、あの観光客たちと同じかもしれない。ここを地上の楽園かなにかと勘違いして、道楽でヒツジ飼いになった金持ちなんじゃないかと。
だが最後の一枚だけは雰囲気が違っていて、俺の足は止まった。
どうしたの、と訊くイヴリンの目も、その絵に吸い寄せられていた。
髑髏が描かれていた。
暗雲が立ち込めていた。
木の枝は折れ、湿った土がむき出しになって、文字が書かれた汚れた墓石みたいなものの上で髑髏が笑っている。それを、二人の若者が呆然と眺めている。そんな絵だった。
「われアルカディアにもあり」
気がつくと、ウィリアムズも振り返ってその絵を見ていた。いや、俺を見ていた。
「碑文のラテン語は、そういう意味だ。作者は十七世紀前半の画家グエルチーノ。もちろんこれはレプリカだがね。本物はローマにある」
ラテン語も十七世紀もローマも、俺には遠すぎる世界の話だった。
「ところで、〈われ〉というのは何のことだと思う?」
俺たちは顔を見合わせて、さあ、と応えた。
「この……ガイコツじゃないんですか」
その通りだ、とウィリアムズは目を見開いた。
「そう、死だよ。理想郷にも死は存在する。なぜなら生があるからだ」
廊下の突き当たりの扉を抜けると、その先は明るい、あたたかい場所だった。
家畜小屋だ。ランプの下に干し草が敷き詰められて、眠たくなるような匂いを放っていた。そして目の前に、真っ黒の大きな塊があった。それは大柄な雌のヒツジだった。
雌だと分かった理由は単純だ。横たわったその尻のあたりから、濡れた小さな脚が突き出していたからだ。エプロンを付けた年配の女が、その脚を掴んでゆっくりと引き抜いていた。
「ここにも、生がある」とウィリアムズが言った。「国や企業や都市のシステムから押し付けられた役割や、薄っぺらなパブリック・イメージではなく、私たち自身の本物の生がある。私はそれを、君たちと分かち合いたい」
ヒツジの出産を見たのは、そのときが初めてだった。
「この赤ん坊を君たちにあげよう。次に生まれる子も、その次もだ」
アレグザンダー・ウィリアムズは振り返って、俺とイヴリンの肩に静かに手を乗せた。
「その代わり、既存のヒツジは処分してほしい。君たち自身の手で殺して、食べるんだ」
俺たちはしばらく返事もできず、ヒツジの親子を見ていた。
雌ヒツジは涙を流していた。
美しいと思った。俺とイヴリンは互いの手を探って、強く握り合った。
先に覚悟を決めたのはイヴリンだった。
俺は彼女に引きずられるようにして、ヒツジを殺す決心をした。
俺たちは家畜小屋の一つを使うことにした。その小屋のヒツジは病気で全滅していた。消毒後は扉を開けてもいなかったから、中は清潔で、ヒツジの解体には好都合だった。
最初の一頭はめちゃくちゃだった。ネットで見つけた動画の見よう見まねだ。毛を刈ったばかりの年寄りヒツジの脚を縛って仰向けにすると、イヴリンがまず胸を突き刺して、次に喉をかききった。ヒツジは暴れて血が飛び散って、俺は尻もちをついた。
どうにか血を抜くと、俺がノコギリで脚の先を切った。そこからナイフで皮を剥いでいくはずが、上手くはいかなかった。丸一日の格闘の末に、ずたずたの枯れ木みたいな枝肉が出来上がった。試しに腰肉を焼いて食ってみたが、臭くて硬くて顎まで疲れ切った。二人とも気が立って、その夜のファックは激しかった。シャワーで落としきれなかった血の匂いに包まれて、抱き合って眠った。
「本当に生きるというのは、こういうことだと思わないか」
何日か後、俺に仔ヒツジを抱かせながら、ウィリアムズはそう言った。
隣では彼の連れ合いのマーサが微笑んでいた。きれいな灰色の髪の彼女は手練れの助産師で、一日に何十匹もの赤ん坊を母ヒツジたちの腹から引っ張り出していた。
「自分たちで命を殖やし、愛し、そして殺して食べる。生も死も我々自身のものだ。それを証明するために、私はヒツジたちに生殖能力を取り戻してやったんだ。ここで生まれたヒツジたちはもう土地に縛られない。ともに生きるために、わざわざ企業に金を払う必要もない」
俺の腕の中で、柔らかい真っ黒な赤ん坊が震えた声を出した。
「名前はどうする」とウィリアムズは訊いた。「自由なヒツジには名前が必要だ」
「春」とイヴリンが言った。
俺もその名前を気に入った。
独学でヒツジの解体を繰り返す限界はすぐに分かったから、俺はケヴィンに助けを求めた。俺は正直、やつを尊敬するようになった。その手際に俺もイヴリンも圧倒された。
ヒツジの胸を切った後、素手を突っ込んで心臓の血管を千切って殺す方法。
皮の切れ目から握りこぶしを押し込んで、ナイフなしできれいに皮を剥ぎ取る方法。
「これは遊牧民のやり方だ」とやつは誇らしげに言っていた。
それから、血と内臓のきれいな処分の仕方や、枝肉を柔らかく美味くする熟成法も習った。ケヴィンは冷房と冷凍庫が揃った地下室の一角を貸してくれた。代わりに、俺は食いきれない肉をケヴィンにタダでくれてやった。やつは怪しげな食肉業者とつるんで、都会の物好きを相手に肉を高値で売りさばいているらしかったが、俺は首を突っ込まなかった。ウィリアムズから次々と譲られる仔ヒツジが育てば、どうにか生計を立てられる。俺は金よりも、ヒツジ自体に魅せられていた。
ウィリアムズの小屋で生まれたヒツジは、何か大きな力を持っていると思った。電力会社の工場生まれと姿は同じでも、連中にはない、どこまでも走っていけそうな勢いを俺は感じていた。うだるような夏を乗り越えて清々しい季節を迎えた放牧地で、新しいヒツジたちを追って車を飛ばす時間は、幸福だった。
「そう、我々は遊牧民だ」とウィリアムズも言った。
ケヴィンに調子を合わせただけかと最初は思ったが、彼は珍しく眉間に皺を寄せて、人を怖気づかせるような雰囲気で俺たちを見回した。俺は思わずイヴリンに身体を寄せた。
それは、ちょっとした祝いの席でのことだった。ウィリアムズと出会って二度目の春が来ていた。俺とイヴリンは四〇〇頭のヒツジを肉に変えて、代わりに一〇〇〇頭以上を受け取っていた。全部のヒツジが入れ替わる節目に、ウィリアムズ夫妻とケヴィンとカレンを食事に招いたというわけだ。さらにその日の朝、春が妊娠していることが分かって、祝い事は倍になっていた。
「羊飼いは本来、土地に縛られない」とウィリアムズは続けた。「文明の誕生以来、自由に移動する民はいつも王や政府を脅かしてきた。物資や情報の流通を握り、重税を課せられれば逃げ、ときには都市になだれ込んで自分たちの存在と力を見せつけた。しかし、我々はどうだ。大多数は電力会社に管理される惨めな牧童にすぎない。都市の人々はここを理想郷になぞらえて、ヒツジ飼いが背負う労苦やリスクから都合よく目を逸らしている」
そこでウィリアムズは俺とイヴリンを見た。
「だから私たちは、動くべきだ」
「動くって……なんのことです」
俺が訊くと、その表情が急に和らいだ。
「デモだよ。電力会社に──いや、この国のすべての人に、自由なヒツジとヒツジ飼いの姿を見せつけてやるんだ。我々はエネルギーインフラの部品じゃない。電力会社や都市の生活を支える家畜ではない。我々は、ここに生きているんだと」
俺は政治的な人間じゃない。デモなんて、それこそ都会育ちの夢見がちな若者がやることだと思っていた。夫婦だけあって、イヴリンも似たような考えだった。
それでもあの日の行進に参加したのは、自分と同じ目に遭うヒツジ飼いを減らしたかったからだ。その春も家畜伝染病のニュースがあちこちから届いていた。自分の頭をライフルで撃ち抜いたやつが何人もいた。その痛みのほんの一部でも、電力会社や都会の連中に教えてやりたかった。
いや、もっと正直に言おう。俺もイヴリンも、燃料棒の買い取り価格の引き上げを望んでいた。思ったよりもずっと仲間が多いことを知って、薄ぼんやりした願いは強い期待に変わった。ウィリアムズから仔ヒツジを受け取った自由なヒツジ飼いは、州内だけでも一〇〇人に迫っていた。何万頭ものヒツジを引き連れて電力会社を取り囲めば、俺たちの立場は変わる。借金もすぐに返せるかもしれない。そう思うと、急に欲が出た。
「大丈夫、みんな順調よ」
デモ決行の前の晩、マーサ・ウィリアムズは血みたいに濃厚なワインを掲げながらそう言った。うちの小屋で成熟した雌ヒツジは一斉に妊娠していた。腹の膨らんだヒツジたちを連れて行っていいのか不安になってマーサに見てもらったが、彼女は心配ないと請け合った。むしろ、妊娠したヒツジこそデモの主役なんだと主張した。俺たちは納得した。
ヒツジの肉を食ったのは、その夜が最後だった。あの味は忘れられない。繊維が歯をしっとりと包んで、香ばしくて、脂身は甘かった。記念日のために熟成庫に取っておいた、俺とイヴリンの自信作だ。出し惜しみしなくてよかった。次の日からずっと、ここのひどいメシを食うはめになったんだから。
翌日のことは、何度も話した通りだ。あんたら警察の方で調べも進んでいるんだろう。
デモはあらかじめ届け出をしてあったし、興味を持ったメディアがいくつか、うちにも張り付いていた。俺とイヴリンは五時に家畜小屋を開けた。
ヒツジたちはいつも通り利口だった。車で追い立てると、群れになって東へ走り出した。うちの敷地を出るときも何の混乱もなかった。しばらく他人の土地を横切っていったが、どこも荒れ地だ。驚くやつはいても怒るやつはいなかった。
集合場所に着いたのは七時過ぎだった。うちと同じくらいの広さの放牧地に、あちこちの方角からヒツジとヒツジ飼いが集まっていた。ケヴィンとカレン以外はみんな初対面だ。ウィリアムズ夫妻は後から合流すると聞いていたから、挨拶が一通り終わると俺たちは車を置いて出発した。道路沿いに長い列を作って進むヒツジたちは、真っ黒な河みたいだった。
空は真っ青で、暑くても気持ちが良かった。通り過ぎる車のドライバー全員が仰天しているのを見て、俺たちは何度も笑った。気が緩んで、異変に気づくのが遅れたのかもしれない。だが、どちらにしろ、あんなもの止めようがなかった。
列の前方で誰かが叫んだのが聞こえた。
何が起こったのか、しばらく分からなかった。渋滞中は信号が変わってもすぐに動き出せないのと同じだ。先頭のヒツジたちが全速力で駆け出してから、俺の周りのヒツジも走りはじめるまで、一分か二分の時間差があった。でも群れ全体が一度動き出したら、徒歩では追いつけなかった。車を取りに戻れる距離でもなかった。俺たちはわけもわからないまま、土埃の中に置き去りにされた。
あんなに走ったのは、ハイスクール以来だ。胸と脇腹を押さえながら、俺とイヴリンは街に入っていった。爆発で抉れたアスファルトや、燃える車や、飛び散った赤い肉片を見たが、街の中心部にたどり着くまではその意味が分からなかった。
いや、今も意味なんて分からない。
ウィリアムズはどうして、俺たちに爆弾なんて育てさせた。
思想や動機なんて興味はない。ウィリアムズやマーサがどんなカルトに属してようが、どこの国に操られたテロリストだろうが、そんなことはどうでもいい。知りたいのは、どうして俺たちだったのかってことだ。人の疎らな荒れ地なら、当局にバレずにテロの準備を進められると思ったからか。それとも、不満を抱えた学のないヒツジ飼いなら、手玉に取りやすいと思ったっていうのか。
あんたらがしつこく訊いてくるような、遺伝子改変だとか子宮内マイクロマシンだとかの話は、俺にはさっぱりだ。だが要するに、雌ヒツジたちの腹を膨らませていたのは赤ん坊じゃなくて、体内で合成された爆薬だったってことなんだろう。そのことは、あの場にいれば分かった。
大通りはひどい有り様だった。まだ若いヒツジが火だるまになって駐車場に突っ込んでいくのが見えた。その火が別のヒツジの毛に燃え移った。それは丸い腹を抱えた雌のヒツジだった。バイオマス燃料に包まれたその身体はたちまち燃え上がって、オフィスビルの入り口あたりで激しく爆発した。俺は熱い風で吹き飛ばされた。
それから、どうにか立ち上がってイヴリンを探した。彼女は五十ヤード先にいて、暴れる一頭のヒツジに追いすがっていた。
離れろ、と俺は叫んだ。
「この子、春だよ!」と彼女は叫び返した。
どうしてだろう。俺はそれを聞いてヒツジに駆け寄っていた。
一緒に死んでやろうだなんて思ったわけじゃない。イヴリンとヒツジを抱きしめると、真っ黒な毛は柔らかくて、草と土とスパイスが混じったような匂いがした。
春は生きていた。俺はそのとき、自分の手で殺して食ったヒツジたちのことを思った。伝染病で死んだヒツジたちのことも思った。どのヒツジも愛していた。本当だ。美味かった。それも本当だ。
春が不発弾だった理由は知らない。思いが通じたからだなんて思わない。とにかく、彼女は震えていた。だから俺たちはずっと彼女を抱いていた。震えと一緒にその心臓の鼓動が消えて、冷たくなっても、抱いていた。あんたらに引き剥がされるまで、ずっとだ。
カバーデザイン:VGプラスデザイン部
津久井五月「われらアルカディアにありき」はKaguya Planetの「気候危機」特集の掲載作品です。特集では気候危機にまつわる3編の短編小説を配信しています。また、「気候危機」にまつわるブックレビューやコラムを収録したマガジン『Kaguya Planet 「気候危機」特集』を刊行しています。マガジンの情報はこちらから。