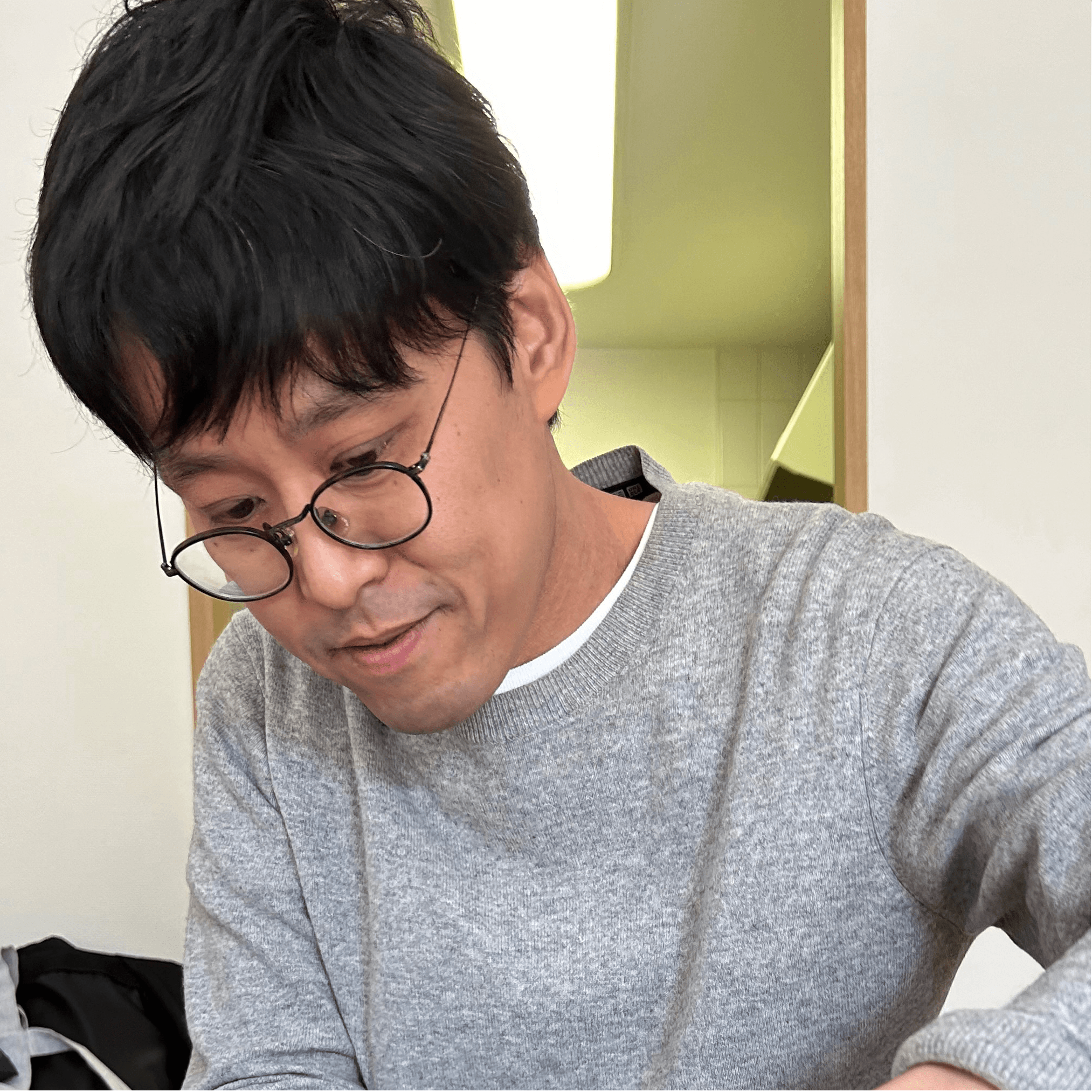上映会のおじさんたち
7,126文字
ある晩、仕事場から帰ってくると、先に帰っていた妻がテレビの前に陣取って映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の放送を観ていた。物語の山場はとっくに通り過ぎていた。親友のドクが発明したタイムマシン、デロリアンで1955年へと迷い込んでしまった、マイケル・J・フォックスが演じるマーティはそこで起きた問題を解決し、1985年へと無事に帰ってきていた。若き日のドクの助けを借り、舞台であるヒル・バレーの街では知らぬ者のいない時計台への落雷の電力をタイムスリップに利用したのだ。今度は2015年へと飛び、デロリアンを空飛ぶ車に改造して舞い戻ってきたドクが、画面の中では、21世紀とはかくあるべしという人工的な格好で、マーティとジェニファーの前に現れて、こう告げていた。
「未来が大変なことになってる!」
そして、ふたりを連れてもう一度未来へと向かう。そのラストの場面だけを、懐かしさのあまり上着も、マフラーもニット帽さえも外さずに、テレビの前でしばらく棒立ちのまま観た。それは、子供の頃にくり返し観た映画を、今世紀に入ってからは機会もなく四半世紀近く経ってようやく観た、ということだけが理由ではなかった。かつて、私の生まれ育った町の、実家が営んでいたスーパー村田の「中庭」で、父たちが『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の上映会を開いたのを思い出したからだった。
とはいえ──と補わなければならないことがふたつある──、まずこのスーパー村田というのが、おそらく多くの人が思い浮かべるようなスーパーマーケットとは似ても似つかないということだ。かつて古い都のあった市の南部の、都とは独立した碁盤の目の入った小さな町に私たちは暮らしていた。その町のとある区画は、ほかの区画と同じように通りの側からはただ古い木造家屋が並んでいるようにしか見えない。だが、南北に一箇所ずつ民家と民家の間を潜り抜けることのできる門になったところがあって、そこから覗けば区画の内側には古めかしい石畳の空間が広がっており、外側の民家とは別に内側にはその石畳の庭のぐるりを長屋のような二十軒ほどの店が軒を並べて囲んでいた。それぞれは本来は独立した商店だったのだが、それらを束ねてまとめて支払いできるように、しかもツケ払いできるようにしたのがうちの父であるらしく、それらの店店をまとめて「スーパー村田」と称していたのだ。その南北の門の上に掲げられた看板には「スーパー村田」の文字があったが、月日とともにペンキが薄くなっていた。いったい、どうしてそのような店の並ぶ空間がこの小さな町の中にできあがったのか、またどのような経緯でそれを父がスーパー村田と束ね称することになったのか。今となってはわからない。「虹の立つところに市が立つ」という伝承の通りだというような話を祖母から聞かされたことがあるが、風が吹けば桶屋が儲かるということわざのようなもので、それでなるほどと納得がいくようなものではない。
何よりもそこで父が中心的な役割を果たしていたということがまったくもって謎なのだ。仕事を怠けるようなところなどまったくなかった父だが、しかし、率先して何かをやる、とか、誰かを統率するような人ではまったくなかったのだ。だから、上映会を開いたのはスーパー村田であり、となれば責任者は父であったわけなのだが、それはどこかの店主たちから強く求められてやむなく開いたという経緯にちがいないのだった。ひょっとしたら、この頃すでに近くにできていた大規模なスーパーマーケットに押され、スーパー村田の経営は苦境に立たされていたのかもしれない。しかし、それは今では中年になった私が想像しているに過ぎず、小学生であった私はそんな事情など気にすることもなく、ただ上映会を楽しみにしていたのだった。そして実際それでいいわけだ。人に楽しんでもらおうとして、上映会を企画していたわけだから。
当日の土曜日、当時は昼まであった小学校から急いで帰り、門をくぐり抜けると、すでに店主たちは準備に追われていた。やがて父よりも少し年配の髭を生やした小柄なおじさん──後にも先にもこのおじさんを観たのはこの一度だけだ──がやってきて、門の脇に置いた機材を中庭の中央へと何遍も行き来して運びはじめた。それに付いて回るようにして父が(私もそれに付いて回っていたのだが)、ぼそぼそと何かを言うと、そのおじさんが言った。
「あんたもほんまに真面目な男やなあ。どうもないんや。どこでもやってるわ」
おそらく、父は気にしていたのだ。そのどこから貸し出されてきたか定かではない映写機とフィルムが、営利目的での使用を禁ずるものであるはずだと。ふつうなら学校や図書館や公民館というような公的な施設での上映のために貸し出しているものなのだろう。そして、スーパー村田はスーパーマーケットであるかどうかは別としても、明らかに営利目的で営まれているのだったから、どこかに知れたら、大ごとになる。ただ、おそらく最初に話をつけてきたどこかの店主は──酒屋の大川さんだったと思うけれど──、上映会はこの真ん中に広がる営利に資することのない「中庭」で行われること、そして映画の鑑賞料を取らないことを理由に挙げて、どう考えても非営利の催しであるのだと説得し、一度は父も納得していたのだったと思う。けれど、その日は朝から肉屋の佐々木さんも酒屋の大川さんも上機嫌で店の前の中庭まで屋台を大きくせり出し、上映機材の設営をはじめた時には、まだ上映会まで4時間もあるというのに、早くも佐々木のおじさんはコロッケや串カツを油で揚げるほどの張り切りようであった。この張り切りようはちょっと言葉で言い表しがたいもので、ただ目を見たらわかる。興奮で瞳孔が見たことのない大きさに保たれていたのだ。だから父の一度は納まっていた、フィルムの使用目的の後ろめたさがくすぶるのも無理はない。いくら映画の鑑賞料を受け取らないとしても、上映会をまたとない稼ぎ時と考えていることは明らかであったからだ。
「こんなに派手にやってどうもないかなあ」
「大丈夫や、任せとけ!」
そう言われてなお一層、恐ろしい気分に父はなったにちがいない。
いや、あるいは父が気にしていたことというのは、もうひとつの「説明を補わなければならないこと」によるものだっただろうか。その日上映されることになっていた映画は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ではなく、その続編『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』だったのだ。いきなり、PART2の上映会をして、人が観に来てくれるだろうかという心配を、あの設営にやってきたおじさんにこぼしていたのかもしれない。しかし、映写技師のおじさんは、父の方には顔も向けず、黙々と設営を続けたから、父はあきらめて俯いたまま店に戻って行った。私は、おじさんに付いてまわり、設営の一部始終を観察していた。二本の長い木の棒を間隔を空けて置いたビールケースにそれぞれ立てて縛り付け、その間に白いシーツのような大きな布を張るのは、いくらひとりでなんでも器用にやるおじさんにも助けが必要だった。
「そっちの端を持っといてくれるか?」
ようやく自分の役割を見つけた私はこれ幸いと手伝った。一方の棒に布から出た縄を縛り付けると、こちらまでやってきて、私が持っていた端を引き取ると、もう一方の棒にその端の縄を縛り付けた。
「ええか、布を棒に縛り付ける時に、しっかりと引っ張ってからぐっと縛り付けるんや。ぐっとな。布が皺にならんように」
その独特の縛り方をなぜか今でも憶えている。あいにく、今のところそれを役立たせる機会はないのだけれど。
スーパー村田の二十軒ほどある店のすべてがこの上映会に乗り気であるわけではなかった。設営が終わってから、私は店店に上映会のことを言って回ったが、理髪店の小川さんは、
「映画の上映やったから言うて、ほな髪の毛切りに行こうかいうお客さんはおらへんで」
と言ったし、スーパー村田ではなく、門を出た向かい側で喫茶店を開いている北山さんでさえも、上映会に来た人たちで、いつもよりも忙しくなることを、むしろ、
「堪忍してほしいわ」
と言っていたくらいだ。
そうかと思えば、洋服屋の石川さんは、この上映会のことを近くに住む親戚に片っ端から電話して知らせ、午後も早々に集合させていた。気づくと、客席の前の方にほとんど瓜ふたつの顔をした人たちがズラリと陣取っていたのには驚いた。いやまあ、集客といえばそうなのだが、おそらく父たちの狙いはそこではなかった。
建具店の岸本さんの工房に入っていくと、まるでその仕事を絵に描いたみたいにちょうど木材をかんながけしていて、かつお節のようなかんな屑が宙に曲線を描きながら吐き出されていた。その奥でお茶を飲んでいた岸本さんの奥さんが、
「どんな映画なの?」
と聞いた。
「1985年から2015年に、そして1955年にタイムスリップする映画です」
まだ観ていない私は映画紹介で読んだとおりのことを形式的に言ったのだが、
「1955年……」
とため息がちに反芻した奥さんには、その年が琴線に触れたようだった。かんな掛けする手を止めた岸本さんが、
「ああ、あの洪水があった年やな。ものすごい台風が来て、何日も雨が降り続いて、堤防が決壊したんやった。わしは、その堤防を治す仕事でこっちのほうに来て、それでここで仕事するようになったんや。あの時は、土手を走ってた電車の線路ごとぜんぶ流されてしもうたしなあ」
と懐かしい思い出を語った。
外がずいぶんと騒がしくなり、岸本さんの玄関を外に出ると、スーパー村田の中庭は、人でごった返していた。私が物心ついてからこれほどの人で埋め尽くされているのを見たのは後にも先にもこれ一度きりだ。肉屋の佐々木さんはコロッケや串カツを揚げ続けていた。左手で揚げながら、右手でお客さんにバットに上げた串カツを、コロッケを、そして串カツとコロッケをという具合に次々と紙にくるんで渡していった。酒屋の大川さんは、紙のカップにサーバーからひっきりなしに生ビールを注いでいた。
やがて日がすっかり暮れた。人々は席につき、座りきらない人は、スクリーンと座席を囲むように立っていた。私も店のおじさんたちと並んで立ち見した。照明が消え、スクリーンにいよいよ『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』が映し出された。
「未来に一緒に来てほしい。未来が大変なことになってる」
最初のシーンは『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の最後のシーンと重なり合っている。これがさっきテレビで観た場面でもあり、それゆえ上映会のことを私はこうして思い出したのだが、考えるまでもなく、未来といっても、私が暮らすこの現在からはすでに過去であるのは、可笑しな気持ちになる。
三人はその未来へとデロリアンで向かい、子孫が直面している問題をどうにか解決しようとする。ところが、固唾を飲んでその事態を見守る私たち観客の後ろで、とつぜん、男たちの声が聞こえてきたのだった。
「おい、えらい儲けてるやないけ!」
後ろを振り向くと、ビールを注いでいる大川さんの胸ぐらを男が掴んでいた。ふたりか三人の短髪の若い男を後ろに従えた、こちらも若いが他よりはいくらか歳を取った男が、大川さんをどやしていた。映画を観ていたお客さんたちも気が気でなくて振り向いている。その時、私はとっさに思ったのだった。このフィルムと映写機は、貸し出されたものではない! どこかの映画館からこのヤクザたちに盗んで来させたものなのだ! そして、その報酬として何かを渡したのだが、それはインチキで、そうそうに騙されたことに気づいたヤクザたちが、復讐のために上映会に乗り込んできてしまったのだ! と。そんな想像をしたのは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の冒頭の場面が頭にあったからだ。タイムトラベルの実験に必要なプルトニウム燃料をリビアの過激派グループに原発から盗ませて、それと贋物の爆弾を交換条件にしてドクが騙し取っていた。しかし、それは子供の安易な妄想だった。映画のようなことはそうそう起きない。このフィルムと映写機の調達に、何某かの形でこのヤクザが関わっており、酒屋の大川さんがその窓口になっていたのは確かなようだが、決して盗品ということではなかったのだった。とはいえ、予想以上に盛況となったこの上映会を目の当たりにして、このヤクザがもう少し金を巻き上げようとしたということだったのだろう。そして、私は客席の後ろに立ちながら、スクリーン上の映画と、それから後ろで繰り広げられるヤクザと店主たちのやりとりを両睨みで窺っていた。
そこに、父が何やら台帳のようなものを持って現れたのだ。そして、ヤクザの目をしっかりと見てゆっくりとこう言ったのだ。
「ここにうちのスーパーの台帳がある。あなたがたの組が購入した品物のツケが随分と残っている。もし、追加の謝礼を要求するというのなら、このツケをまずは全部支払ってもらいたい」
むろん、そんな言葉だけでヤクザを追い払うことなどできたはずがない。それでは印籠を掲げることで悪者たちをひれ伏させてしまう『水戸黄門』のままではないか。しかし、そういう安易な展開で事態の収拾は図られたものだと私はその時、納得してしまったのかもしれない。あるいは大人たちは子供の目の届かないところで、落とし所となる取引を済ませたのだろう。だから、本当のところは、どうやって追い払ったのか。そこは記憶が定かでないのだ。私の記憶では上映は最後まで行われた。それにそんなトラブルが忘れ去られるくらいのとんでもないことがその後に起きたのだ。
映画の半ばをすぎてから、次第に強い風が吹きはじめていた。その度に布を張っただけのスクリーンがうなったが、おじさんとともに強く結んでおいた布は、さすがビクともしなかった。それに風でうなる音は、やがて風が吹き、雨が降り、雷が落ちて、デロリアンに乗ったドクを西部開拓時代に送り込んでしまう映画のクライマックスシーンに、ドルビー顔負けの臨場感を与えることになった。
今にも雨が降り出しそうな気配があった。上映が終わり、あたりに灯りがつくと、お客さんたちがせわしなく帰っていく。その時だ。中庭に光の柱が立ち、あたりはまるで昼間のように一瞬明るくなった。同時に、ドーンというものすごい音が鳴ったのだ。このスクリーンの両脇に立てた木の棒に雷が落ちたのである。落雷による停電で照明が消え、暗闇になった中庭でスクリーンを支えていた二本の棒がたいまつのように炎を上げてゆっくりと燃えていた。皆が腰を抜かして石畳に尻餅をついていると、岸田のおじさんが玄関から表に出てきて、中庭にあいた広い空を見上げてこう言ったのだ。
「この土地は、雷が落ちやすい」
*
「こんな不思議なこと信じられないでしょ?」と、思い出していくうちに私が興奮して話していると、それまでただ話を聞いていた妻が、
「ねえ、村田くん」
と話しはじめた。
「それは不思議だと思うけど、でも不思議というなら、あなたの話に女の人がほとんど出てこないことのほうがずっと不思議なんじゃないの?」
そう言われて、私は頷くよりほかなかった。私は思い出された記憶に忠実に話したわけだったが、そこからは女の人の姿がほとんど消え去っていた。まるで『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で写真に写っていたマーティやお兄さんの姿が、物語の中で過去が変わっていくにつれて、次第に薄く消えてしまったみたいに。
「たしかに、あなたの生まれ育った町では、そんな事件があり、そしてその中心にはおじさんたちがいたのかもしれない。そして、その人たちが今でもあなたの無意識のなかで生きていて、時折顔を出し、あなたの意思に対しても影響をもっているのかもしれない。けれど、スーパー村田に来る人の多くは、日々の生活に必要なものを求める人たちだったのでしょ? だとしたら、その空間は、いま村田くんが語ったような男の人たちが中心であるよりもむしろ女の人が大勢いる風景になるはずではないのかなぁ」
「そのとおりなのだけれど……」
そこに居たかもしれない人を付け加えていくことはできる。けれど、それは今ここで私の知っている女性像で判を押したように書き込んでいくことにすぎず、それは金属に金属を糊で無理やり貼り付けたようなもので、一体になったイメージが浮かび上がってくることはない。どうしたらいいんだろうか。
「スーパー村田によく買い物に来ていた友だちのお母さんとか、具体的な人を思い出して、何を買っていたとか、何を話したとか。ほら、例えば幼馴染の石田くんのお母さんが……」
「まったく逆のことになるけれど、スーパー村田が女性ばかりになった日のことを思い出したよ」
「女性ばかり??」
「そうそう。近くの神社の祭礼で男たちがみな神輿を担ぎに出払ってるんだ。それでスーパー村田は女の人だけ。もちろん、老人や子供はいるし、だから子供だった私はその光景を覚えているわけだけど」
「じゃあ、そこから順に思い出していくといいかもしれないね」
「だけど、これはまた話が長くなるよ? 朝まで掛かる」
「よし、朝まで聞こうじゃないか!」
妻のその威勢のよさに、まるで斑点柄のねじり鉢巻をしている姿が思い浮かぶようだった。しかし、私が一転して女性ばかりのスーパー村田の風景を話しはじめると、あの威勢よさはどこへやら、気づけば妻は寝息を立てて眠っていた。ここに雷が落ちれば、驚いて目を覚ますにちがいないのだが、と私は思いもしたが、ここはその土地ではないのだった。
告知
「おじさん」特集 掲載作品
作品をより楽しみたい方は、小説に加えて、おじさんにまつわるコラムやブックレビューを収録した『Kaguya Planet No.5 おじさん』をお読みください。
先行公開日:2025年3月29日 一般公開日:2025年4月29日
カバーデザイン:VGプラスデザイン部
作家・編集者。京都府出身、博士(理学)。二〇一八年に自主制作本『『百年の孤独』を代わりに読む』を全国の本屋さんへ営業したことをきっかけに、翌年、ひとり出版社・代わりに読む人を立上げ、雑誌『代わりに読む人』やわかしょ文庫『うろん紀行』、佐川恭一『アドルムコ会全史』、青木淳悟『憧れの世界 ──翻案小説を書く』(いずれも刊行は代わりに読む人)の編集を手掛けた。「代わりに読む」というアイデアや、《パリのガイドブックで東京の町を闊歩する》シリーズ(代わりに読む人)など、独自の問い、独自の視点を打ち立て、読者を思わぬところへと連れていくユニークなスタイルが魅力の書き手だ。二〇二三年にはエッセイ・小説集『ナンセンスな問い』(H.A.B)を刊行。二〇二四年には、『『百年の孤独』を代わりに読む』をハヤカワ文庫から刊行した。敬愛する作家は、ガルシア=マルケス、後藤明生。