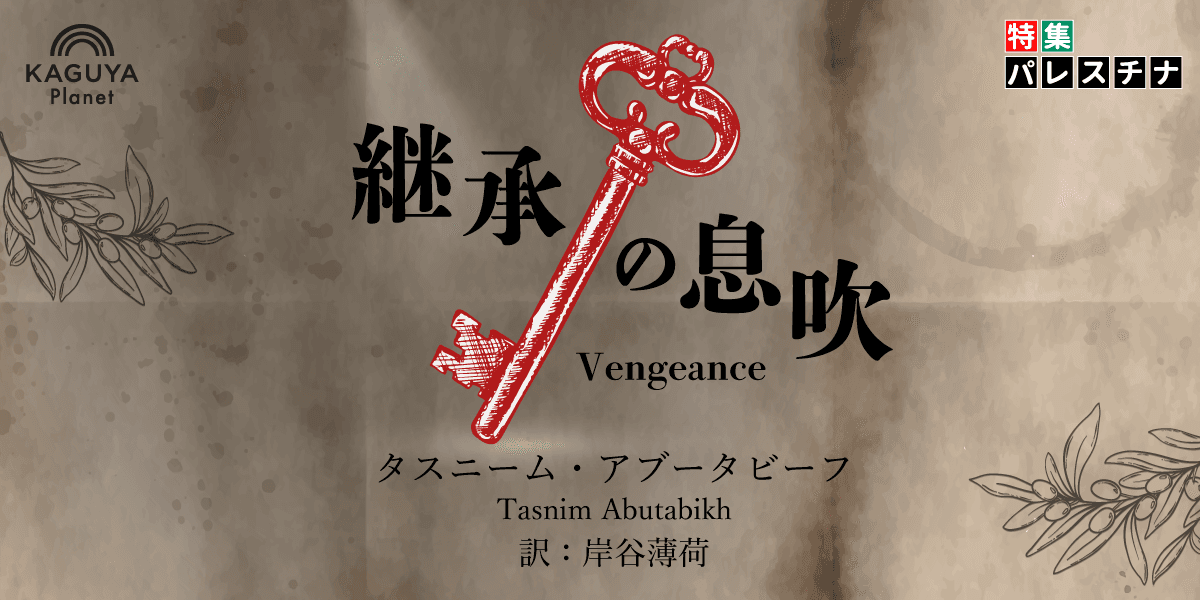
継承の息吹
原題:Vengeance
翻訳:岸谷薄荷
9,407字
アフメドの足取りが重くなった。心臓の音が聞こえる。数分後には、全ての責めを負うべき男と会うのだ。
数時間前、男の居場所を突き止めるために雇った私立探偵から電話があった。探偵によるとユーセフ・アブドゥルカーデルは35歳の男やもめで、アルナーセル通りで小さな工務店を営んでいる。主な商売は、地元のサイボーグたちのための、C型義足500、I型義肢350といった義肢の修理や改修だという。ここ数年でこれらの義肢の市場は急成長した、と探偵は付け加えた。通話が終わるや否や通知音が鳴り、自宅と仕事場の住所を含むアブドゥルカーデルの基本情報が全て入ったフォルダが送られてきた。アフメドは即座に、アブドゥルカーデルに会いに行き、知り合いになることを決意する。でも、どうやって? まだそこまでは考えていなかった。
通りは狭く、ガザの他の通りと同じように薄暗かった。もしかしたら世界じゅうのどの通りも同じように暗いのかもしれない。道を歩きながら、空間を獲得することが何よりの優先事項だった頃について考えていた。親たちの世代は急激な人口増加によって、ここガザ地区でも他の場所でも、祖父母の世代が想像もしなかったほど狭い通りに立つ、祖父母の世代のものよりも高い建物に、より密集して暮らさざるを得なくなった。しかし、空間の確保という危機は、ほんとうの危機の前ぶれに過ぎなかった。人口過密を緩和するため、後先を考えずに世界各地で農地の都市化と森林伐採が進められたが、この開発はより重要なものをこの惑星から奪い去った。肺である。今や大気は二酸化炭素に満ちており、地球全体の平均気温は20年前よりも4度上昇した。
すぐ横の壁にサッカーボールがぶつかり、アフメドの思考は現在に引き戻された。何人かの子どもたちがエア・サッカーをしていて、ボールをパスし合いながらホバーボードで苦もなく飛び回っていた。汗に濡れた髪が、黒く重いライフマスクの後ろにのぞいているのが見える。子どもの一人がアフメドに近づくたびに、マスクのフィルター構造を通り抜ける空気の音がシューシューと聞こえた。
子どもたちをよけて歩きながら、アフメドは明るく照らされた空を見上げた。ずっと消えない雲に覆われている空は、夜のあいだじゅう広告や訓告の背景として使われていた。CMに出てきた子どもたちをみて、アフメドは少し笑った。みずみずしい緑の野原を走り、なんの補助装置もなく綺麗な空気を吸い込み、地面の上でぶつかり合って笑っている子どもたち。機械的な声が「子どもたちのために、よりよい未来を。団結して地球を守りましょう」と告げている。「朝の空気を吸って涼しい風を感じるなんて特権、この子たちが手に入れられるなんて言ってくれるなよ」と、アフメドは思った。牧歌的な、濾過された空気のなかの生存圏は、先進国だけが所有することのできる贅沢だった。
アフメドが近づくにつれ、アブドゥルカーデルの横顔がくっきり見えてきた。送られてきた写真を見ていたから、店の入り口に座っている男がそうだとわかった。冷たい雰囲気とむっつりした表情を想像していたが、彼は優しげな見た目の男で、せいぜい7歳くらいの女の子を膝に乗せてその義手をいじっていた。男がジョークをいうたびに、女の子は空いた方の手でお腹を押さえ、頭を前後に揺らしてポニーテールをばさばさと振り、マスク越しにも涙を流すほど笑っているのが見えた。
アフメドは声をかけあぐねてふたりから数メートルのところで足を止めた。少しのあいだ、所在なさげにアブドゥルカーデルの方を見つめていたが、彼の方から大きな声で「アッサラーム・アレイクム、兄弟!」と声をかけてきたので我に返り、戸惑いながら挨拶を返した。
「どうしたんだい?」アブドゥルカーデルが親しげな笑顔でいう。
「ああ、ええと、仕事を探してて」アフメドは最初に思いついたことを口に出した。「もう1年くらい探してるんだけど、ぜんぜんだめで。機械エンジニアなんです。スキルが役に立てばいいけど、でもなんでもやります。床掃除とか、工具にオイルを差したりとか、ゴミ出しとか。母親が病気で、お金が必要なんです」
アブドゥルカーデルは、茶でも飲みながら話そうと言ってアフメドを店の中に招きいれた。お茶のグラスを手渡しながら、「で、きみのお母さんはどんな……」と尋ねる。
「重いC型肝炎で、余命1ヶ月なんです、あの、つまり、1ヶ月後にマスクが無効化されてしまうんです」母の病状を説明するとき、まぶたが引きつった。
言葉が染み込んでいくひとときがふたりのあいだに流れたのち、アブドゥルカーデルは目を逸らして、咳払いをしてからいった。「で、きみはどうするつもり?」
「診断書をアルハーフェザ病院に送りました。肝移植を受ける資格はあるんだけど、そのためになるべく早くお金を貯めないといけないんです」母親の病気のことを利用しているのが恥ずかしかったが、嘘ではなかったし、本当にお金が必要だった。
アブドゥルカーデルは立ち上がってため息をついた。「明日から来なさい」
「8時ちょうどに来ます」アフメドは約束した。
「待ってくれ、名前はなんだった?」
「アフメド・アルバルダサーウィー」
「ユーセフ・アブドゥルカーデルだ」アフメドの背中を軽く叩いて彼はいった。
(知ってます)と、アフメドは心の中だけでささやいた。
店を出るところでちょうどやってきた卸業者にユーセフが挨拶するのが聞こえた。漏れてくる会話を聞き取れるかもしれないと思い、アフメドは店の横の小路にとどまった。
やがて、店の中から声が聞こえてきた。「もう1ヶ月経ったぞ。なのにまだ500シェケルを用意できていないわけか」と卸業者が怒鳴る声だ。
「もう1週間だけ待ってくれ」
「1週間でなにが変わるっていうんだ」卸業者の声は皮肉げである。
「宝くじに当たるかもしれないだろう」ユーセフは笑う。
とつぜん、卸業者の声色が変わった。「1週間だな」
アフメドは自分のライフマスクをいじりながら路地を離れた。あんなにも簡単に業者が支払いの遅延を了承するものなのか。しかし同時に、自分が手に入れた良いニュースに頬を緩めてもいた。ユーセフ・アブドゥルカーデルは金に困っている。
3週間が経ち、アフメドはユーセフの店での仕事にも慣れてきた。毎朝、店の前の壁に寄りかかって、アブドゥルカーデルがシャッターを開けるのを待つ。店の入り口の階段では、店主が冗談を言いながらクッキーを用意してくれるのを子どもたちがわくわくと待っていた。1日おきに、錆びたI型義肢350を装着した肉屋のアブームハンマドが足を引きずりながら通りを渡ってやってきて、ひとしきり怒鳴っていくことも知っていた。アブームハンマド曰く、調整が必要なだけで新型の義肢はいらないそうだ。アフメドはとくに、店を訪ねた最初の日に出会った、半義体化した女の子・ロアーを可愛がっていた。先生や友だちについて、あるいは糖尿病を患いながら生きることについて、ロアーの他愛のないおしゃべりを聞くのがアフメドにはとくに楽しかった。金曜日をのぞいて、ユーセフは日が暮れるとバックヤードにある個室に閉じこもった。読んでもいない本が積まれた本棚が並ぶダミーの壁の裏に、隠し部屋があるのだ。誰も、アフメドでさえも、その部屋に入ることは許されなかった。そして金曜の礼拝前に店を閉めると、アフメドは家に帰された。ユーセフはこのあと、いったい何をしているんだろう。
働き始めて4週間が経った金曜日、アフメドは、自分がなぜここにいるかを忘れてしまう前にユーセフの行動を突き止めようと決意した。終業後、ユーセフにさっさと職場から追い払われたあとで、アフメドは例の小路に入り込んだ。待っていると、小さな箱を手に持ったユーセフが道に出てきた。アドレナリンが血管を巡りだすのを感じたアフメドは、見つからない距離を保ちながらユーセフを追跡しはじめた。
暗く静かな通りが一瞬ごとにより暗く、より静かになっていく中、アフメドは45メートルくらいの距離を保ちながらユーセフを追った。やがて、通りというよりも裏路地といった方がよいような、古ぼけた倉庫が両側に立ち並ぶハバシュ通りにたどり着いた。とある倉庫のドアの前でユーセフが突然立ち止まり、そのドアを2回ノックするのが見えた。年季の入った自販機の陰に隠れながら、ユーセフと挨拶をかわす男の姿をなんとか捉えることができる。背が高くてがっしりしており、レザーのロングコートを着ている。その後、ふたりとも倉庫の中へと消えた。ユーセフが何をしているのか知らずに帰るわけにはいかなかった。外壁に覗き穴となるひび割れでもないか探しながら倉庫の周りを回って、二人の男の横顔をはっきり見ることができる窓を見つけた。
男たちの表情を伺うことはできなかったが、背の高い男が怒ったように大きく手を動かしているのが見えた。ユーセフは彼の肩に手を置き、それから持ってきた箱を手渡した。ためらいがちに中身を取り出す。ライフマスクだ。
アフメドは目を見開いて後ずさった。誰にも装着されていない状態のマスクを見たのは生まれて初めてだった。ガザ市民は全員、出生と同時にライフマスクを着けられる。マスクは身体に適合し、成長とともに拡大して、色も変わっていく。時に修理が必要になることもあるが、決して付け替えはしない。未登録マスクの密輸は違法行為だと誰もが知っている。身元がばれないように犯罪者が着用するからだ。しかし、この名もなき廃倉庫でロングコートを着た頑強な男にマスクを手渡しているのは、アフメドの上司なのだ。そのときアフメドの背後で物音がして、体格の良い男が窓の方を見た。すんでのところで顔を引っ込めたアフメドは、男の顔を微かに見ることができた。店を訪ねる人々の中で、ユーセフの秘密のバックヤードに立ち入ることを許されている唯一の男だった。商談をしに来ていたのだろう。ドアが閉まったその瞬間、いつも大きな罵声が漏れ聞こえてきていた。近づきすぎてしまった、そう思ったアフメドは、ライフマスクについたスマートグラスを使って二人の写真を撮ると、全速力でその場を離れた。
家に帰りながら、アフメドは頭の中を整理していた。帰宅すると、母親のフェルヤールがお帰りを言い、アフメドを抱きしめた。「今日はどうだった?」母親に嘘をつきたくなかったアフメドは、「夕飯はなに? チーズとオリーヴのサンドイッチが一日中食べたかったんだ」と話をそらして母の手を握り、目だけで悲しげに笑った。
「いま作ってあげる! そういうことは遠慮しないで言いなさいよ」母親は明るく笑って答えた。「子どもに食べさせてあげるのが、お母さんの幸せなんだからね」
母親が台所へ行こうとするので、アフメドは彼女のもう片方の手をとってこちらを向かせた。「母さん、ほんとは、気分はどう? って聞きたかったんだけど」
「昨日とも、一昨日ともかわらない。何事も神様の思し召しなのだから」
「そうなんだ」アフメドはテーブルについた。母親はアフメドの知っている中で一番強い女性で、だから、母親の元気が日に日になくなっていくのを見ると、アフメドも弱気になった。
楽しげにサンドイッチ作りを始めようとするか細い姿を見て、アフメドは「正しいことをしよう」と決意した。周りの人たちのために、でも何よりも、母親のために。ユーセフを売るのだ。明日、イスラエル当局に出向いて写真を渡し、引き換えに母親のマスク無効化の期日を引き延ばしてもらうのだ。
次の日、アフメドはうなだれて警察署から出てきた。イスラエルの治安部隊員に写真を手渡して昨日見たものを説明しているとき、自分の大切な最後の部分を売り渡したように感じていた。
生気のない目で、耳鳴りを抱えて、アフメドはユーセフの店に向かった。到着するとユーセフが背中に手をおいたが、「お母さんのことか? また調子が悪いのか?」と尋ねられるまでアフメドはそのことにほとんど気づかなかった。彼は何も答えず、目を逸らした。
「おいで」とユーセフがいう。「見せてあげるときが来たようだ」
ユーセフは店の裏手に周り、少々苦労しながら本棚を横にスライドさせた。後ろから現れたドアをユーセフは開け、アフメドについてくるよう合図しながらその奥へと入っていった。
「ここ数週間、作っていたものがあるんだ」ユーセフはドアを後ろ手に閉め、デスクを回り込んで小さな引き出しを開けた。
「これはきみのお母さんに」大きなペールブルーのライフマスクを取り出しながら、ユーセフは言った。「知っているだろうけど、健康で犯罪歴がなく、IDF(イスラエル国防軍)に脅威ではないと分類された人物を示す色のマスクだ。お母さんに残された時間はあと1週間だったね、これでもっと時間稼ぎができる」それから、彼はアフメドに封筒を手渡した。「そしてこれは給料の前払いだ。必要な治療を受けるための手続きを急いで進めてもらうためのね」
アフメドの胸が高鳴った。「僕があなたを疑っていたあいだに、あなたは僕の母親を助けるためにずっとここで仕事をしていたって? 嘘だ、あなたは犯罪者でしょう?」
「俺を疑っていた? 犯罪者?」ユーセフが眉根を寄せた。
「僕はあなたのことも、家族のことも知ってるんだ!」ユーセフを憎んでいるそもそもの理由に縋りつきながら、アフメドは声を荒らげた。「そうだよ、あなたは犯罪者だ。法律を潜り抜ける犯罪を手助けしてるんでしょう。昨日あなたを尾けて、それで、ギャングと秘密の取引をしているのを見たんだ」
「俺を尾けたって?」ユーセフは息を呑んだ。「ギャングってなんのことだ? あの男はロアーの父親だぞ。容体が悪化して、昨日マスクが無効化されるところだったんだ。だからお前の母さんのと同じように、ロアーにも時間稼ぎのためのマスクを作ってあげた。見ていたのなら、大人のギャングのためのマスクではなく子ども用の黒いマスクだったことだって見えただろう。それに、俺の家族と何の関係がある?」
アフメドの激しい気持ちは、少女の名前を聞いて融解していった。最近、会うたびにロアーの調子が悪くなっていくのを見ていた。ユーセフは正しかった。マスクがなければ、ロアーは今頃死んでいたかもしれない。
「で、俺の家族と何の関係があるんだ、アフメド」
ユーセフはより大きな声でもう一度聞いた。
アフメドは、ユーセフの目に怒りが満ちているのを見てとった。「そもそも、どうして僕がここに働きに来たと思う? 復讐のためだよ」
アフメドが知っているストーリーはこのようなものだった。かつて、ある百姓がいた。裕福なパレスチナ人が所有する農場とそこにいる家畜の世話をして、妻と二人の息子を養っていた。人々はこの裕福な地主を、みなに助言や手助けを施す村の重鎮だと考えていた。
ある夏の夜、百姓の一番下の息子が農場の馬小屋で眠っていた。母屋で寝るよりも涼しかったから、彼はたびたびそこで寝ていたのだ。ところが、ある時点で息が詰まって目覚めた。あたりを見回しても、煙と燃えている干し草が見えるばかりだった。馬たちはパニック状態で、後ろ足で立ち上がったり足を蹴り出したりしており、いななきが夜の空気に満ちていた。少年は即座に、このごろ出回っていた、「村が焼き尽くされる」という噂を思い出し、それが現実になってしまったことを悟った。皆、地主の庇護があるなら安全だと思っていたが、そんなことはなかったのだ。
百姓の息子は口と鼻を覆う布を見つけだし、小さな体を馬小屋の窓にねじ込んで外に出た。そこにひととき立ち尽くし、燃え盛る炎を眺めていたが、すぐに家族のことを思い出した。両親のいる家に走って戻ったが、兵士たちが家に放火しているのを目撃して、足取りは遅くなった。一瞬のうちに炎が窓ガラスを舐めはじめた。何世代にもわたって住み継いだ家族の思い出が、煙となって空に昇っていくようだった。
両親と兄はすぐに見つかった。家の裏庭で3人の兵士にライフルを向けられ、手を宙にあげて立たされていた。少年は駆け寄りたかったが、低い壁の陰にしゃがみ込んだきり、足は無力にも動かなかった。少年はずっと、この日母親が着ていた服を覚えていることになる。白地に赤の刺繍入りのワンピースだ。母の視線は兄の顔に釘付けになっていた。一方、兄はライフルの銃身を見つめていた。
兵士の一人が母親の身体を掴むと、母の叫び声がその夫、そして年上の息子の叫びと重なった。他の兵士がライフルに弾を込めたとき、少年は隠れていられなくなって足を踏み出したが、同時に兄が母親に向かって突進した。ほんの数メートルも行かないうちに、兄は銃弾に倒れた。母親の絶叫は途中で途切れ、耳が聞こえなくなってしまったような静寂の中、白いワンピースに赤が広がっていった。父親は銃弾を待つまでもなく、あまりの苦しみに胸を掴んで地面に倒れ、事切れていた。
何年も後になって、真実が明らかになった。少年の父親が頼りにしていた地主は、父親や地域の人々を裏切って土地をシオニストに売り飛ばしていたのだ。兵士から逃げ出したその日から、少年は家族を殺したものたちに復讐をすることを誓った。たとえ、どんなに長い時間がかかっても。
「その地主はあなたの曽々祖父だ」アフメドは言った。「そして少年は、僕の曽祖父」
ユーセフはその言葉を噛みしめながらひとときアフメドを見つめ、それから尋ねた。「どこでその話を聞いた?」
「小屋の火事と兵士の話は、子どもの頃にほとんど毎晩聞かされて育った」アフメドは拳を握りしめていた。「僕が継承したんだ。後日談の方はあなたの曽々祖父が土地を売った相手の日記を元にした本で読んだ。ヤヒヤー・サーレフって人の本」
「その名を言わないでくれ! 知らないとでも思ってるんだろう」ユーセフが鋭く言った。「俺の曽々祖父は愛国者だった。敵に土地を売るつもりなんてなかったんだ。真逆のことをしようとしたんだよ。母親が病気になり、カイロで治療を受けなくてはならなくなって、曽々祖父は友達だと思っていた人の申し出を受け入れた。そいつこそ、お前がこのあいだ名前を知った人物だよ。ヤヒヤー・サーレフは侵略者から土地を守ってくれると言ったんだ。持ち主が土地にいた方が安心だと言われたから、曽々祖父は一時的に権利書を手渡した。サーレフは、友が帰ってきたら権利書を返すと約束した。そう書いてある契約書に署名すらしたんだ。だが、曽々祖父がカイロに発って1週間後、この友人は潜入したシオニストだったことがわかった。農場で働く人々を裏切って、ユダヤ軍の側についたんだ」
シオニストの植民者たちは、パレスチナの土地を支配し所有することを正当化するために、いろいろな策を巡らせた、とユーセフは言った。アラブ風の名前を持ち、アラビア語を流暢に話すシオニストたちは、ビジネスマンのふりをしてパレスチナにやってきては、地主にいろいろな提案をした。パレスチナ人ではない人たちのあいだで流布した噂によれば、中にはこの提案を呑んだパレスチナ人もいたという。でもそれは、パレスチナの大義を傷つけるためにわざと誇張されて流された噂だ。土地が売られることがあるとすれば、それは地主が攻撃の噂でパニックに陥り、考えなしに手放したから。それにしたって、極めて稀なケースだ。ほとんどの場合、土地は嘘や単純な強奪によって奪われた。「でも、歴史のことなんていまさら誰が気にする? 本当にあったことなんて──」とユーセフは言った。「今は俺たちの学校で使ってる教科書すら、ヨルダンでつくられているじゃないか」シオニストたちは、ユーセフの曽々祖父をお金で買うことはできなかった。だから、病気の母親への愛をダシにして、騙したのだ。
ユーセフは本棚に置いてある箱からファイルを取り出し、「見てみろ」といいながらアフメドに色褪せた古い書類を手渡した。「曽々祖父とヤヒヤー・サーレフの間で交わされた契約書だ。サーレフが破った約束の概要が書いてある。イスラエルの裁判所はこんな書類、ご覧になってもくださらないわけだ」
部屋中の空気の重さがすべてユーセフにのしかかってでもいるかのように、彼は机に手をついた。「わからないのか? 俺はおまえの敵じゃない。おまえも俺も、相手にするべきはひとつ、同じ敵なんだよ。俺たちを互いに敵対させ、俺たちの生活の全てを隅々まで、呼吸する空気に至るまで支配している相手だ」
アフメドはヘビーブローを食らったような気持ちだった。彼は罪なきひとりの男の人生を壊してしまったのだ。膝から崩れ落ちたアフメドはユーセフと目を合わせることができずに、「もう手遅れだよ、奴らが来る」と口ごもった。
「何をしたんだ、アフメド」
「あなたをイスラエル当局に売ったんです! 昨日のマスクのやりとりの写真を渡してしまったんだ」
ユーセフはアフメドの腕を引っ掴んで立ち上がらせた。
「すぐ逃げるぞ! 母さんのマスクを隠せ」
ふたりが偽の壁を本棚で隠し終わったと同時に、遠くからサイレンの音が聞こえてきた。
ユーセフはアフメドの方を向くと、切羽詰まった声で囁いた。
「お前は俺の知ってる中でもいちばん聡明な人間だ。良心がある。ロアーとの接し方を見てたから、わかってる。偽の情報に惑わされてしまったのなら仕方がない。信じてるからな、アフメド。俺の仕事を引き継いでくれると、信じている。俺が始めたことを続けてくれ、いいな」
ユーセフは自分の言ったことをアフメドに染み込ませるように、両手で彼の顔を挟んだ。「聞いていたな、わかったか?」
「うん」アフメドの顔を涙が伝った。「約束する」
次の瞬間、浮遊する小さなドローンの戦隊が店の入り口を突破し、イスラエル兵たちがテイザー銃をユーセフに向けてなだれこんできた。兵士たちは手を挙げるよう口々に叫びながら銃床をつかってユーセフを道へと押し出した。小隊を率いる中尉が大声で外の人々に呼びかけると、野次馬がさらに広がった。「お前たちはこれから、法に背き、我々が懸命にもたらそうとしている秩序を乱した人間がどうなるかを目撃する!」と宣言すると、補佐官に向き直り、悠々と指令を下した。「マスクを無効化しろ」
重装備の補佐官が前に進み出て、ユーセフの側頭部でIDカードをスライドさせたのち、左耳の後ろにあるスイッチを切った。ユーセフは息を呑む観衆の真ん中で、1分ほど平静を保っていた。その後、首を両手で掴んで膝から地面に崩れ落ち、窒息しはじめた。顔色が紫になり、のたうち回っていたが、3分後にはそれも止んだ。兵士が脈拍を確かめ、止まっていることを合図した。小隊は速やかに車に乗りこんで走り去り、後には地面に無防備に投げ出された死体だけが残された。
ユーセフがイスラエル兵にマスクを無効化されたという知らせは、次の日には町中に広まっていたが、このみせしめは彼らが意図したものとは逆の効果を人々にもたらした。町の住民たちに広がったのは、恐怖ではなく、怒りだった。
その晩、ユーセフの葬儀には何百人もの人々が参列した。彼が助けた人々とその家族(その中には卸業者も含まれていた)、彼が助けられなかったけれど、その努力に希望を見た人々の遺族。それから、この男の身の上を知って駆けつけた人もいた──心臓病を持って生まれ、「ハイコストな人間」リストに入れられた彼の娘が、わずか2歳のときにマスクを無効化されたことを。それからはマスクの無効化を宣言された人々のために人生を捧げてきたことを。
3日後に行われたユーセフの追悼式で、アフメドは母親と一緒に座っていた。その朝、アフメドは母親に、ユーセフの最後の仕事を手渡していた。ペールブルーのマスクだ。その日は、アフメドが鏡の中の自分の目をやっと見返せるようになった日でもあった。睡眠不足で目は充血し、ひどいくまができて、髪は乱れていた。彼は3日間、デスクにかじりついていたのだ。計算式、設計図、そしてスケッチがすでに積み上がっていたデスクに。スケッチのほとんどはもちろんユーセフのものだったが、すでにアフメドは自分のアイディアを書き始めてもいた。上司の遺したデザインをより効果的にするための方法を探し、地元で手に入る素材を使った、より安価な製品を作るやり方を考えていたのだ。
式が終わり、みんなが立ち去っても、アフメドは帰らなかった。モスクの裏手にある、ユーセフのホログラムが投影されている部屋へと向かう。ためらいながら頭を上げ、明るい笑顔を浮かべるユーセフの姿を眺めた。マスクのないユーセフを見るのは新鮮だった。でもここに本人がいてくれればと、アフメドは願った。もう一度笑い声を聞きたい。マスクにつけたガラスのバイザー越しに、顔に寄った笑いじわを見たい。
アフメドは髪を掻き回し、頭を抱えた。震えるため息をつくと、ユーセフの姿が涙で滲んだ。涙を拭いて歯を食いしばり、誓いを立てる。「命をかけて償うよ、ユーセフ。あなたの想いを、必ず実現します。僕たちの土地は仮に取り戻せないとしても、マスクをひとつずつ作っていくことで、必ず、僕たちが呼吸している空気を取り戻します」
告知
「パレスチナ特集」特集 掲載作品
作品をより楽しみたい方は、マガジン『Kaguya Planet No.2 パレスチナ』をお読みください。詳細はこちらから。
先行公開日:2024年6月15日 一般公開日:2024年7月16日
カバーデザイン:Ikumi・VGプラスデザイン部
"Vengeance" by Tasnim Abutabikh.
First published in 『Palestine +100』(Comma Press), 2019 ©Tasnim Abutabikh
Translated with the permission of the author.

タスニーム・アブータビーフ著者
タスニーム・アブータビーフ著者
1996年パレスチナ・ガザ生まれ。ガザのアル=アズハル大学を卒業したのち、2018年にアメリカに移住。2015年にスウェーデンとガザの文化交流を目的とした団体Novell Gazaが主催のNovell Gaza短編賞を受賞し、受賞者アンソロジーである『Novell Gaza 2』に作品が掲載。現在はマサチューセッツ州で歯科医をしながら執筆活動をしている。
1993年生まれ、北海道出身。編集者、ブックキュレーター、ライター。得意分野は海外文学。「岸谷薄荷」名義で、ジェーン・エスペンソン「ペイン・ガン ある男のノーベル賞受賞式に向けたメモ」、 R・B・レンバーグ「砂漠のガラス細工と雪国の宝石」(いずれもKaguya Planetに掲載)、ジェニー・カッツォーラ「パーティトーク」(井上彼方・紅坂紫編『結晶するプリズム 翻訳クィアSFアンソロジー』収録)の翻訳や創作を行ってきた。フェミニスト。
佐佐藤まな監修
佐藤まな監修
英語翻訳者。主な翻訳作品に映画『鉄道運転士の花束』『リトル・パレスティナ』(日本語字幕)、ジェームズ・ウェルカー編著『BLが開く扉 変容するアジアのセクシュアリティとジェンダー』(青土社/2019)(共訳)など。『現代詩手帖』2024年5月号「パレスチナ詩アンソロジー 抵抗の声を聴く」に翻訳・解題などで参加。
