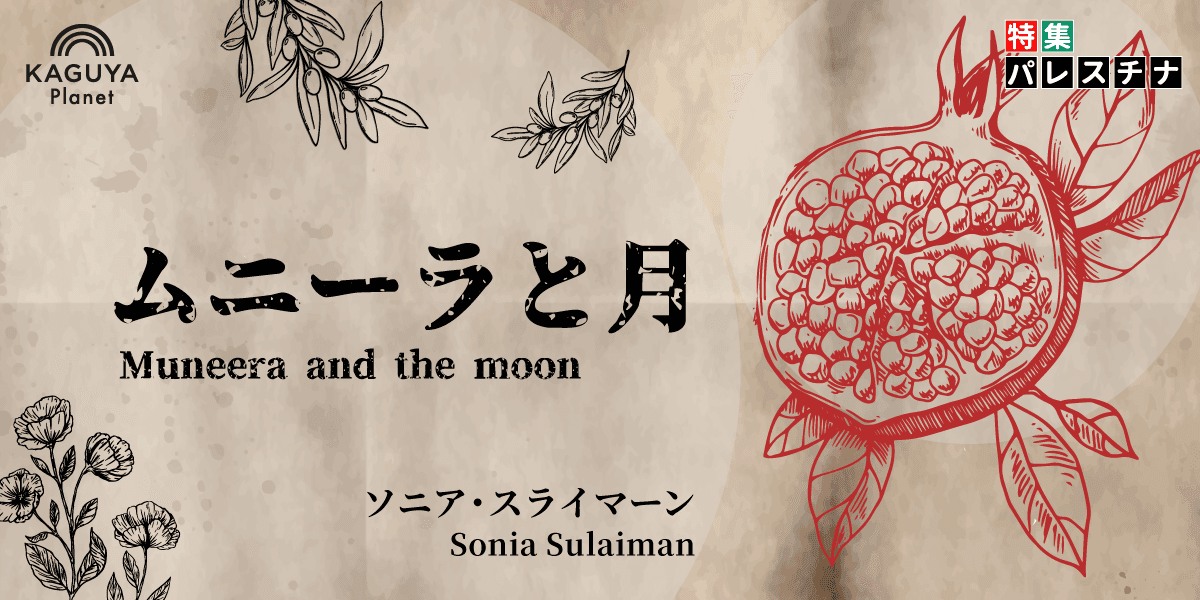
ムニーラと月
原作:Muneera and the Moon
翻訳:岸谷薄荷
監訳:佐藤まな
そこは、霊的な存在が現れるのにうってつけの状況だった。その柘榴の木は40年以上もの長きにわたり、涸れ川が擁する村を遥か遠くまで見おろして立っており、果実をつけた、重く比類なき枝を揺らしていた。長くうねる繊維のらせんが枝の隅々にまで絡みついている。祈りのために結びつけられたリボンを吹き抜ける絶え間ない風が、神聖な恵みの泉を波立たせた。近くには、かつて栄えた帝国の廃墟が立ち並んでいたが、それぞれに唯一無二であったそのかたちは時が経つにつれて風化し、今となっては丸柱の土台が残るのみとなっていた。その白い表面には、柱の石材のように丸く栄えたいと願う村人たちによって結び付けられた赤い糸が横切っていた。形代への願掛けだ。絶好の条件がこんなにも揃っているのだから、この木の中に光が躍っていようと、祝祭の日や聖日に遠くから祈りの歌声が響いてこようと、誰も驚きはしなかった。
その夜、空は暗く澄み渡り、幾千もの光によって刺し貫かれていた。丘の静寂の中に、誰も耳を傾けるもののない雷が落ちると、雷鳴は空からではなく、地面からとどろいた。柘榴が生えている堅牢な大地が裂け、深い溝が口を開けた。赤みがかった閃光が鮮やかな色を柘榴の木に投げかけると、その溝からひとつの影が現れた。大地が揺れ動き、溝が塞がると同時に、影は脚を振り上げて地上によじのぼり、柘榴の木の横に立った。
その影は精霊だった。ジンは、まるで優しく抱きしめてくれているかのように木の枝の間から降り注ぐ月光を見上げた。月光はジンの顔を照らした。黒い肌で輪郭は丸く、王冠のような形に結い上げられた太く長い三つ編みを頭に戴いている。彼女は柱の土台に、厳かに、何かを耐え忍ぶように座った。
ジンは、闇の中では紫にも見える黒と赤色の刺繍が入った長い衣を整え、長いこと黙ってあたたかな月明かりを浴びていたが、やがて眼の上に手をかざし、黒々としたまつ毛の下から月を見上げた。「今夜は明るいんだね」と、いたずらっぽい微笑みをうかべて彼女は言った。「こうやって見るのがやっとだよ。ねえお月様、ちょっとこのムニーラのために薄暗くなってくれない? 雲がいたら同情してくれたかもしれないけど、今日はこんなにも澄んだ空なんだし」彼女は膝を抱え、座ったまま上体を起こした。
ジンは顔を半分隠して、人里離れたこの地を、切望と胸の痛みを語る言葉で満たした。陽のもとから追いやられ、愛に飢えたイヴの隠し子の言葉。月には、どんな隠し事も秘密も痛みも打ち明けていた。
ジンは毎晩その場所に戻ってきては、天界の静かな観察者に語りかけた。「地上にも地下の世界にも、私といてくれる人は誰もいない。知識を何世紀も蓄えてきたからって慰めにはならないし、あたためてもらいたいときに頼れる人もいないから、私はますます眠れなくなっていくの。私の話に耳を傾けてくれる人すらいないんだ。柘榴の枝が心の病に効くと言われていてよかったよ。こんな状態がこれ以上続いたら、どうしようもなくなってしまいそう。
世を忍ぶ者のひとりとして、陽光の中を歩くことも地球上の女性と恋仲になることも期待するべきではないとわかってはいるよ。でも、わかっているからってさみしくなくなるわけではないし、私の感情は、分別があるとされる振る舞いとは逆の方を向いてしまうんだ。
人間を地上から拐って恋人にしてしまう男のジンの話はたくさんあるけれど、女性のジンの恋人になった女性の話なんて聞いたことある? それに私は、犠牲者を支配して誘惑して、意志を奪ったり心を壊したりして縛りつけたいわけじゃない。パートナーがほしい、それだけなの。
こんなに哀れなこと、ほかにある? それに……私みたいなジンが、こういう気持ちになったり打ち明けたりすることがあったとして、聞いてくれる人なんて……いったい誰が聞いてくれるんだろう」彼女は激しい口調でつけたした。
「でも、私が聞いているよ」月が言った。柔らかな声だった。
ムニーラはよろめきながら立ち上がった。
「聞いてほしいなら、私がここにいる」声が続いた。
ムニーラは光を、物言わぬ月だと思い込んでいた光を無理やり見上げようとした。眩しくて見上げることができず、トーブから護符を引っぱり出してその銀色の小箱から紙片を取り出した。彼女が顔をしかめながらその紙を自分と月のあいだにかざすと、紙片に書かれた文字がまるで金箔のようにかすかにきらめいた。
「死に損ないだね」ムニーラは警戒した口調で言った。「幽霊や悪鬼とおしゃべりする趣味はないんだ。で、あんたは幽霊? グール?」ムニーラが腕を振ると、その手に半月刀が現れた。真っ白に輝き、聖なる紋章や数秘術の術式がびっしりと刻まれている。彼女は柱の土台から降り、柘榴の木の周りを用心深くまわった。「それで、何を企んでいるわけ?」
月の光が揺れ動き、木から離れるにつれ暗くなった。枝をすべり落ちる光の束が靄となり、そこから人影が現れた。裾にかすかに赤の差した、なめらかなトーブを着ている。手には、ごく簡素な短剣が握られている。歩み寄ってくるにつれ、彼女を取り囲む後光はいくらか薄れた。彼女はそこに立って、ムニーラを見上げた。
「私は聞いていただけだよ……」
「もう話は充分!」ムニーラは殺意をこめて叫び、刀に火をつけた。ふたたび狙いを定め、体をかがめて待った。ムニーラが月と勘違いした、幽霊の頭を取り囲む後光は、空高くにぼんやりと浮かぶ月の光を今もなお凌駕している。彼女はその光を頼りに突進した。動きを見切った幽霊は彼女を避け、ムニーラは方向を変えようと体勢を立て直した。
半月刀の炎が後光の中の顔を照らした。最初は微笑する口元がかすかに見えただけだった。口角の上がった、珊瑚の唇。意地悪な顔ではなかった。ムニーラは何度もその顔に刃を向けた。炎がきらめくたびに、顔全体が見えてきた。その幽霊は美しく、信じ難いほどに強かった。ムニーラは決して手を抜いていたわけではない。普段ならどんな戦いでも3回以内の攻撃で片付けられるが、この戦いは延々と続いた。ムニーラは体力が消耗するのを感じ、幽霊は攻撃を避け、打撃を吸収し続けた。
どうしてこんなことがありうるのだろう。幽霊は強かったが、スピードと呪術においてはムニーラに利があった。でも、そのどちらも効かないのだ! ただの幽霊が、こんなにもたくさんの聖印や術式を跳ね返すことができるものか。怒りが湧いてきた。この存在に心の叫びを打ち明け、いちばん傷つきやすい秘密を打ち明けてしまったのだ。だから負けかけているの? 相手が私を知りすぎたから? 幽霊は一分の隙もなく、疲れも知らず、すべての攻撃を予測していた。
「どうしてそんなに強いの?」ムニーラは噛み締めた歯のすきまから訊ねた。幽霊の防御は堅かった。白い刃のオーラに照らされて、幽霊の顔のほとんど全体が見えた。黒い瞳が刃の向こうからこちらを見ていた。優しく獰猛で、ムニーラが予想だにしていなかった勇気で輝く瞳。安らかならざる死者の、胡乱な目ではなかった。
「ありがとう、父さんが教えてくれたの」幽霊が言った。ふたりはお互いの周りを回った。父親が戦い方を教えたって? でも人間は娘に武術を教えないんじゃない? 幽霊はムニーラの混乱を見てとったに違いない。跳躍して間合いを詰めた幽霊に打撃を加えられ、ムニーラは息を整えるため後ろに跳びすさるしかなかった。幽霊は短剣で柘榴を木から切り落とし、刃を持ち替えて果実を切り裂いた。濃紅の果汁が飛び散って彼女の手を染めた。長く優美な指で果実の中を器用にまさぐり、ひと粒を取り出す。
「楽園からの種が、かならずひとつ入っている」幽霊はそう言って、つまみだした粒をムニーラに差し出した。彼女は逡巡ののちに手を伸ばした。幽霊は後ろにさがり、ほほえむ。「キスをして、それから何が見えるか見てみましょう」
ムニーラが幽霊を見下ろすと、彼女の周りで輝く後光に眼を灼かれてしまいそうだった。身を乗り出して、そっとキスをする。彼女の肌は驚くほど熱く、柔らかだった。白檀のような香りがする。光がバラカの滝となってムニーラに注ぎこんだ。巻きこまれ、溺れて、幸福の中に屈服する。意識の逸れた手から半月刀が滑り落ちた。もつれる足で幽霊に近づき、柘榴の木に押しつけるように抱擁する。幽霊の放つ神聖さにムニーラは圧倒された。両手で幽霊の硬い鎖骨をなぞり、顎を包んで上を向かせてもう一度キスをして、崇高な力の奔流をより深く、夢中で飲みこんだ。
ムニーラが息をついてキスが終わると幽霊は身を引き、手の中にある柘榴の粒を確かめた。「ほら、見て」眼を向けると、彼女は幽霊などではなかった。この女性は、この存在は、聖女だったのだ。ムニーラは後ずさりしながら、聖女が粒をつまんでムニーラの口に入れるのを見ていた。魅力的でとても、とても甘い粒だった。
「また明日おいで。もうひとつあげるよ。覚えておいて、全ての果実には天国からのひと粒が潜んでいる」聖女は言った。ムニーラは重たげな柘榴の実のついた木に眼をやって、微笑んだ。
ムニーラは何度もそこに戻った。「枕を持ってきたよ。地面よりもこっちの方が寝心地がいいと思って」彼女は枕をふたりの寝床になるようにしつらえた。聖女が先に横になり、ムニーラを手招きした。本物の月明かりの下で、夜更けまでふたりは語り合った。
聖女はムニーラと額同士をくっつけて、優しい慈しみの微笑を浮かべた。「言いたかったことがあるんだけど……。月と間違えて語った打ち明け話を私が聞いていたと知ったとき、きみはあまりにも動揺していたよね。あまりにも空っぽでかなしげな声をしていた。それでね、実は私も空っぽだったんだ。漂っているうちに、この木を見つけて棲みついた。礼拝者が来て印を残していくけれど、かれらは私じゃなくてバラカの海に祈っていた。私がいることすら知らないんだ」
「いったいどうしたらきみが空っぽだなんてことになるの?」ムニーラは眉をひそめた。聖女は腕をひらいてムニーラを抱き寄せ、こめかみに優しくキスをした。
「きみだって」聖女が言った。ムニーラは目を細め、聖女が言ったこと、ふたりのあいだに起きたことを思い返した。そして何も言わずに聖女の力強い腕を撫でた。聖女はムニーラの眉間にかかった髪をそっと払って抱き寄せた。
「ねえ、どうしてきみの人間としての生は終わったの?」とムニーラは勇気をかき集めて訊いてみた。聖女はムニーラから手をどけて、トーブの裾の、なめらかな白を縁取る深紅をなぞった。「もしかして……殉教したの?」聖女は頷いた。
「何が起こったか、もう気づいてると思うけど」ムニーラが眉根を寄せると、聖女は続けた。「自分らしくいるために殉教する者はよくいるんだ。とくに家族の義務や命令に背いて、結婚を拒否したときにはね。私もそうだった」
「私が孤独について話していたとき、本当に辛抱強く聞いてくれたね」ムニーラは恥ずかしげに眼を逸らし、それからまた真面目な顔で彼女の顔を見た。「きみは独身でいるために命を失ったのに。私が言ってたこと、すごくひとりよがりだったよね」
聖女は首を横に振った。「私の家族もそう考えたけど、それは違うよ。私は独身でいたかったんじゃなくて、自分らしく愛したかっただけ。同情も恥ずかしいことも何もない。そんなこと、軽々と超えてきたじゃない。好きだよ、ムニーラ。こうやっていられて、愛することができて、私は本当に恵まれている。これ以上何を望むっていうの」
ムニーラの眼に涙が溢れた。あまやかな温もりが体を満たした。必要とされ、全てを受け入れられ、大事にされるのは生まれて初めてのことだった。聖女の手をとって、月から彼女を覆い隠すように身を寄せる。もらったすべてを彼女に返すことができることもわかっていた。そう信じていた。
◇
パレスチナでは、「聖女/聖人(saint)」という言葉はどの宗教においても使われます。
ソニアさんによると、作中の「聖女」はキリスト教徒です。キリスト教の寓話には、多神教を信仰する王や権力者の子どもがキリスト教徒となり、多神教徒との結婚を拒んだために殺されるが、奇蹟が起きて聖人となって生き返るという形式のものが数多くあります。この物語は、現実のパレスチナの世情を反映したものではなく、キリスト教の神への献身を説く物語になぞらえたお話です。
告知
「パレスチナ特集」特集 掲載作品
作品をより楽しみたい方は、マガジン『Kaguya Planet No.2 パレスチナ』をお読みください。詳細はこちらから。
先行公開日:2024年4月26日 一般公開日:2024年7月16日
カバーデザイン:VGプラスデザイン部
"Muneera and the Moon" by Sonia Sulaiman.
First published in FIYAH , 2022 ©Sonia Sulaiman
Translated with the permission of the author.

ソニア・スライマーン著者
ソニア・スライマーン著者
パレスチナ系、アメリカ在住の作家。パレスチナの民話や伝承を題材としたファンタジーやSF作品を多く発表している。作品は英語で読めるアラブの文芸を紹介しているメディアArablit、アフリカ系作家によるSF雑誌FIYAHのパレスチナ特集、そのほかFANTASY Magazine、Lackington’sなどさまざまな媒体に掲載されている。
1993年生まれ、北海道出身。編集者、ブックキュレーター、ライター。得意分野は海外文学。「岸谷薄荷」名義で、ジェーン・エスペンソン「ペイン・ガン ある男のノーベル賞受賞式に向けたメモ」、 R・B・レンバーグ「砂漠のガラス細工と雪国の宝石」(いずれもKaguya Planetに掲載)、ジェニー・カッツォーラ「パーティトーク」(井上彼方・紅坂紫編『結晶するプリズム 翻訳クィアSFアンソロジー』収録)の翻訳や創作を行ってきた。フェミニスト。
佐佐藤まな監修
佐藤まな監修
英語翻訳者。主な翻訳作品に映画『鉄道運転士の花束』『リトル・パレスティナ』(日本語字幕)、ジェームズ・ウェルカー編著『BLが開く扉 変容するアジアのセクシュアリティとジェンダー』(青土社/2019)(共訳)など。『現代詩手帖』2024年5月号「パレスチナ詩アンソロジー 抵抗の声を聴く」に翻訳・解題などで参加。
